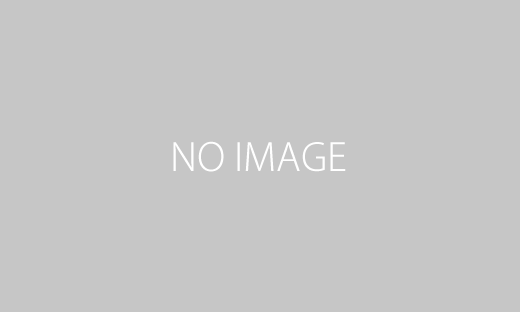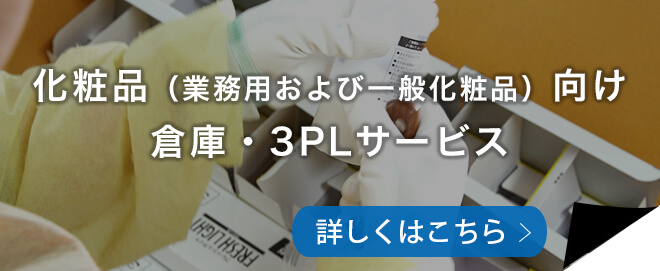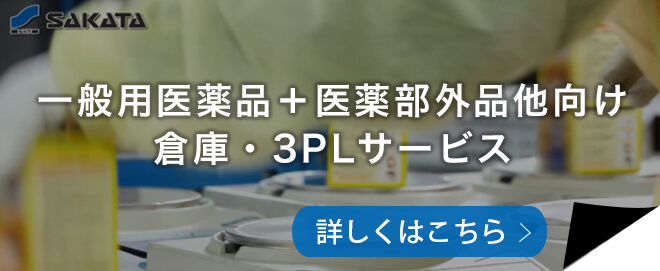第542号 「過剰サービスにはお金がかかる」(2024年10月22日発行)
| 執筆者 | 山田 健 (中小企業診断士 流通経済大学/文教大学非常勤講師) |
|---|
執筆者略歴 ▼
目次
- episode1:ジャストインタイムの宅配便
- episode2:自社宅配便
宅配便草創期のことでもう時効だと思うので、今回のテーマである「物流の過剰サービス」にまつわるエピソードを2つほど紹介したい。
episode1:ジャストインタイムの宅配便
1つ目は、筆者が営業担当として勤務していた物流会社の地方支店での話である。荷主は大手酒類飲料メーカー。支店の最大荷主である。仮にA社としておこう。
A社では得意先の問屋(特約店)向けに新製品発売キャンペーンを定期的に実施していた。新製品のパンフレットと小売りに配る注文書のセットを特約店に配布するである。
はたから見ればただのキャンペーンに過ぎないと思われるかもしれないが、実際はかなり大がかりなイベントである。A社は特約店に配布する順番と時間を厳密に定めていた。それはA社にとっての重要度や販売戦略など特約店の「格付け」「順位付け」によるものであり、これを間違えると大事になる。
特約店にとっては新製品の発表・発売は重要な販売機会である。営業マンは入手と同時にパンフレットと注文書を携え一斉に小売店へ注文取りに走る。特約店の営業テリトリーはだいたい決まっているのだが、ときに営業マンはあわよくばテリトリー外の小売りまで足を延ばして「抜け駆け」しようとすることもあった。一定のルールがあるなかでの「仁義なき戦い」である。こうした「越境営業」を避けるためにち密に計画された配達時間と順番なのである。業界外の人間からしたらあずかり知るすべもない「暗黙の」商慣習といえる。
さて、物流会社はこの配布業務をまだ誕生間もない宅配便で請け負っていた。現場には分刻みの配達時間表が配られ、同様の情報は宅配伝票にも記載されている。
実際は配達時間、順番は指定通りにならなかった。よそより早くセットを入手できた営業マンはまず自社のテリトリー内への注文取りを行う。それが終わると次にテリトリー外へ足を伸ばしていく。配達順番を狂わされた(遅らされた)特約店の営業マンが担当先を訪問する頃にはすでに抜け駆けされている。営業マンとしては、注文取りに行った先がすでに他の特約店に発注しているわけであるから重大事である。
と、荷主からの説明をそのまま述べているが、正直いま一つ納得感には乏しい。指定時間通りに届けていればなぜそのような事態が起こらないのか、やはり同じようなことは起こりうるのではないか、など疑問は出てくるが部外者にはそのあたりの詳しい事情はわからない。
とにもかくにも、「メーカーが掟を破った」ことで、その怒りはメーカーへ向けられる。A社はこうした事態を招かぬよう、売上げなど自社への貢献度を十分に配慮した上で優先度に応じた順序と時間などを定めていると聞く。
こう書いてくると、ただの配達上のクレームと思われるかもしれないが、実際はそんな生易しいものではない。想像できないかもしれないが、他のクレーム、たとえば納品先への遅配や誤配、商品の破損といった通常(?)のトラブルとはくらべものにならないほど厳しく激しいクレームが担当営業の筆者の元へ寄せられることになる。A社にとっては大切な顧客の信頼と自社の面子を失う二重の意味での「決して許されない」トラブルなのである。
このあたりの事情は、大手チェーン店やコンビニなどによる電子発注が当たり前になった現在では理解不能の商習慣かもしれない。当時でさえ、なぜこれほど怒られなければならないのか、筆者自身もよくわかっていなかった。決して褒められたことではないが、トラブルを重ねる(!)なかで、いやでも叩き込まれていった当時の地方酒類流通業界で厳然と存在していた「掟」なのである。
いまでこそ宅配の時間指定は当たり前になったが、それでも1時間単位の「時間帯」指定である。商品としての時間指定宅配が登場するはるか以前に分単位での時間指定配達を行っていたわけであるから、ある意味先進的な(?)取り組みといえるかもしれない。一方で、草創期とはいえ、一日に100個以上の配達をこなさなければならならず、昼食をとる時間も惜しむドライバーに、自分で組み立てた配送順や時間などを根底から覆してしまうジャストインタイム指定など土台無理な要求である。トラブルとクレームのたびに筆者が書いた「お詫びと対策」文書は数えきれない。
結局のところ、宅配ドライバーには任せられないということで、キャンペーンのたびに現場の管理職や事務員が総出で配達する羽目になった。きちんと計算すれば、単価数百円の宅配便の配達コストは数万円規模に膨れ上がっていたことであろう。
これは本来「レディーメイド(既製服)」であるはずの宅配便に「オーダーメイド(注文服)」の仕様を求めた結果の悲劇である。
営業を引き継いだ時にはすでに定着してしまっていた業務ではあるが、それまで主に海運畑を歩んできた筆者にとっては、違和感を拭えなかった。宅配の仕組みについての知識も不足しており、最大の荷主の業務であることから、疑問を呈する余裕もなくひたすらこなしていたのが本当のところである。これが、荷主の指示通りに業務を遂行することが絶対とされていた当時の物流業界にとっての常識であった。
仮に異議を唱えでもしたら、荷主には「出入り禁止」処分、支店にもいづらくなっただろう。
今でこそ、費用負担を別にすれば個人事業主の軽トラック(赤帽など)をチャーターすれなど、やり方はいくらでもあったと思う。決められた業務をこなすのに精いっぱいだった当時の筆者にはそのような知恵がなかったことはお恥ずかしい限りである。
episode2:自社宅配便
2つ目は、episode1をさかのぼることさらに数年、担当ではなかったが筆者の所属していた総合商社の営業窓口でのできごとである。
ある大手総合商社は、飲料の訪問販売員を介した通信販売を企画していた。最近でこそ、コンビニやスーパー、外食など総合商社の「川下」への進出は珍しくないが、外国での資源開発や原材料輸入、鉄鋼など素材系物資の販売、プラント輸出など「川上」を主戦場としていた当時の総合商社にとって、消費者向けビジネスへの参入はきわめてチャレンジングな取り組みである。
方法もユニークである。インターネットなど登場する以前の通信販売は、家庭へ郵送するカタログをチャネル媒体として注文を集めるのが普通であった。そこへ、毎日のように家庭を訪問している飲料販売員を介してアパレルや家電のカタログを届けながら対面セールスも行うというのである。カタログ販売の品揃えの広さと訪問販売がもつ対面という、それぞれの強みを生かした販売戦略である。やがて総合商社はこのビジネスを行うため、飲料販売会社と共同出資の通信販売会社(仮にB社とする)を設立するに至る。受注した商品の配達を担うのが宅配便である。
もっとも、販売方法はユニークなものの、宅配という作業自体に代わり映えはなく、せいぜい、初期の宅配便特有の配達トラブルなどはいろいろあっただろうとの想像はできるかもしれない。
ところが、要求された配達方法もまたユニークであった。配達員は届け先で商品を引き渡す際に「B社からご注文の商品をお届けに参りました」と挨拶することが求められた。宅配会社ではなく、あくまでもB社の一員として配達する決まりだったのである。いわば自社物流に近いサービスである。
このハードルはけた違いに高い。世界一のサービス水準を誇る現在の宅配便でさえここまでの「個別対応」は提供していない。せいぜい、デリバリープロバイダーなど特定のEC企業専門の軽トラック個人事業主でならどうか、というレベルである。実際に今でもEC企業名を名乗っているケースはないように思われる。ネット通販が定着した現在では、顧客としては配達員が宅配業者だろうがEC企業だろうが、あまり関係ないであろう。
まったく新しいビジネスという気負いもあったのかもしれないが、とにかく通信販売会社B社は配達時の「挨拶」の徹底を強く要求した。そのような要求は無謀だということは誰もがわかるかもしれないが、誕生間もない当時の宅配便について、荷主はおろか物流会社でさえもサービス内容や仕組みをよく理解していなかったのではないか。
指示文書を全国の支店、営業所に流してみたものの、何万人といる配達員への周知徹底などそう簡単にできるものではない。配達員にとっては配達する100個のひとつでしかなく、伝票にその旨記載があったとしても見逃したり、そもそも理解できなかったりで「挨拶」はほとんど実行されることはなかった。レディーメイドの商品に個別対応(オーダーメイド)を求めること自体が無理なのはepisode1と同じである。
もっとも挨拶がなかったといって顧客からクレームが寄せられるわけではない。クレームは通信販売会社B社の社員、関係者から上がってきた。当然のことながら社員は販促として自社の商品を購入するので、配達時の挨拶がないことに気づく。そこからはお決まりのクレームの嵐である。
物流会社の営業は、クレームを受けた支店、営業所を回って指示の徹底を説いて回るが所詮もぐらたたき、焼け石に水である。こうした「クレーム潰し」は一定以上の物量を伴う荷主の場合は、ある程度有効な場合がある。配達員も頻繁に対象に接することから意識付も可能である。ところが結果からいえば、残念なことに当該の通信販売は期待した売り上げを上げることができなかった。物量も少なく配達員にほとんど認識されることもなく、数年で会社は解散となってしまった。時代に先んじる発想は面白かったが、少々早すぎたのかもしれない。
●過剰サービスとは
取り上げてきた事例は典型的な過剰物流サービスである。繰り返すが、そもそも宅配便は設定されたサービス条件を理解し、そのインフラを活用することによって適正な料金が成り立つ「レディーメイド」の物流商品である。そこに提供メニューにない「オーダーメイド」的な個別サービスを盛り込もうとした結果招いた不幸な例といえる。
そもそも過剰サービスという表現は適切ではないかもしれない。様々な物流サービスを提供すること自体は否定されるものではない。ゴルフ宅配便やスキー宅配便、家具の配達と組立、物流センターでのさまざまな流通加工などの例を挙げるまでもなく、物流は新しいサービスを開発し、提供することで顧客満足度を向上させ、進化してきた。
問題は、サービスに見合った対価を得ていない、払っていないことにある。対価に見合わないサービスが「過剰サービス」である。
先の「ジャストインタイム宅配便」や「自社宅配便」の例では、現実にこれだけの要求レベルを満たすにはラストワンマイル部分は荷主専用のチャーター便を仕立てるのが妥当である。そしてその対価を支払えば何ら問題ないのである。実際、それだけのコストをかけて行う価値があるのか、採算が取れるのかなどを最終的に荷主が判断すればよいのである(もちろん現在では十分な作業戦力が確保できるかどうかも重要な判断要素であるが)。これほど極端ではないものの、物流現場では十分な対価を得られていない過剰サービスは今でも枚挙に暇がない。
ただ断っておくが、突発的に発生するイレギュラーなサービスまで杓子定規にお金を払えといっているわけではない。物流現場では、予想外のトラブルへの対処として荷主に頼みこまれて緊急に対応する場面はよくある。こうしたサービス提供は信頼関係を築くうえできわめて重要な要素であり、「貸しを作る」といった打算抜きに誠心誠意手を尽くすべきである。緊急事態への対応は一歩間違えれば物流事業者にとって致命的な評価を招くこともあるので、「有料サービス」はあくまでも定型的に発生する業務が対象であることに十分留意する必要がある。
●正確な原価をつかむ
では、こうした過剰サービスを解消するには何が必要なのか。「これを行えばすべて解決」といった決定的な方法は残念ながら見いだせない。根底には荷主と物流事業者の(対等でない)関係が厳然として存在するからである。ただ、少しずつではあるが前進させていく希望がないことはない。背景にあるのが、言わずと知れた昨今の「ドライバーの2024年問題」と「人手不足」である。
こうした背景により、荷主が物流事業者の要求に聞く耳を持ってくれる環境は整ってきている。世間の目も無視できない。要求したからといって、少なくともかつてのように「出禁」処分をくらうことはないだろう。まずは「過剰サービスにはお金がかかる」ことを理解してもらう努力をするべきである。
そのうえで物流事業者に求められるのは、提供するサービスに対する正確な原価計算である。当時は筆者もそうだったので人のことはいえないが、物流事業者の原価計算は相当アバウトである。「ジャストインタイム宅配便」の例でいえば、管理者による配達の原価を明らかにすることもなく、「他の作業で儲けさせてもらっているからいいだろう」くらいの軽い気持ちで請け負っていたのである。いわゆる「どんぶり勘定」である。正確な原価計算ができないところに「適正な料金設定」などできるわけもない。交渉の土俵にも上がれない。まずは正確な原価計算を行うことが第一歩である。
他の業界では、一見低い料金を提示しながらも、実はしっかり儲けている事例はたくさんある。よく知られているのが家庭用プリンターである。たしかに市販のプリンターはとても安い。安いからといって気軽に買うと、あとから補充する純正インクの高価さに驚く。気が付いたらプリンターの値段をはるかに超すインク代を払っている。安いからと純正でないインクを使うと結構とんでもないことになったりする。これは決してどんぶり勘定ではなく、プリンター販売の赤字分を補って余りある補充インクの販売の儲けがしたたかに計算された戦略なのである。
ここでは詳細に述べられないが、一口に物流原価計算といってもそう簡単ではない。現場作業にかかわる直接費の計算はまだしも、間接費である事務所費用や管理費、利益など共通コストの原価への適切な配分が求められる。確立された原価計算手法にもとづき正確に計算しないと誤った原価を算出してしまう(筆者は物流原価算出に関する研修を行っており、いずれこの場でも紹介したい)。
正確な原価計算と、そして何より「過剰サービスにはお金がかかる」という認識を荷主、物流事業者双方が持つこと、それがすべての出発点である。
(C)2024 Takeshi Yamada & Sakata Warehouse, Inc.