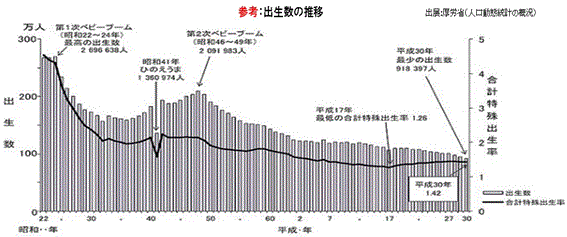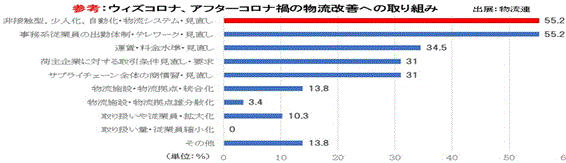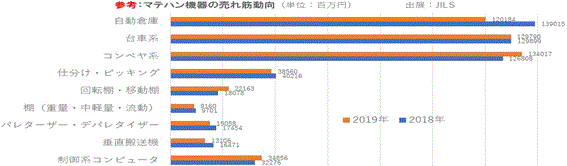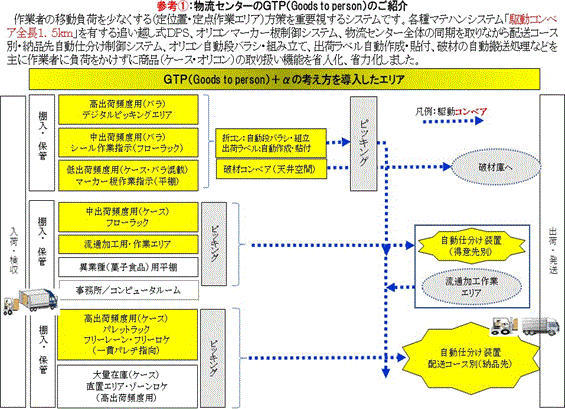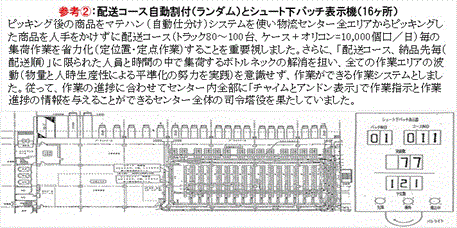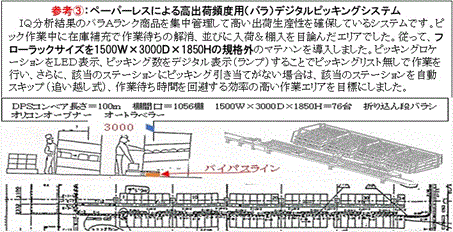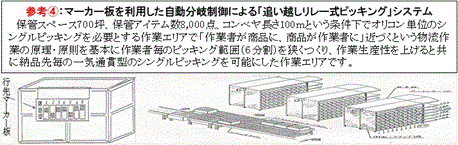第469号 物流現場の省人化、省力化とGTP(Goods To Person)を考える。(2021年10月7日発行)
| 執筆者 | 髙野 潔 |
|---|
執筆者略歴 ▼
目次
- 1.はじめに。
- 2.物流現場で高まる省人化ニーズ
- 3.物流現場の省力化と省人化について
- 4.費用対効果を策定しながら物流分野の自動化、省力化を進めたい
- 5.メーカー、卸・流通系のオペレーション別、省力化・少人化を考える
- 6.省人化、省力化を意識したGTP事例のご紹介
- 7.最後に・・・。
1.はじめに…。
人口減少社会が確実に迫っています。人口減少社会とは、出生率の低下などを背景に人口が少なくなっていく社会のことです。色々な複合的な理由がありますが、具体的には未婚化、晩婚化、晩産化、夫婦出生力の低下に起因していると言われています。
さらに、大きな特徴として少子化や平均寿命の長寿化に伴い、死亡率が低下して高齢化が進んでいること、出生者数が継続的に死亡者数を下回る状態が続いており、人口が減少し続けているのが原因と言われています。特に経済的な負担感として子育てにかかる教育費用(保育園、幼稚園から大学卒業まで)の負担を重圧に感じている人が多いようです。
これから確実に訪れ避けられない人口の減少により、日本経済の成長や社会保障制度の維持などと共に企業活動にも大きな影響を与えるのは必至と言われています。少子高齢化が急速に進む物流業界は、人口減少の中で大企業、中小企業を問わず、人手を省力化する自動化、省人化システムが求められています。
果たしてそれだけで競争力は高まるのでしょうか、単に人を省力化するために自動化(マテハンシステム)設備やロボットを導入しても同じように自動化した企業同士では、投資負担で差を広げるのではないかと考えます。
こうした問題意識から省人化、自動化を超える自社に合った「競争力を生む自動化」を導き出す時代になったと考えます。そこで、物流センターの中で必要となる省人化、省力化+GTP(Goods To Person)を検討し、「価値」を加えた省人化、省力化に迫りたいと思います。
2.物流現場で高まる省人化ニーズ
コロナ禍の中、人口減少やインターネットショッピングなどによる需要拡大を背景に、物流業界は人材不足、人手不足に直面したり、関係者がコロナ禍に遭遇しても何とか稼働を維持しています。そこに「止められない」物流事情が垣間見えるようです。
さて、製造現場では早くから生産工程の自動化(ファクトリーオートメーション)が進められていますが、物流現場では、これからというのが現状のようです。そんな中、大手物流企業や通販業界では、自動倉庫システムを中心に、自動化が進んでいます。さらに、人手不足を見越した物流分野の自動化、省力化が認識され、AGV(無人搬送台車)や次世代物流ロボット、パワーアシストスーツ、ドローンといった新しいテクノロジーが、スタートしています。これからの物流市場にどのように拡大していくのかが楽しみです。
さらに、これからの物流現場でのIOT(Internet of Things)やAI(人工知能)も様々な活用が進むものと期待しています。製造業と違い物流業(中間流通業)の自動化の取り組みは「人とマテハン」が相互補完できる物流現場が必須と考えます。倉庫内の荷物の搬送のみならず省力化、省人化システムを考えてみたく思います。
物流連が物流の現場がどのような課題を抱えているかの把握と人手不足や自動化に対するニーズに関するアンケート調査を行いました。第一位は、自動化でした。この調査で大手に限らず中小企業を含めた各社が、労働力不足の打開策として自動化機器やロボットの活用に関する検討を始めているといった状況がありました。
物流現場の省人化は、製造現場に比べると圧倒的に自動化が遅れていると指摘されています。製造現場は、「FA」と言われる自動化が進んでいますが、物流現場は、まだ人に依存している部分が多く、労働集約型の典型的な業界だと言われています。物流現場の省人化は、先ず全体最適を追求しながら部分的に最適化していくことが望まれます。導入にあたり壁になるのは、やはり投資資金の問題です。費用対効果を確認しながらの導入が必須と考えます。また、自動化システム(ロボットなど)といえども万能ではなく不得手とする業務も沢山あります。だからこそ、部分的でも良し、物流業界の人的リスクを省力化システム(仕組み)、省人化機器(マテハン)で解決したいものです。
3.物流現場の省力化と省人化について。
省力化は、「(人の)力を省く」と書くように、作業を見直して、無駄を省くことによって、効率化を上げることです。同じ成果でも人数を省くことでコスト削減につなげます。省力化の目的は、手間や労力をできるだけ省くことです。省人化とは業務を見直して無駄な工程を削減して人員を減少させることです。
人手不足の中で物流現場は、長時間労働や作業人員を減らしてコスト削減のために無駄をできるだけ削減することが求められています。そこで、人を省く、つまり、物流現場に「省力化のための省力化システム(仕組み)」と「省人化のための省人化機器」などを導入し、人と省力化システム、人と省人化機器が融合して人の代わりに作業の代行を行い業務の効率化を図りたいものです。
日本は人口減少社会に突入しています。働き手の減少で高齢化社会が進んでいます。特に物流業界は、EC(イーコマース)の普及とインターネットショッピングの需要拡大で取り扱い物量がうなぎ上りです。そのために宅配便の人材不足、労働環境の問題が多く取り上げられています。物流部門では人口が年々減少する中で生産性の向上と省人化の両立を達成すべきと思っています。そのような課題を解決していくのが「省力化システム(仕組み)」と省人化機器であると考えます。大手に限らず中小企業を含めた各社が労働力不足の打開策を試みる自動化機器やロボット化の活用をしたいものです。
物流業務には、自動化システムやロボット化に取り組み易い業種と取り組みにくい業種があります。熟慮して取り組むことが肝要と考えます。物流業界に於ける自動化の実現の時期は、まだまだ、先になると思われますが現在の物流現場の様々な課題の解決に繋がる重要工程の省力化、省人化の強化に繋がる投資からスタートしたいものです。投資対象としてロジスティクスファシリティ(自動倉庫、自動仕分け、自動搬送など)、ロボティクスオートメーション(AGV、物流ロボット、パレタイズロボ、物流向けパワーアシストスーツ、物流向けドローンなど)、IOT(デジタルピッキング、物流倉庫管理システム「WMS/TMS」、スマートグラス、宅配ボックス、トラックシェアリングなど)、AI(トラックの自動運転、AI音声システム、AI画像認識システムなど)の次世代・物流システムなどの市場規模の拡大を見込んでいます。
4.費用対効果を策定しながら物流分野の自動化、省力化を進めたい。
私は、自動車メーカーの情報システム部門に入社、生産工場の設立準備室、工場完成後、単一の物流拠点としては、日本最大級規模の敷地面積420,000㎡(≒127,000坪)のサービス部品・補修部品専用の物流拠点の開発プロジェクトとして18年間、参画する機会に恵まれました。東洋一の自動車部品物流拠点10棟のうち、自動倉庫6棟のシステム(仕組み)と輸出の効率化、自動バンニングなどを目指した平屋と自動倉庫を融合した輸出流通基地(川崎市東扇島)の開発プロジェクトにも参画する機会に恵まれました。開発したシステム(仕組み)は大型自動倉庫システム(仕組み)と自動搬送台車を融合した物流現場機能システムの開発、日本経済の「行け行けドンドン」の時代、モーターリゼーションと情報系の想定以上の進展で物流量と情報処理量の増加に対応する制御系と基幹系とのインターフェイスシステム、さらに、パネル自動倉庫(22,000棚)と小物自動倉庫(49,000棚)2棟に絡む難易度の高い増設を経験しました。そして、127,000坪の敷地をフル活用した自動化・自動制御システム(仕組み)の開発に18年間携わりました。
これからの人手不足を補う物流業界の対応は急展開、物流の省人化・省力化への変革は、自動倉庫システム・自動化制御システムが主役と言われています。さて、ウィズコロナは、私達の生活や仕事の有り様を今までとは大きく変えていくと言われています。最近は、省人化や省力化に関する話題がかなり多くなりましたが、中堅・中小企業や通販関係に於ける商品特性上の自動化し易い側面を持っている企業が様々な取組みを積極果敢に行っています。
一方で、卸業(流通系)が担っている複雑な物流業務を、全て自動化して一気通貫の仕組みに到達するには、暫く時間がかかりそうです。そうしたものを目指すには、最終的には、無人搬送台車、自動倉庫、ピッキングロボットなどを連動させる制御装置と情報をネットワークでつなぎ、WMS等のシステムで一括制御する必要があると考えます。現状は、各工程毎や部分的な自動化、省力化に留まっています。しかしながら、商品の形状によっては自動化しやすいものがあるほか、マテハンメーカーでも様々な自動化製品を提供してくれており、適性や効果が認められる部分に対しては、費用対効果を策定しながら導入にチャレンジし、同業他社よりも付加価値を高めて競争優位性を確保していくべきだと考えています。
5.メーカー、卸・流通系のオペレーション別、省人化・省力化を考える。
物流実務を大きく分けるとメーカー系と卸系(流通系)の現場実務のオペレーションがあると考えます。商品の取り扱い(入出荷)がサプライチェーンを意識するとメーカー系に近い物流オペレーションと卸系に近い物流オペレーションがあり、それぞれに省人化の対応を考えたいと思います。
メーカー系に近い物流では、取り扱い商品が規格化されているケースが多く自社製品の取り扱いが主要で管理し易くフルシステムの自動化(省人化、省力化)に取り組み易いと考えます。メーカー系の物流センターでは、次世代物流システムを駆使してフル自動化へ一気に舵を切るプランも十分想定されます。既に大手のメーカー系の工場では、「FA」の導入が進められている企業も多くなってきているようです。メーカー系の物流センターでは、「FA」のノウハウを活用して一気通貫型のフル自動化で省人化・省力化に繋げ易いと考えます。但し、費用対効果と需要変動・製品ラインアップの変更などに対応できるなどのシステムの柔軟性を考慮することが必要と考えます。
一方、卸系(流通系)に近い物流では、いきなりフル自動化はハードルが高いと考えています。リードタイムに厳しく、多数のメーカー品目を扱い、多品目で荷姿や個々の商品の流動量なども多様化します。さらに、取り扱う商品の新設、廃止など、変更も頻繁に行われ、物流実務(オペレーション)も納品先毎に納品条件が細分化されています。そこで、特定工程に着目し、優先度をつけて進めることで効果の大きい「人とマテハン」の相乗効果を期待したいものです。さらに、協調作業と汎用性を持たせる省人化、省力化が労働力不足の改善策に繋げ易いと考えます。
6.省人化、省力化を意識したGTP事例のご紹介
GTP(Goods To Person)とは、物流拠点(物流センター)において「ピッキング、棚入」などを行う場合、商品が作業者に近づくか、作業者が商品に近ずくなどの「定点・定位置」で作業する方法のことです。メリットとしては、作業者の歩行、動作範囲を狭くしたり、歩行距離を短くしたりして、作業の効率化、作業者の体力的なハードルを下げ、疲労を少なくすることです。GTPは、人手不足の対応にも効果が期待できると言われています。さらに、狭いエリアでの作業性の向上が可能で作業者の歩行動線に必要なスペースの削減によって、物流センター全体のスペースの削減が可能になります。デメリットは、ある程度の規模がないとスペース削減、コスト削減に繋げにくいことです。さらに、導入にあたっては、倉庫レイアウトの変更、オペレーションの見直しが必要になります。
GTPは、従来の物流拠点(物流センター)の業務の6割に当たるといわれている「歩く」という行為を大幅に省力化することができます。そこで、私が取り組んだホスト系システムと制御系システム&マテハン系システムの連動で省人化(自動化)、省力化を実現した好事例をご紹介したく想います。開発の狙いは、経営を継続するために売上を増やし、コストを下げるための物流の在り方を研究し、導入したことでした。トレードオフの関係にある売上増加と人員削減、在庫削減、100台前後の輸配送トラックの効率的な活用方策でした。さらに、納品時間の厳守と作業コストの削減、作業品質・精度、庫内作業全体の見える化(作業進捗)などで可視性を重視することで生産性を高めるための作業者の意識付けと作業待ちなどのムリ、ムラ、ムダを極力抑えるシステム(仕組み)づくりでした。
物流現場では、特に前述したムリ、ムラ、ムダを省くことを重要視し、物流センター(6,700坪)全体の出庫作業の平準化(人時生産性と人員体制)、配送量の集約化などを心がけました。配送エリア・同一商圏を基点に受注〆時間を1日当たり3回(①8:00、②10:30、③15:30)にして1台当たりの商品の集約化で配送量・積載量の集約化と効率化を狙いました。大手量販店や専用車両での単独納品、緊急オーダーなどは、当日処理、当日配送などの特別便を出して対応しました。
物流拠点(物流センター)の特徴として生命線である「庫内全体」に張りめぐらしたケースとオリコンの自動搬送コンベア(長さ延べ≒1.5km)と制御系コンピュータとを連動させた倉庫全体(6,700坪)からの出荷品の行先別の自動搬送でした。これは、配送コース(トラック)単位に配送時間帯を意識した出庫アルゴリズム(出庫の最適化)を駆使してトラック積込場に全倉庫(6,700坪)からの商品を最短の歩行で集荷できるようにしたことです。
物流拠点(物流センター)内に14ヶ所ある作業エリア毎の流速管理と人時生産性を加味した人員配置で日々の出庫アンバランスを極力抑え、出庫量のバランスが大幅に崩れた場合には、各エリアの人時生産性をもとに物量に応じた作業体制を組み換えることにより作業終了時間の均等化(残業の抑制)を優先し、適宜、作業体制の変更を行いました。
さらに、CCR(コンピュータ・コントロール・ルーム)による物流現場全体(全フロアー)の稼働状況を監視する司令塔役として制御系コンピュータとITV(監視テレビ)装置などを設置しました。この物流現場全体(全フロアー)の司令塔の役割は、ファイナル工程である「配送コース別(自動仕分け装置)積込作業場」の進捗状態をリアルタイムに把握しながら全フロアの投入可能な配送コース毎(トラック単位)の商品集荷の同期を取るシステム(現場アンドン表示、PC端末、CCR監視装置)の導入で商品集荷をスムーズに管理・進行できるようにしました。そこで、6,700坪の広い物流センターのGTPの事例(参考①~参考④)を参考にして頂ければ幸いです。商品をピッキングする作業場エリアの移動範囲、棚入れする作業エリアを狭くすることを重要視するために流速別管理と作業者の歩行を少なくする作業方策を重要視し、多くの作業人員を必要とする作業工程のボトルネックの解消に努めました。
GTPのメリットは作業者があちらこちらへと動かなくて済むようにすることで作業の効率化、と歩行距離を短く体力的なハードルを下げ、動き回る動線を限定し、商品保管を密にしてスペースの削減を図ることです。GTPを導入することにより、在庫管理アイテム数約100,000点の保管、出庫個口数約10,000個口/日(ケース+オリコン)の出庫、出荷配送車両台数約100台分の荷量をコントロールするためのスペースの効率化が可能になりました。さらに、物流センターの人手不足の対応の効果と作業生産性(効率化)の向上に期待が持てる効果、売上増加に寄与できる効果などが享受できる考え方が基本のバックボーンでした。デメリットは、ある程度の規模がなければコスト削減につながらないこと、導入にあたって物流センターの作業情報とマテハンの融合、物流センター全体の作業進捗の見える化などの開発に苦慮したことでした。
7.最後に…。
ウィズコロナ、アフターコロナ下で、物流量の波動が深刻化しはじめた物流業界では、物流拠点(物流センター)や配送業務などの様々な分野で自動化、半自動化、デジタル化などを駆使した省力化(効率化)、省人化(半自動化・自動化)の検討が行われています。国内の労働人口は減少の一途であり、さらに、ウィズコロナ後の労働環境とその労働力を補完するには、デジタル化、自動化・ロボット化など、有力な方策が必要との声が出ています。ただ、導入が目的ではなく何を享受したいのか、効果と目的を明確にしてチャレンジしたいものです。
自動化・ロボット化は人間と違い365日、24時間、故障しない限り働き、文句も言わずに辞めることもなく費用対効果を克服できれば導入のメリットが大きいと言われています。人手不足の特効薬は、いまだに見つからず、物流業界では自動化が大手企業(特にネット通販)中心に最善の策との判断からますます加速していくと思われます。こうした動きは、単に人手不足の解消に資するだけでなく中長期的には導入企業と未導入企業との競争力、収益力の優劣・格差に影響しかねません。物流業界の構造と先行きに激変をもたらす可能性を含んでいる自動化、省力化、GTPを含めて注目していきたいと思います。さらに、楽しみにしています。
以上
(C)2021 Kiyoshi Takano & Sakata Warehouse, Inc.