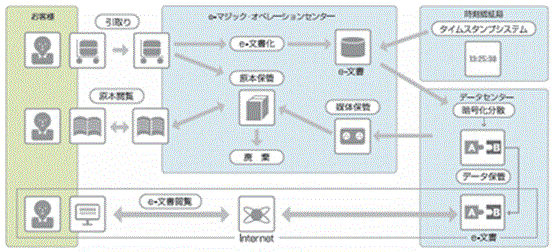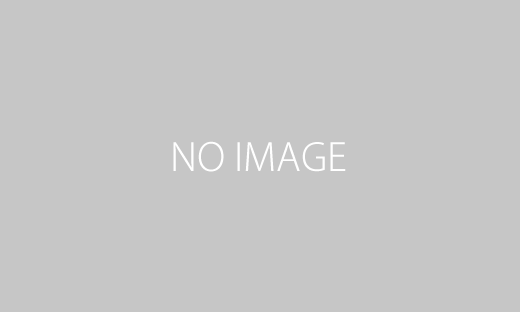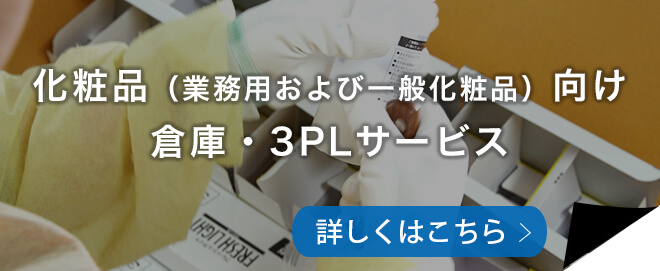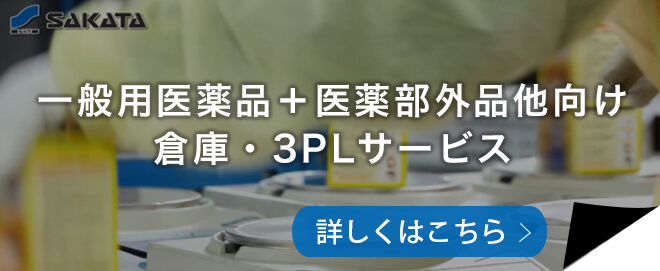第350号 わかりやすい戦略、わかりにくい戦略 (2016年10月18日発行)
| 執筆者 | 山田 健 (山田経営コンサルティング事務所代表 流通経済大学非常勤講師) |
|---|
執筆者略歴 ▼
目次
1.日立と佐川
報じられているように、佐川急便を傘下にするSGホールディングス(SGHD)が3月30日、日立物流と資本業務提携を発表した。陸運業界で3位と4位が提携することで、売上規模はヤマトホールディングスを抜き、合算規模では首位の日本通運に次ぐ2位グループとなる。いずれは経営統合も視野に入れているという。
今回の資本提携は、SGHDが日立製作所の保有する日立物流株(発行済み株式総数の29%)を、日立物流がSGHDの保有する佐川急便株(同20%、非上場)を、それぞれ市場外の相対取引で取得する。これによりSGHDは日立製作所(同30%)に続く、日立物流の第2位株主となる。
日立物流は、言わずと知れた3PLのリーディングカンパニーである。バックボーンとなる日立のDNAを受け継ぎ、物流情報システムなどITとデータにもとづく科学的な分析力、提案力には定評がある。物流業界では珍しく、理科系の学生の採用に積極的な企業でもある。
一方の佐川急便はあらためて説明するまでもなく、BtoB、BtoCを中心とした特別積み合せ便業界の雄である。荷主に従順(隷属的?)で横並び意識の強い物流企業が多い中にあって、「独立独歩」を貫くユニークな存在でもある。
なかでも、2013年に不採算を理由にアマゾンの宅配業務から撤退したのは関係者の間で語り草となっている。いくら料金が安いからといっても、桁違いの物量を持つ主要荷主との取引を打ち切るという判断は並大抵なことではできない。大口荷主であれば、少々の値下げでも甘んじて受け入れるのが、これまでの物流業界の常識だったからである。筆者などは無責任ながら、その潔さに陰で快哉を叫んだ一人である。
もっとも、不採算の業務からドラスティックに撤退することは、欧米流の経営ではごく当たり前のことである。不採算業務に有効な手を打つことなく会社に損害を与えれば、経営者は株主から「不適格」の烙印を押されるし、訴訟を起こされることだってあり得る。荷主の無理な注文に従うことを、「顧客ニーズに応える」ことと考えれば一概に否定することはできないが、それも限度あってのことである。明らかに赤字となるような仕事を従来の延長戦上で我慢して続けるというのは、将来期待される大規模案件獲得の布石など、よほどの戦略的意図によるものでない限り、まず評価されない。そもそもただ値段を下げろというのは、厳密には顧客ニーズとはいえない。
物流業界には得てして一方的値下げなど、荷主の理不尽な要求を飲まざるを得ず、ダラダラと不採算あるいは低利益の業務を継続する傾向がある。その点で、筆者は先の佐川急便のアマゾン撤退などは、物流業界に勇気を与えるきわめて合理的な決断であると評価している。
両社の株式持ち合いが今後、経営統合まで発展するかは不透明である。SGHDには、3PLのハマキョーレックスとの資本提携を解消した「過去」もある。何よりも、日本を代表する一大企業グループの日立と、業界では異色といわれる佐川の間には企業文化の大きな壁もある。
ただ何はともあれ、順調に進めばITと企画提案力に武装された「保守本流3PL」と、機動的な全国配送ネットワークを持つ「足」を兼ね備えた巨大総合物流企業、3PLが誕生することになる。その点では、戦略意図がきわめてわかりやすい提携といえよう。
2.なぜいまトールなのか
日立物流と佐川の提携を「わかりやすい」と表現したのは、最近「わかりにくい」買収や提携が多いからである。断ってくが、これは公表資料の限りで筆者が「わかりにくい」と感じているにすぎない。本当は公表されておらず、外部からは計り知れない深い戦略的意図があるのかどうかは、もちろん不明である。
筆者がわかりにくいと感じる最たるものが、1年前に発表された日本郵便の豪トール買収である。6,200億円を投じたこの買収は物流業界では最大規模である。それにしてはこの話、当初から意図がよく理解できなかった。
豪トールはオーストラリアのメルボルンに本社を置く国際物流企業である。とくにアジア地域の国際物流に強みを持つ。従業員4万人というから、日本でいえば日本通運に匹敵する巨大物流企業である。主要業務は航空フォワーダー。近鉄エキスプレスや郵船ロジスティクスのような物流企業と想像できる。買収の目的は、日本郵便の国際物流事業への進出である。
一般的に企業買収の目的は2つある。1つは、既存事業の強化あるいは新規事業への進出にあたって、自社に不足している経営資源を手っ取り早く手に入れるためである。この場合、買収企業と既存事業との間にシナジー効果が期待できることが重要である。もう1つは、経営効率を高めたりリストラしたりして買収した企業価値を高め、より高く転売して利益をあげることである。後者は主に投資ファンドなどの戦略であるから、日本郵便の戦略はおそらく前者であろう。
大口荷主確保の第1弾として、イオンがPB商品で使うオーストラリア産牛肉を日本に輸入する際にトールを利用することが決まった(2016年7月8日付け日経新聞)。郵政グループの中でも収益力が弱い日本郵便としては、トールを足掛かりにアジアに展開する日本企業との取引を増やし、収益の柱に育てる考えという。イオンはTPPの発効もにらみ、今後は日本への輸入だけでなく、アジア各国間で商品や原料の相互供給を活発にする方針である。
わかりにくいのは、日本郵便が国際物流事業へ進出するのに、なぜいきなりオーストラリアの物流企業なのか、という点である。一般的に国際物流事業といえば国際フォワーディング業務が主である。国際フォワーディングとは、航空機や船舶(キャリア)を使って貨物を輸送する利用運送業務をさす。フォワーダーは、輸送に伴う集荷、配達、保管、通関など、各種付帯サービス、およびキャリアへの支払い運賃と荷主からの収受運賃の差額を収益源とする。
必然的にフォワーダーのコア業務はこの業務に係る戦力、および海外ネットワークと情報システムを駆使して国際物流全体をコントロールする総合力となる。日本からタイへの航空輸出を想定すれば、日本からの集荷、通関業務およびタイでの通関、配達業務がメインとなる。日本のフォワーダーは、通常日本国内でのこうした付帯サービスは自社の戦力により対応できるが、困るのは現地である。そこで、当初は現地フォワーダーと代理店契約を交わし業務委託することによって、日本から現地までの一貫輸送を実現する。必要に応じて現地に物流センターを設置する場合もある。順番としては、自社の駐在員事務所を設置して現地代理店を買収したり、さらには現地法人を設立したりすることによって、自前戦力としてのフォワーディング業務が可能となる。日通、近鉄、郵船など日本の主要フォワーダーのほとんどが、こうしたステップによって国際物流ネットワークを築き上げてきた。
日本郵便が国内のフォワーディング業務をすでに行っていて、アジア・オセアニア地域の現地戦力が不足しているためトールを買収したというなら話はわかる。それが、国内のフォワーディング経験も戦力もなく、いきなり海外フォワーダーを買収したのである。そもそも国際フォワーディングの荷主であるメーカー、商社などは日本郵政の物流部門であるゆうパック(宅配便)の顧客とはあまり重ならないので、大きなシナジーが期待できるとは思われない。
国際物流以前の問題としてさらにいえば、CtoCあるいはBtoCに軸足を置いてきた日本郵便が今後本格的にBtoBの物流に進出していこうと考えているのか。それも佐川のような特別積み合わせ便を主体とした小口貨物の分野なのか、あるいは日本通運や日立物流のような物流センターから輸送モードの選択まで総合的にマネジメントするソリューション型3PLの分野なのか。いずれの方向性にせよ、これまでの郵便、宅配とは大きく異なるインフラとノウハウ、手法が必要となる。
今回のイオンのように新たに日系の荷主を開拓していこうとする場合、主要どころはすでに大手フォワーダーに押さえられてしまっている中で、し烈な獲得競争が繰り広げられている現状では、よほど強みや魅力的な提案がない限り容易ではない。まして日本郵便ほどの巨大企業の収益を支えるほどの大口荷主の獲得となると決して容易ではない。日本を経由しない、アジア域内での三国間貿易も同様である。
同社は「事業を相互に補完できるパートナー」と豪トールを評価するが、現在のところ、連結対象としてトール社の利益が日本郵便の業績に上乗せされている以上の目立った効果は認識できない。
日本郵便の国内郵便・物流事業は、2015年4~12月期決算では前年同期の97億円の赤字から29億円の黒字に転換した。これまでの赤字の主因は、日本通運のペリカン便を吸収したゆうパックである。ペリカン便は1977年の開始以来一度も黒字を計上することなく、日本郵便と共同設立したJPエキスプレスを経て2011年に日本郵便に譲渡された。これも慢性的に不採算であったゆうパックと一緒になって以来、日本郵便の業績の足を引っ張ってきた。前記日本郵便の国際物流事業の営業利益は188億円とされているので、トール買収が黒字化の原動力となったのは間違いないだろう。
ただ、トール買収ののれん代(買収金額と総資産の差額)は、2015年末で4,700億円といわれる。これから20年間にわたって続く、単純計算で200億円以上ののれん代の償却負担は同社の経営に重くのしかかる。「国際物流の展望が見えない」などとアナリストに指摘される理由はここにある。
ちなみに、豪トール社の子会社に「トールエクスプレスジャパン」という国内物流企業がある。これは2009年にトールが、当時の特別積み合せ便会社「フットワークエクプレス」を買収して社名変更となった物流企業である。こちらもいまのところ、日本郵便が国内でトールエクスプレスジャパンと連携して特別積み合せ便業務に乗り出す、などといった方向性は示されていない。
3.ワンビシを買った日通
2015年12月、日本通運は、豊田自動織機の100%子会社である株式会社ワンビシアーカイブズの全株式を取得した。前2例に比べれば地味であるが、これもなかなかわりにくい。
ワンビシは、1966年に設立された書類やメディア保管に特化した物流会社である。官公庁・金融機関・医療機関などの機密性の高い、極めて重要な文書データの管理を担っている。2006年には豊田自動織機の出資を受け子会社となった。14年度の売上は211億円で経常利益は46億円、売上高経常利益率は22%である。一般的に物流会社の経常利益率はよくて3%前後であるから、業界の中では「超」高収益企業に属する。価格はともかくとして、商品としては価値ある買い物といえる。
書類やメディアの保管分野では、寺田倉庫が知られている。同社は文書からワイン、映像、美術品など、業界としてはニッチでユニークな分野での保管業務を営んでいる倉庫会社である。資本金1億円、年商140億円といった小規模ながら、明確な事業ドメインを持つ。同社の方向性を見ていると、もはや「モノを預かる」という従来の枠に収まらない、「情報管理を売る会社」に脱皮していると思えてくる。
ワンビシ、寺田倉庫に共通するのは貴重品保管や情報管理という高付加価値な分野に特化して高収益を上げている点である。セキュリティや施設面での高度なノウハウと投資が必要な反面、他の用途への転換が難しいことから大手はなかなか手を出しづらい分野でもある。機密情報を扱うことから、流出した場合のリスクも大きい。それなりの「覚悟」がなければ参入するのは難しい事業である。市場の規模もそれほど大きくはないので、日通をはじめ、倉庫大手各社もそれなりに手掛けてはいるものの、本格的に軸足を置いているとは言い難い。
さて、日通はワンビシを買収するにあたって、どのような戦略ストーリーを描いているのであろうか。日通も小規模ながらトランクルームや文書保管専用の倉庫を保有、運営している。また、書類をデータ化して保管する「eマジック」というサービスも提供している(図2参照)。
これら既存事業とワンビシのシナジーをどう高めていこうと考えているのだろうか。本格的に文書・データ保管分野への参入を考えているのであろうか。事業部などを設立して<この分野の強化を図る、などといった方針はあるのだろうか。
ワンビシの総資産309億円に対し、買収金額は860億円。差引のれん代が550億円近く発生する。現在の純利益が約26億円であるから、単純計算で元をとるのに21年以上かかる計算になる。現段階での公表資料からは、これほどの買い物をした割には明確な戦略が見えてこない。
2016年3月に同社が発表した3か年計画の重点戦略には、「国内事業の強化と新規事業軸の構築」が謳われている。そこには、自動車、引越、航空、海運など既存事業の強化が羅列されているが、「文書管理」や「情報管理」といった事業分野は見当たらない。重点戦略に位置付けない事業に860億円の投資を行ったということなのであろうか。
4.求められる「戦略性」
ストーリーがわかりやすい日立と佐川の提携と、わかりにくい日本郵便と豪トール、そして日通とワンビシ。繰り返すが、後者にも機密情報や高度な戦略的意図が隠されているのかもしれないし、本当に何もないのかもしれない。少なくとも一般株主にはわかりづらいことは間違いない。
ただ上場企業である限り、事業戦略を投資家にわかりやすく開示していく義務は避けられない。このままでは、キャッシュ・リッチな大手物流会社が銀行や証券会社にうまく乗せられた、などとあらぬ噂を立てられぬともいえない。
一橋大学の楠木建教授は、著書「ストーリーとしての競争戦略」の中で、「大きな成功を収め、その成功を持続している企業は、戦略が流れと動きを持ったストーリーとして組み立てられているという点で共通している」と述べ、筋の通った「面白い戦略ストーリー」の重要性を指摘している。
これまで物流業界が「事業ドメイン」や「戦略」に関心が薄かったのは事実である。荷主企業の要求を受け入れてさえいればそれなりに仕事が確保できる、といった「受注産業意識」が強かったことも否定できない。
しかし、業界を取り巻く環境はきわめて厳しい。物量は増えない中で構造的な人手不足は深刻化の一途をたどり緩和のきざしすら見えない。一方で荷主ニーズはますます高度化し、利益率は上がらない。業界を代表する大手企業の間でも、明確な戦略ストーリーによって大胆な提携、買収に挑むか否かによって格差が生じる時代が到来しつつある。
以上
(C)2016 Takeshi Yamada & Sakata Warehouse, Inc.