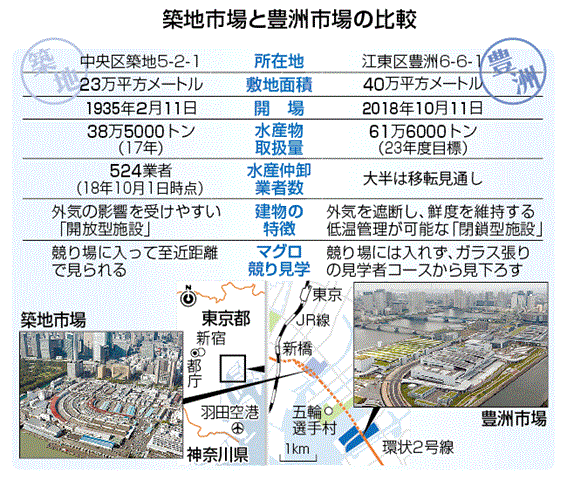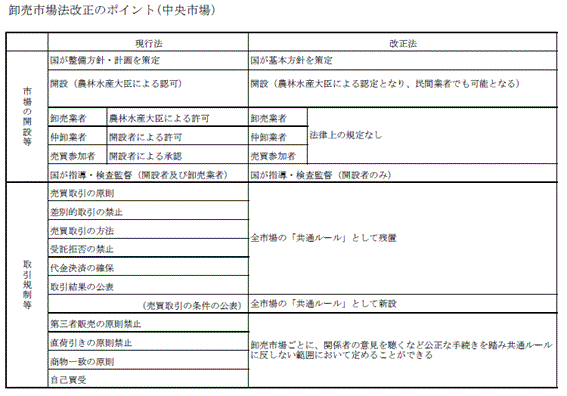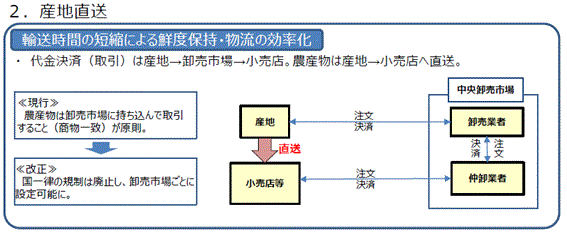第456号 卸売市場法改正と最近の生鮮食品流通(前編)(2021年3月16日発行)
| 執筆者 | 長谷川 雅行 (株式会社日通総合研究所 経済研究部 顧問) |
|---|
執筆者略歴 ▼
目次
1.はじめに
2018年2月の第381・382号で、「卸売市場を主体とした生鮮食品サプライチェーンの現状と課題」を報告させて頂いた(バックナンバー参照)。
その後、全国の水産物流通の中心である、東京都中央卸売市場の築地市場が豊洲市場に移転するとともに、2020年には改正卸売市場法が施行され、いよいよ生鮮食品流通については大きな変革が始まろうとしている。
既に、卸売市場が生鮮食品流通に占めるシェアは低下しており、大きな変化は起こらないという関係者もいる。
そこで、上記2大イベント「豊洲移転後」「卸売市場法改正」を中心に、最近の生鮮食品(農産物・水産物に限る)流通の動向や、物流業界への影響・対応等を述べたい。
2.開場2年を経た豊洲市場
2018年10月に築地市場が移転した豊洲市場は、開場2周年を迎えた。新旧両市場を比較したのが、図表1である。
*画像をClickすると拡大画像が見られます。
移転後は、築地市場当時と比較すると取扱量が減少している。築地市場が通年開場した最終年次である2017年の取扱量が385,004トン(図表1参照)であったのに対して、豊洲市場が初の通年開場となった2019年は346,212トンと、10%減少している。
2020年は、コロナ禍や不漁により、高級魚などを中心に取扱量が減少していると報道されている(2020年8月6日付日経新聞等)。
また、卸売業者(後述の「荷受」)は7社で変わらないものの、図表1の水産仲卸業者は524社から、488社に減少している(2019年4月現在)。移転を機に廃業した業者もあったようである。
仲卸は卸売業者(一次卸。荷受)から買った生鮮食品を小売店・飲食店に売る二次卸で、鮮度や品質に対する「目利き」と呼ばれる技術が不可欠で、経験年数が必要とされる。一方で、中小・零細の業者が多く、東京都によれば、2017年時点で約4割が経常赤字となっている。
東京都の中央卸売市場(大田・豊洲など11ヵ所)全体では、青果・水産・食肉・花きの仲卸業者は、2019年4月時点で976社と、近年は減少傾向が加速している。
このうち、豊洲市場は年間、346千トン・約4千億円の生鮮食品(2019年実績。一部青果も含む)を取扱う最大規模の中央卸売市場である。
東京という日本最大の消費地を控えて、荷(生鮮食品)が多く集まる大田・豊洲の両市場は、他の中央卸売市場・地方卸売市場で取引される参考となる価格を形成する「建値市場」としての役割もある。マグロやメロンは、豊洲や大田のセリ値が全国の取引価格を形成していると言っても過言ではない。
スーパーなどは卸売市場を通さず、産地の生産者(JA・漁協)等から直接仕入れるケース(市場外流通・相対取引)が増えている。その結果が、2項で述べる「生鮮食品流通占める卸売市場の取引シェアが3割」という実態を招いているとも言える。
その場合の相対価格も、大田や豊洲のセリ値が目安(大田のセリ値の○%引きなど)とされている。
この全国の価格指標だった高級魚・高級果物等の需要が、コロナ禍による外出自粛・巣ごもりにより「蒸発」したため、大田・豊洲の両市場関係者は、上述のように取扱量の減少に苦しんでいる(同様に、小売店・飲食店も苦しんでいる)。
また、中央卸売市場の物流面では、第382号で指摘したように、市場外流通(転送)の問題も大きい。大田・豊洲の大市場は、本来の東京都民向けよりも全国各地向けに転送する荷の集散地としての役割が大きいので、まさに方面別仕分けと積替えの「トラックターミナル」と化している。
先述の豊洲市場の2019年の年間取扱量346千トンを同年の開場日数258日(最近では、卸売市場も年間100日は休場する)で割ると、1日約1,400トンとなる、これは、セリや相対によって豊洲で「取引」される量である(豊洲で取引されない「通過」量は、市場の統計では把握できない)。豊洲を「通過」する量を加えれば、おそらくその2倍はあるだろうと言われている。
「取引」額に応じて施設利用料を収受している市場開設者(地方自治体)は、取引をしないで積み替えているだけの利用者(生産者・流通業者・物流業者等)からは施設利用料を収受できないことになる。「フリーライド(タダ乗り)の世界」だと、元築地市場長が嘆いていた。
さらに、物流面で言えば、生鮮食品の鮮度・品質を維持するために、市場施設を「開放型」から「閉鎖型」としたことである。「開放型」とは魚介類が外気に晒されている状態であり、閉鎖型とは市場施設全体が低温倉庫化したものである。近年の、「食の安全・安心」やHACCPからは当然のことであるが、仲卸業者等からは「電気代が高くなった」との声も強い。
豊洲市場の取扱量の実績は、開業時の目標616千トン(2023年)の56%(2019年)である。「築地の取扱量が減少していたのは、設備が狭隘で老朽したから」と6000億円を投じたのが豊洲市場である。
築地の1.7倍の面積(図表1参照)を誇る豊洲市場に移転したにもかかわらず、取扱量が減少するということは、「狭隘・老朽」が原因ではなく、
①後述する産直やネット販売等による、市場を経由しない「市場外流通」が増加していること
②国内での漁獲高が減少して、海外からの冷凍輸入水産物の比率が増加していること
②消費者の「魚離れ」により、魚介類の消費量も肉類に抜かれて減少傾向にあること
が挙げられる。
加えてコロナ禍により、高級魚を中心に取扱量が減少しており、2023年度の目標(616千トン)達成が懸念される。
3.卸売市場法の改正
(1)改正の経緯
2020年6月21日に改正・施行された卸売市場法のポイントについて、2項との関連で、水産部門を中心に述べたい。
なお、卸売市場、卸売市場を中心とする生鮮食品流通、卸売市場に関係するプレイヤー等については、上述の第381・382号を参照されたい。
上述の第382号では、卸売市場の機能として、以下の4つを挙げた。
①集荷・分荷機能
(全国各地から多種多様な商品を集荷するとともに、需要者のニーズに応じて、迅速かつ効率的に、必要な品目、量に分荷)
②価格形成機能
(需給を反映した迅速かつ公正な評価による透明性の高い価格形成)
③代金決済機能
(販売代金の迅速・確実な決済)
④情報受発信機能
(需給にかかわる情報を収集し、流通の川上・川下にそれぞれ伝達)
このうち②③④は、これだけICT化が進んだ今日、卸売市場に依存しなくても可能であろうということは、市場外流通の比率が高まっていることからも明らかである。
そして、卸売市場流通のシェアは既に3割でしかない。わが国の食料品輸入の増大を考慮すれば、実態はもっと低率であろう。市場外流通の発達で卸売市場法が形骸化していると言われている。形骸化しているのは法律よりも実態である。卸売市場数や卸売業者数も激減しているのが現状であり、原則的には禁止されているはずの第三者販売や直荷引きも行われているのが実態である。
改正前の卸売市場法による取引は、以下のような原則がある。
⑤受託拒否の禁止、即日全量入場、セリ・入札販売
中央卸売市場・地方卸売市場の卸売業者(以下、「荷受」。大卸ともいう)は卸売市場法で、産地から送られてくる生鮮食品を全量荷受け(委託集荷)しなければならず、「受託拒否の禁止」と言われている。
また、荷受した生鮮食品は、入荷当日に全量を売場に並べなくてはならず、「即日全量上場」と言われている。取引は、「セリ・入札販売」で行われる。
⑥第三者販売の原則禁止
荷受は、原則として仲卸業者(以下、「仲卸」)ないし売買参加者(以下、「買出人」)以外へ(第三者)には販売できない。
具体的には、荷受は市場外に店舗を構える小売店(鮮魚店など)に自由に卸売することができない。
⑦商物一致の原則
荷受は、原則として市場内にある生鮮食品に限定して販売する(市場に入荷していない生鮮食品は販売できない)
⑧直荷引きの原則禁止
仲卸は卸売行為(荷受の行為)をできない。仲卸は市場外で生鮮食品を仕入れてはならない。
具体的には、仲卸は荷受以外から生鮮食品を仕入れることができない(メーカーや産地等からの直接仕入れが禁止されている)。
⑨自己買受の禁止
荷受は委託販売に限られ、自ら生鮮食品を購入することはできない。
この⑤~⑨の各項は、①~④の卸売市場の機能を担保・実現させるための規制・原則であったが「原則」であるがために、実態的には、幾つかの市場(とくに地方卸売市場)では、空文化していると言われている。
そこで、卸売市場の機能を高めようという農林水産省の「第10次卸売市場整備基本方針」(2016年)に基づき、2018年に卸売市場法が改正され、2020年6月21日に施行された。
(2)改正のポイント
農林水産省の「卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の概要」によれば、卸売市場法改正の背景として、以下の3点が掲げられている。
①食品流通の中で卸売市場が果たしてきた集荷・分荷、価格形成、代金決済等の調整機能は重要。今後も食品流通の核として堅持。
②農林漁業者の所得を向上させるとともに、消費者ニーズに的確に応えていくためには、卸売市場を含めて、新たな需要の開拓や付加価値の向上につながる食品流通構造を確立していくことが重要。
③このような観点から、卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境の確保を促進。
そして、改正のポイントは図表2の通りである。
*画像をClickすると拡大画像が見られます。
図表2だけでは、よく分からないので、改正内容について筆者なりにまとめてみた。
1)市場の開設に関する規制緩和(民間による中央卸売市場開設)
従来は、農林水産大臣が認可し、都道府県または人口20万人以上の都市に限定されていた中央卸売市場(開設者は地方自治体)について、農林水産大臣が認定すれば、民間業者でも中央卸売市場の開設可能になった。
民間業者が卸売市場に参入することで、卸売市場の活性化を図る目的であるが、施行から短期間のため実績はない。
2項の豊洲市場への移転・開場は、今次卸売市場法改正を織り込んだものである。
また、これまで農林水産大臣・開設者の許認可・承認が必要であった、卸売業者(荷受)・仲卸業者(仲卸)・売買参加者(買出人)についての法律上の規定がなくなったが、自由に参入できるかは市場ごとでの運営ルールになると思われる。
2)取引規制に関する規制緩和
表1の「取引規制等」の下半分を参照されたい。
①「第三者販売の原則禁止」の廃止
「第三者販売の原則禁止」の廃止により、荷受は市場内の仲卸や買出人以外にも販売が可能になった。
仲卸から仕入れることしかできなかった小規模販売店(青果店・鮮魚店)・飲食店が、荷受から仕入れることが可能になった。仲卸を介さない「中抜き」によって、より安価な生鮮食品仕入れの可能性が生まれた。
②「直荷引きの原則禁止」の廃止
「直荷引きの原則禁止」の廃止により、市場内の仲卸は全国各地の産地から直接仕入れることが可能となった。これにより小規模の仲卸でも、中央卸売市場に普段は入荷しないような特産の生鮮食品や、高級飲食店等が求める食材を小ロットで産地から仕入れる可能性が生まれた。
③「商物一致の原則」の廃止
「商物一致の原則」が廃止され、「商物分離」となることにより、仲卸は顧客であるスーパー・販売店・飲食店等に、産地から生鮮食品を直接調達することが可能となった。卸売市場での積替えが亡くなり、より効率的で高鮮度の生鮮食品輸送が可能になることが期待される。
第381号の「図表3 卸売市場を中心とした水産物の流通」をご覧頂ければ分かるが、水産物の流通では「産地卸売市場」から「消費地卸売市場」の2段階となっている。
前述の豊洲市場を例に挙げると、たとえば産地(八戸港で水揚げされたサンマ)は産地(知八戸の地方卸売市場)でセリにかけられ、豊洲市場に到着するのはその翌日となる。「商物一致」の原則が廃止されれば、もう1日早く東京の小売店に並ぶ可能性がある。
(筆者注:卸売市場法でいう「商物一致」「商物分離」は、物流・ロジスティクス分野でいう「商物一致」「商物分離」とは、やや概念を異にしている)
④「自己買受」
荷受が、卸売市場における独占的な立場を行使して価格操作を行うことや、価格が暴落した際の大きなダメージ(取引手数料)等で、市場取引の安定を損なうことを防ぐための措置として、荷受が自ら生鮮食品を購入することはできなかった(委託販売のみに限定)。
今次改正では、生鮮食品の安定的な確保のため、荷受による買受け(購入)が可能となった。
(3)法改正の実効性
農林水産省では卸売市場法改正のための調査報告書に、「卸売市場法改正により期待されるビジネスモデル」として、「輸出促進」「産地直送」「市場間ネットワーク」の3つを掲げている。そのうちの「産地直送」が図表3であり、「③商物分離」を示している。
*画像をClickすると拡大画像が見られます。
2020年6月21日の改正施行によって、①~④の各規制は原則廃止されるものの、「卸売市場の調整機能維持に十分配慮しつつ、卸売市場の活性化に資する視点に立ち、卸売市場ごとに、特定の事業者の優遇にならない」ように「市場毎に取引ルールとして定めることができる」とされている。さらに、「卸売業者、仲卸業者等の関係者の意見を聴くなど公正な手続を踏む(原文のまま)」こととされている。
何となく、関係者の既得権擁護のように読み取れるし、規制緩和による荷受・仲卸の対立は避けたいという行政当局の意向も感じられる。
しかし、卸売市場の取引シェアが3割を切って、新型コロナ禍で生鮮食品流通が大きく変化している今日、卸売市場の関係者もこのままで良いとは思っていないので、法施行後は、市場内の取引形態や、生鮮食品流通が変化していくと思う。
①~④の各規制を卸売市場ごとにどこまで緩和できるか、即ち、取引の自由度が卸売市場間の競争原理になることが想定される。①~④が緩和されて取引の自由度が高い卸売市場には「荷」が集まり易くなる。
既に、市場外流通との競争激化により市場経営が厳しくなり、市場存続のために規制が緩和されつつある地方卸売市場のなかには、さらなる規制緩和を推進する動きも出始めているようだ。
卸売市場の規制緩和については、後述する大手スーパーマーケットや大手EC業者の動きも着目されるところである。
今次、卸売市場の改正により、急激に変化する生鮮食品流通のなかで卸売市場が存続するために、市場それぞれの創意工夫を生かした改革は待ったなしと言えよう。
なお、卸売市場法の改正と同時に、食品流通構造の改善を目的とする「食品流通構造改善法」も改正・施行されたが、本稿では省略する。
(C)2021 Masayuki Hasegawa & Sakata Warehouse, Inc.