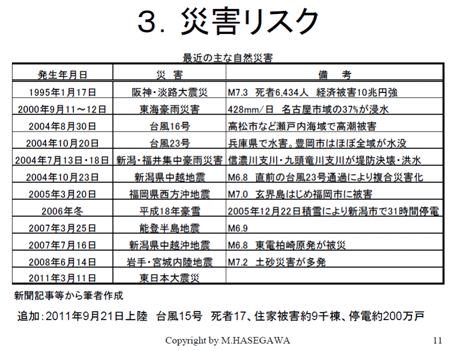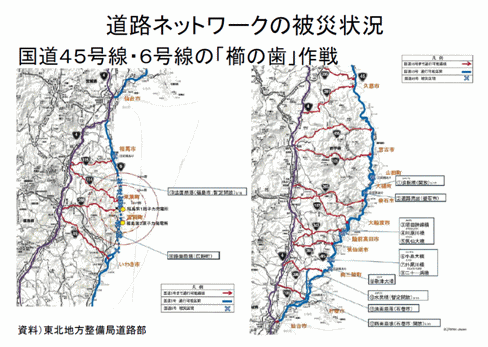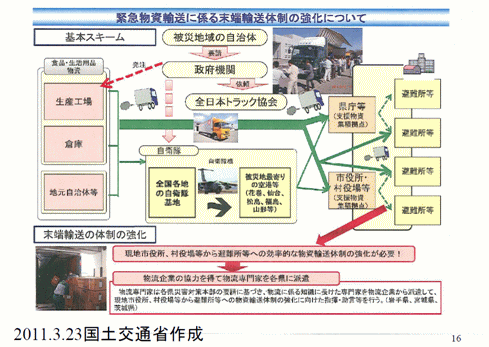第248号『ロジスティクスと危機管理』~BCP策定のポイント~(前編)(2012年7月17日発行)
| 執筆者 | 長谷川 雅行 (株式会社日通総合研究所 経済研究部 顧問) |
|---|
執筆者略歴 ▼
*サカタグループ2011年11月16日「第18回ワークショップ/セミナー」の講演内容をもとに編集しご案内しています。
*今回は3回に分けて掲載いたします。
目次
只今ご紹介にあずかりました日通総研の長谷川です。本日のワークショップ/セミナー主催者であるサカタウエアハウスさんの田中社長とは以前から親しくさせていただいており、6月にサカタさんのロジスティクス・レビューに寄稿した事(物流業から見た「災害とロジスティクス」 https://www.sakata.co.jp/jp/logistics-222/をきっかけに今回こちらでお話することとなりました。
今日お話したいことは、今司会の方からご紹介いただいた、危機管理、リスクマネジメント、それからBCP、この辺について、私は中小企業診断士をやっている関係もあり、特に中小物流企業の方を対象にお話したいと思います。少し観点からずれることもあるかもしれませんが、ご参考にしていただければありがたいと思います。
1.危機管理とは
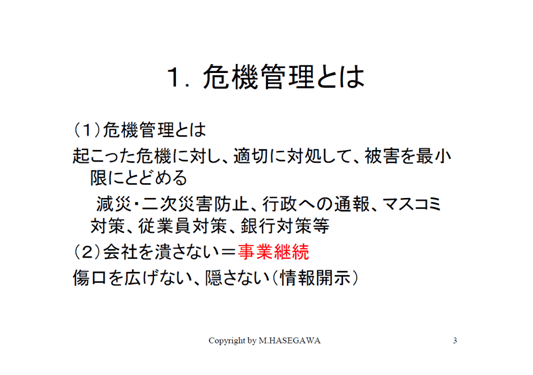
まず危機管理ですが、私なりに思っていることですが、これは既に起こってしまったことに対して被害をどのように最小限にとどめるかということです。今新聞で話題になっている製紙メーカーさん、精密機器メーカーさんがありますが、一つ大きな事が起こった時に、従業員に対してどのように説明するか、あるいは小さな会社であれば銀行対策をどのようにするかということですね。
そこで重要なことは「会社を倒産させない」ことであり、ここにもやはり事業継続、BCPが重要になるということです。
2.リスクマネジメントとは
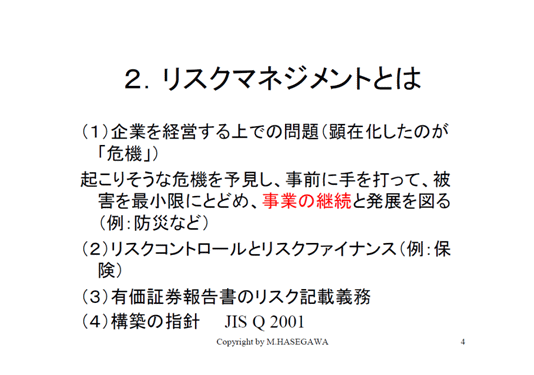
リスクマネジメントについて、これは今これからどんな事が、会社経営の中でリスクがあるかと言うことです。起こってしまったもの、顕在化してしまったものが危機となるのですが、そのことを予測して事前に手を打ち被害ができるだけ少なくなるようにすること、例えばこれからお話しする防災とはそういう事です。ここで重要な点は、事業の発展継続だとかそれに関連する事も入ってくるということです。
これについては今日上場企業の方も参加されていますが、今は有価証券報告書等のオプションの中に、リスクを記載する事も義務化されており、それぞれ大きな会社の株式を持っているとうちの会社はこんなリスクがありますと報告書などに書かれているわけです。
ではリスクについて、そのリスクを今後どのように対応するかということで、まず一つはリスクコントロール、これはリスクをいかに減らしていくかという事です。
もう一つはリスクファイナンス、リスクが顕在化して起こってしまっていないか、起こったときにそれをどうやって補償していくかという事で、例えば保険がそうですね。地震保険とかあるいは火災保険とかそういったものはあらかじめリスクを想定してそれに対して会社が大きな損害を受けないようにかけていると言う事です。
ただ保険というのは保険料と保険金を比較してどうするかということですね。新しい保険ができると、「入ってくれませんか、今回こういう保険作りましたので入ってくれませんか」という事で加入し結局保険金をもらうことになりますが、言ってみればその保険金も損害金の延払いみたいな形になっているんじゃないかと個人的には思っています。
リスクマネジメントについては、JISQ2001で規格化されています。これからお話しするBCPについても実は既にISO化していこうという動きが国際的にあります。多分、ISOの9000とか 14000、あるいはCSRのISO26000がありますが、やがてこのような形になっていくのではないかとは思っています。
(筆者注:BCPについては、ISO22301が2012年5月5日に発行した)
・リスクの例(日本SC協会)
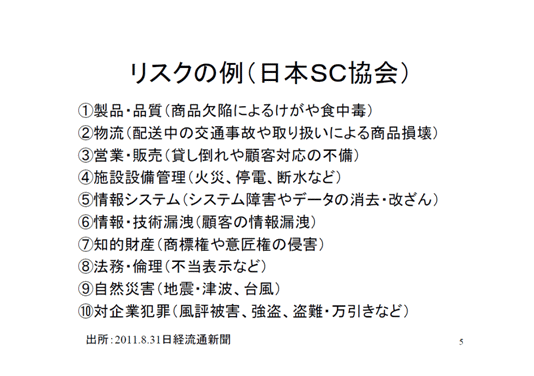
リスクの例としては、これは今年の8月31日の日経流通新聞に出ていたのですが、日本ショッピングセンター協会さんでは、「製品・品質から物流・営業・販売、施設設備管理に始まって、最後の対企業犯罪、風評被害まで、こういうリスクがショッピングセンター、もしくは量販店、小売業にはありますよ」という事です。
商品欠陥というのが例えば産地の偽とか、あるいは賞味期限切れとか当然そういうことも入ってきます。そこで、流通業の方も物流、特に配送中の事故だとか或いは取り扱い商品を破損するとか、そういったことについて、小売業ではリスクとして考えておられるということの認識が必要です。
ロジスティクスにおけるリスク10項目(平居義徳先生)
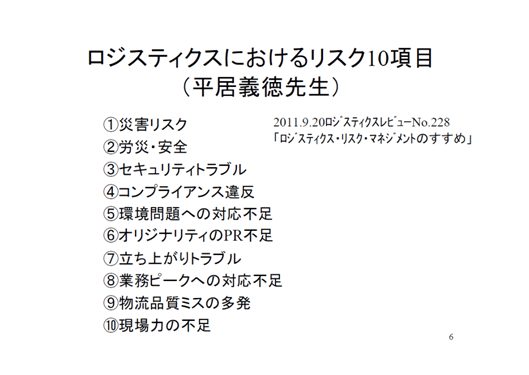
多分この①から⑩に向かって、リスクの大きさが一番大きいものから並べているのではないかと思っています。それから先程サカタウエアハウスさんの「ロジスティクス・レビュー」の話をしましたが、こちらは私が書いた3ヶ月程後に日本能率協会におられた平居先生、私も存じ上げていますが、この方が「ロジスティクスにおけるリスク10項目」について、ロジスティクス・レビュー(https://www.sakata.co.jp/jp/logistics-228/)の中で取り上げていました。
平居先生もやはり一番最初にあげられているのが、災害リスク、それから本日のワークショップの全体テーマでもある労災・安全です。
安全管理、それからセキュリティ、コンプライアンス違反があり、コンプライアンス違反というのは物流業でいうと、例えばトラックであればスピードオーバーあるいは過労運転ということも当然入ってきますね、それから今言われている環境問題です。
PR:コンプライアンスセミナー内容
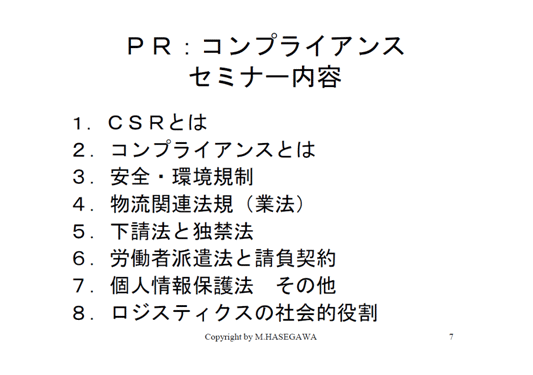
コンプライアンスの話がありましたのでここに加えていますが、私の方ではこのようなコンプライアンスに関するセミナーを実施しています。
先ほど安全の話がありましたので少しご紹介しますと、労働安全衛生法の問題だとかあるいは下請法とか派遣法ですね、私の方でこんな事もセミナーでやっています。これは宣伝です。
物流企業の「事業等のリスク」例
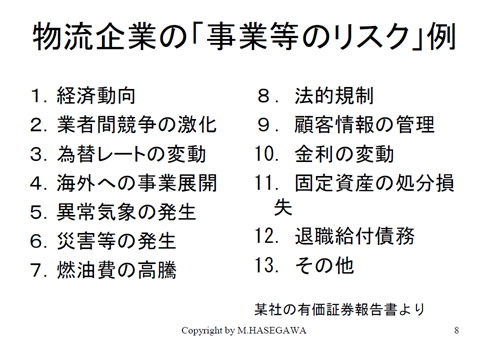
それでは、先ほどお話しました上場企業の物流企業における事業リスクにはどのようなものがあるのか、ある上場企業の有価証券のオプションを見るとこういう事が出ています。
経済動向、今後景気がどうなるのか、あるいは現在物流業者、トラック運送業者は全国に約65,000社ありますがそれが減ってくる国内貨物輸送に対して、更に海外輸出が減っていく中で競争がどんどん激しくなっています。それからこの会社は国際物流でやっていますのでそれが現在の超円高の状況ですが、今後為替レートがどうなるのかですね。
海外の事業展開では、東南アジア、タイでも洪水がおこっていますがこういったリスク、あるいはカントリーリスクの問題、それから異常気象ですね。ここでの異常気象とは、夏の急激な気温上昇や冬の低温により農村での農作物の収量減少やその後の大きな消費動向への影響を指します。
6番目に今日のテーマの災害ですね、それから7番目に物流業、トラック運送業あるいは海運業では大きく影響されるんですが燃油費の高騰の影響があります。8番目に法的規制、これは法的規制がこれから増えてくることにより影響があるということです。
つまり、ショッピングセンターを運営する小売業さんもそうですし、コンサルタントの平居先生も言われていましたが、物流企業においても災害等のリスクについてかなり強く意識することが必要ということです。
トラック運送業のリスクマップ例
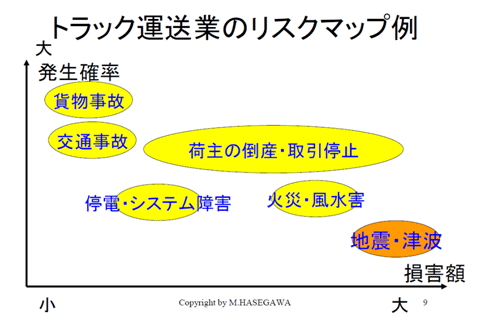
こちらは私が作成した資料ですが、トラック運送業、およびトラック運送業を利用している荷主企業さんにも関連するリスクマップです。縦軸がリスクの確率です。発生する確率が低いものは100年に一度、1000年に一度とかそう言うレベルですね。それで、横軸がそれによって発生する損害額、大きいか小さいかという比較です。
先ほどの流通業の物流リスクですが、残念ながら商品事故、貨物事故、これらがどちらかと言うと発生確率が高く、それから交通事故ですね、これも発生確率は比較的高いのですが、損害額は大から小まであり全体の金額としてはそれほど高いものではなく、保険がかかっているということです。
次に停電・システム障害、これはコンピュータが止まったとか電気がこないとかのリスクですね、物流業にとってみれば車と人と燃料があればなんとか配送できますので、それほど損害額は大きくないのです。今回のような地震、津波、この辺は発生確率が100年に一度とか言われていますが、いざ起こると非常に損害がが100年に一度とか言われていますが、いざ起こると非常に損害が大きくなります。
なぜこういったリスクマップを作成したかと言うと、BCPを作るときにこれをしっかり落とし込んで作った方が良いのです。BCPとは災害に対するBCPだけではなく、こういったリスク全体のことも踏まえて考えなくてはならないということで、リスクマップを作成しています。
3.災害リスク
こちらが災害リスクです。1995年の、もう16年も前の阪神・淡路大震災、私もこの時は日本通運の本社にいてどちらかというと後方支援部隊として取り組んでいました。その当時は日本通運本社は、秋葉原にありました。あの頃はそれほど携帯電話が現在のように普及していなくて、応援の車100台を出すにあたって、その運転手に携帯電話を持たせようとして、私たちは手分けして秋葉原の電気街を走り回って計100台の携帯電話を集めた記憶があります。
その後東海豪雨だとか、台風、あるいは新潟の集中豪雨、中越地震、西部沖地震、もちろんこれ以外にも色々な災害があります。たとえば2000年9月に岐阜県の南部で水害があったり、あるいは2004年10月には兵庫県西部で水害が発生しています。
2008年岩手宮城内陸地震の後に、2011年東日本大震災が発生し、大震災発生からもうすでに8ヶ月が経ちましたが、備考欄が未記入なのは行方不明の方が未だ約3600人おり、そのため空欄となっています。
今福島原発の話がありますが、実は2007年の中越地震の時も、柏崎原発が被災して完全復旧が終わっていない状況です。
この後追加したのは9月21日の台風15号、17号と、その前の12号、10号です。これにより停電約200万戸ということですが、台風自体はかつての伊勢湾台風と同じような規模です。防災が進んできてそれだけ台風による人的被害は減ってきたのですが、まだまだ家の損害とか停電とかそういったリスクは存在するということです。
4.東日本大震災とロジスティクス
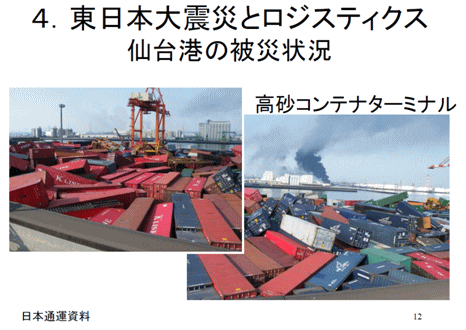
・仙台港の被災状況
少し話題を変更して、東日本大震災の被災状況はどうか、これが仙台港ですね。コンテナが積み木を崩したように崩れ、大体2000本くらいのコンテナが流出したと言われています。左側が流出の一部、仙台港のコンビナート、高砂のコンターミナル、右側をよく見ると後ろ側に煙が出ていますが、多分製油所が被災して燃えているのではないかと思います。
このときに、日本パレットレンタルさんから聞いたんですが、やはりレンタルパレットが何十万枚と流出し「本社から70~80人の応援を出して回収した」とおっしゃっていました。それでも、1万枚くらいは回収出来なかったそうです。
・仙台空港の被災状況
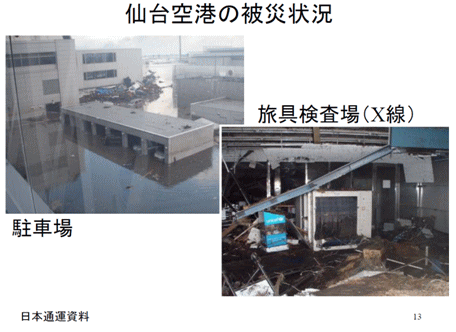
これが仙台空港です、この後水が引いて米軍の「トモダチ作戦」により機材を投入したおかげで、旅客機の運航までには少し時間がかかったんですが、救援物資の輸送には確か3日位で回復したと思いますが、そのときの様子です。駐車場はすっかり水に浸かっていて、右側が旅具の検査場です。皆さんが飛行機に乗るときにX線検査をうけるところ、チェックインのところですが、このように完全に水に浸かっています。
・道路ネットワークの被災状況
これが、海沿いの道路ネットワークです。国土交通省さんの資料ですが、丁度この円の真ん中が原発ですね。これが常磐線と国道6号線で一部不通のままです。こちらが内陸の4号線と三陸沿いの45号線です。
このあたりの被害が大きく、それに比べて東北道はそれほど被害が大きくなかったため、11日に地震がおきて翌12日から緊急車両だけは通れるようにしたということです。
それからこのような内陸から海岸に出る17本ある道路です。「櫛の歯作戦」ということで優先的に復旧工事を行ったのです。これにより、緊急支援物資あるいは量販店さんへの食料や日用品などの供給を出来るようにしたのです。
・緊急物資輸送の取組み
東日本大震災とその復旧の話で、今回日通総研からも、3月はまだ現地が大変だったので、4月になってから調査員を出して聞き取り調査を実施したのですが、地方自治体、被災三県、仙台市、あるいは各市町村を含めた自治体の方も被災してしおり、小さい市区町村の中には職員の3分の1くらいが被災者というところもありました。
緊急支援物資については、日本国中あちらこちらから届くものをストックして仕分けし被災地へ送るということが必要なのですが、そういう事にぜんぜん慣れていないので、最初はてんやわんやで市役所の脇の駐車場もすぐ満杯になってしまいました。
「餅は餅屋」ではありませんが、トラック会社だとか倉庫会社が拠点を貸して、そこで物流作業、在庫管理をし、荷受して商品を台帳につけてそれを各被災地からの救援要請に応じて、水が何本毛布が何枚出荷、そういったことをやっていくようになって初めてうまく緊急支援物資が流れるようになったのです。
ここに至るまでには、11日の震災が発生してから1週間くらいかかっていますが、これからようやくうまく回りだしたのです。もちろんそこには自衛隊や米軍の支援によるものもあります。そういったことをやりながら、復旧に努めてきたのです。

こちらが緊急支援物資の保管場の様子ですね。これは岩手県の例ですが、岩手県の場合は最初県庁や市役所を使おうとしたのですが、早々に岩手県トラック協会が請け負うことになりました。「県庁や市役所ではだめだ」ということで、トラック協会が提案して岩手産業文化センター・アピオという展示場を活用しました。
そこで実施していた住宅展示場を、もちろん地震がおきていますから開店休業状態なんですが、それを中止して東京ビッグサイトみたいなところに緊急支援物資を集めて仕分けして出荷したということです。

ここは良いことに普通の体育館と違って、10t車が直接施設の建物内に入ることができるのです。これが実際の状況です。よく見なければどこかの流通センターで荷受をしてそれを仕分けしていると思われますから、専用の物流施設とあまり変わらないですね。そういったことで岩手県では緊急支援物資の輸送が非常にうまくまわっているのです。
宮城県でも実はこれをやりたかったのですが、名取市の方にあった1箇所の施設は被災して流されてしまったり、もう一箇所の施設は別の用途に利用し使えなかったりということで、宮城県では民間業者の倉庫を借りて運用し、やりくりをしたのです。
(C)2012 Masayuki Hasegawa & Sakata Warehouse, Inc.