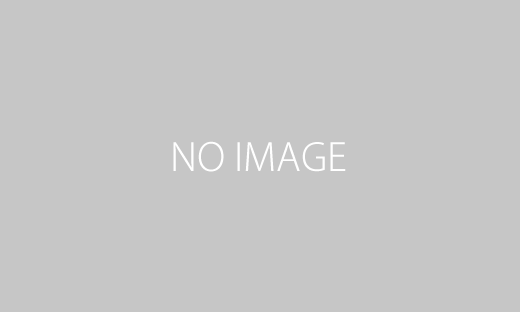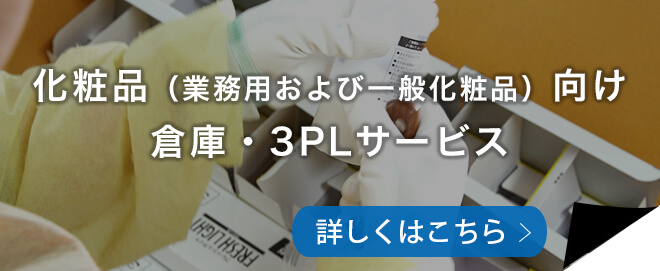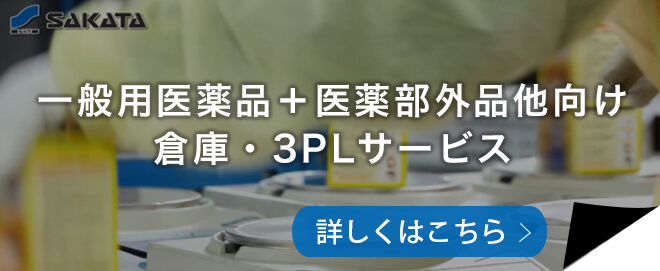第453号 働き方改革が進まないわけ(2021年2月4日発行)
| 執筆者 | 山田 健 (中小企業診断士 流通経済大学非常勤講師) |
|---|
執筆者略歴 ▼
目次
- I.リモートワークが進む?
- II.物流が止まる?
- III.アマゾンが出社前提のオフィス拡張
- IV.働き方改革が進まないわけ
- V.「自分だけ時短」はダメ
- VI.管理不在の管理
- VII.生活残業をどうする
- VIII.社会全体で負担を
I.リモートワークが進む?
落ち着いたりぶり返したりの新型コロナ感染拡大を避けるため、リモートワークがまた復活しつつある。仕事の生産性が上がるか否かといった議論は別にして、労働者の「働き心地」という点からはどうなのであろうか。
冒頭から私事で恐縮であるが、サラリーマンからフリーランスに転じた筆者などは、リモートワークが基本である。その経験からいえば、「慣れると快適」といったところであろうか。もちろん、家の間取りや家族構成など「家庭内環境」にもよるが、個人的には自宅勤務の生活には満足している。
それはさておき、報道では在宅勤務の普及によって多くの企業で出社の機会が減り、オフィス重要も一時的に減少しているという。こうした情報に接していると、「オフィス不要論」といった極端から極端に振れる風潮を感じる。
その割には筆者の周辺企業の動きは鈍い。電車も空いてることは空いているもののまだまだ混んでいる。たしかに、机上やパソコン上で仕事がほぼ完結する一部の知識集約型業界ではありうるだろうが、こうした産業だけで世の中が成り立っているわけではない。むしろそうではない業界、企業の方が圧倒的に多いのではないか。
II.物流が止まる?
その典型が物流業界である。一部の大手事業者の本社や管理部門で在宅勤務を行っているものの、大半の物流事業者で在宅勤務は「夢のまた夢」である。本社や管理部門などのホワイトカラーは元より在宅勤務のハードルは高くない。問題の根はやはり現場にある。
夏真っ盛りの先日、中堅運送会社の営業所で配車担当者が新型コロナに感染した。無症状であるが、14日間の自宅待機を課せられる。その営業所では大手消費財メーカーの問屋向け配送を中心とした配車を行っている。一日に運行させているのは自社車両、傭車含めて100台以上におよぶ。本人の自宅待機はまだしも、他の従業員まで感染が広がり出社できなくなってしまったら、配車業務がストップし商品の配送が完全に止まってしまう。関係者は凍り付いた。会社は在宅勤務に対応するため急遽、社員全員のノートパソコンを準備する手はずまで整えたという。
幸い、社員は濃厚接触者とはならず感染者もなかったため、配車・配送停止という最悪の事態はギリギリのところで回避することができたが、新型コロナが配送の要である配車機能を通じて物流を麻痺させてしまうことを改めて認識させる出来事であった。
配信される業界ニュースをみても、物流会社の社員が新型コロナに感染したという記事を目にしない日はない。それでいて、当該営業所が閉鎖されたという事実はほとんどなく、濃厚接触者の調査と消毒で「通常営業」を維持しているケースがほとんどである。保健所の指導によるものだろうが、「止められない」物流の事情が垣間見えるようである。
では、配車をはじめとした物流業務でリモートワークは不可能なのか。結論からいえば不可能ではない。ただし、すべての荷主、協力会社との紙による情報のやり取りが完全にデジタル化し、すべての業務手順が標準化・マニュアルされ、追加オーダー、発注ミス、緊急対応など荷主との一切のイレギュラー処理がなくなり、商品の検品・出荷ミス、破損、配送遅延、交通事故など一切の現場のトラブルもゼロとなる、さらに社内の報告や経理・各種の事務処理などがIT化されている、といった条件がほぼ満たされれば、である。これでも現場事務関係の在宅勤務が実現するレベルであり、さらに倉庫内、配送などの作業は完全無人化とならない限り難しい。
物流スタートアップ企業などの出現が目覚ましいところであるが、残念ながらこれらが実現するのがいつになるのか予想すらできない。もっと夢のある話をしたいのはやまやまであるのだが。
III.アマゾンが出社前提のオフィス拡張
日経新聞(2020年8月29日)によると、米アマゾン・ドット・コムがニューヨークなど米6都市で、技術者やクラウドインフラの設計者、データサイエンティスト、UX(ユーザー体験)などの高度人材計3,500人を追加採用するという。さらに新型コロナウイルスの収束後を見すえ、出社を前提としたオフィス拡張などに約1,500億円を投じる。ニューヨークでは、5番街にある老舗百貨店ロード・アンド・テイラー跡地の建物を取得、約5万8千平方メートルのオフィスに衣替えをする。
社員に無制限の自宅勤務を認めるIT企業が多い中、アマゾンの対応に奇異な印象を持たれる読者も少なくないだろう。ましてGAFAの一角として挙げられる同社が在宅勤務に逆行するとは。
この答えは同社がIT企業である以上に「物流企業」だからに他ならない。記事によれば、アマゾンは自宅で働ける従業員に対しては2021年明けまで在宅勤務を認めている。ただ、物流施設や小売店では新型コロナの感染拡大局面でも多くの人が施設で勤務を続けた。ホワイトカラーだけが在宅で働き続けることには社内から反発もあるとされ、いずれは多くの従業員を通常の勤務に戻す考えとしている。
この記事からは、先に挙げた物流現場の「止められない事情」に加えて、現場とホワイトカラーの課題が見えてくる。ホワイトカラーが現場に気を遣うなどというのは、ジョブ型雇用である欧米企業にしてはきわめて日本的と言わざるを得ないが、これが物流をはじめとした現場を抱えている企業の実情であろう。
実際、日本の物流事業者の本社や管理部門では、在宅勤務をやろうと思えばできるけど現場の手前行っていないという例も少なくない。アマゾンの記事に接して、その対応に改めて納得がいく。
IV.働き方改革が進まないわけ
新型コロナのインパクトがあまりに強すぎるため、前置きが長くなってしまったが、本題と関係がないわけではない。
今回のテーマは「働き方改革」である。産業界で取り組みが進む働き方改革であるが、中でも物流業界の一番悩ましいのは労働時間上限規制である。ご承知の通り、大企業では2019年4月より、中小企業では2020年4月より時間外労働時間は最大単月100時間以内、年間で720時間以内に規制される。違反企業には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則も課せられる。罰則が加わったことで、企業にはいやおうなく対応が求められる。
ちなみに本題からはややそれるが、この規制は医師、建設、自動車運転業務(つまりバスやトラックのドライバー)には5年間の猶予が認められ、さらに自動車運転業務は猶予期間後も960時間の規制にとどまる。
この「規制緩和」について読者はどう感じるだろうか。バスやトラックのドライバーは5年間時間外の上限規制がないだけでなく、5年後からは960時間という「産業界最長」の長時間労働が「保証」されるのである。この規制を見て、この業界で働きたい、ドライバーになりたい、と思う若者が果たしてどれだけいるだろうか。経営上の都合もあるのだろうが、筆者には官民共同で「この業界には来てくれるな」といいうメッセージを発しているとしか思えない。
本題に戻そう。今回はドライバーではなく、物流会社、中でもトラック運送会社の事務系社員などドライバー以外の職種を対象に考えていきたい。つまり、他の作業と同じく年720時間規制の働き方改革である。
大企業はまだしも、今年の4月から適用されているこの時間外規制への対応に苦慮している中小の運送会社が少なくない。先の罰則はおそらく現場の管理者に課せられるはずであるから、彼ら彼女らにとってもこれまでのような(?)他人ごとではない。
筆者は先日、関係するある中堅運送会社の経営者、管理者での会議で対応を協議した。ここでは筆者自身の経験とその会議で検討した課題を改めて整理し、今後の方向性を考えてみたい。
V.「自分だけ時短」はダメ

物流会社の働き方改革を論じる際、どうしても「荷主が悪い」という論調になってしまいがちである。物流業界出身の筆者のスタンスもどうしてもそちらに偏りがちになるため、その点は厳しく中立を保ちたいとは思う。
ただそれを踏まえながらも、どうしても最初に述べておかなければならないのは「荷主の姿勢」の問題である。
たとえば、最近ではすっかり影が薄くなってしまった「プレミアム・フライデー」。当時、大手企業を中心に金曜日の時短勤務が進んだ。これはこれでとてもいいことだと思う。どんどん進めるべきだと思うのだがなぜトーンダウンしてしまったのだろうか。
問題なのは自分たちだけプレミアム・フライデーを実践し、その分の業務を外注先や物流会社にしわ寄せしてしまうことである。実際、ある大手荷主では金曜日の受注業務はこれまで通り15時まで受付としつつ、時短で午前中勤務のみ、以降の外注先と物流会社の業務は変わらず、という「自分たちだけ時短」を行った。また消費財を中心に現在でも一般的に行われている、自分たちは完全週休二日制の一方、土曜、祝日出荷を継続しているケースがある。
もちろんこれらはそれだけでは問題ない。世の中には人の休んでいる時に働いている仕事はいくらでもある。電車だってバスだってそうだし、スーパーだってコンビニだってそうである。こうした業態は基本的に24時間365日営業するための勤務シフトとそれを支える売上収入を確保している。
物流業界がそうした勤務体系を組み、そしてそれを維持するだけの適正な収入が確保できていればいいのであるが、現実はそうではないところに問題がある。現在「人が休んでいる時に稼働できる」体制と売り上げが確保できているのは、もともと年中無休を前提とした大手の宅配事業者くらいである。
それ以外の運送会社は、休日出勤と時間外労働で荷主の「時間外・休日配送」を支えており、シフト勤務を維持するための人員増を賄えるだけの運賃収入もままならない。人手不足の代表業界にあっては人の確保も厳しい。必然的に働き方改革のハードルはとてつもなく高くなる。
「自分たちの時短」を行うためには、こうした配送パートナーの時短を実現するための出荷・配送時間、日程の見直しを行うか、さもなくば時間外・休日配送に見合った運賃を負担するか、の2つを考えるしかない。
誰かの犠牲の上に成り立つ働き方改革が本当に労働者のための改革とは到底思えない。アマゾンの例のように現場へのそれなりの配慮が必要になるはずである。
VI.管理不在の管理
運送会社側の課題も少なくない。先の会議で明確になったのは現場の「管理不在」である。管理職に時間外規制の説明を行い、対策を尋ねたところ、意外な答えが返ってきた。多くの管理者がいとも簡単に「できる」と口にするのである。できない理由を延々と聞かされることを覚悟していた筆者にとって、これは予想外の展開であった。
理由は単純化すればこうである。これまで時間外勤務についてはとくに管理者から指示することもなく、社員各自の判断にまかされていた。それを管理者が日々明確に指示(要するに「早く帰れ」と指示すること)すれば時間外は減らせるというのである。あまりにも単純な理由なのでにわかに信じられないかもしれないが、物流の現場では大いにありそうな話ではある。
そもそも、職務分担があいまいなため、担当者の行っている仕事の中身は各自の判断にゆだねられ、管理者や他の社員からは完全にブラック・ボックス化する。仕事の内容がわからないので、管理者が明確な指示を出せるわけもない。言い方は悪いが、各自が好き勝手に仕事をし、好きな時間に帰っているわけである。時間外が減るはずがない。
この場合、管理者たちは簡単に「できる」と口にしたが、実際に帰宅を指示するのはそれほど容易なことではない。「帰りなさい」と指示しても「これこれこういう仕事があるので帰れない」と反論されてしまえばおしまいである。その仕事が明日に回してもよいものか、あるいは別なやり方でやれば時短になるのか、など仕事の内容を把握していない限り判断できないからである。
働き方改革の第一は、現場管理者の意識改革にかかっている。
VII.生活残業をどうする
前項と密接に関連するのだが、時間外労働の多くが「生活残業」という実態がある。生活残業であるから社員の自主性に任せておけば、際限なく増えるのは当たり前である。本連載でもこれまで何度も指摘してきた課題である。
管理者が業務内容を把握し、効率化を一緒に考えて時短を進めようにも、本人にその気がないのでは始まらない。実際、業務の効率化にもっとも抵抗するのは担当者本人であったりする。
この問題は根が深いが、基本の給料と賞与では生活できないという深いところでこれまで述べてきた課題とつながっている。時間外を減らせと指示したところで、「では生活できる給料に上げてくれ」と反論され、「それはできない」となって議論は堂々めぐりの泥沼にはまってしまう。
VIII.社会全体で負担を
結局、物流、中でも運送会社の働き方改革を進める原資は運賃に帰結する。運賃収入を確保するには車両の積載効率を高める、実車率上げる、車両の稼働率を上げるといった策があるが、これには限界があるし、それほど大きな効果は期待できない。貨物の流動には地域的な偏りがあるので、たとえネットのマッチングを行ったとしてもトラックの荷台を完全に満たすことも難しい。
おりしも本年4月に国土交通省からトラックの「標準運賃」が告示された。自由化され届け出制となっていたトラック運賃について国が標準を示すという異例の対応である。
これは持続可能な物流の実現に向けて、取引の適正化・労働条件の改善を図るために国がやむにやまれず口を出したものと考えてよいだろう。実際の原価計算にもとづいたこの標準運賃を、現在の実勢運賃に近い1990年頃の標準運賃と比較してみると、小型・中型車(2~4トン車)クラスの距離制で3割から5割、大型車(10トン車)クラスで1割~3割の乖離がある。
自動運転、無人化などの研究に資金を投入するのもいいが、楽観的に見ても実用化はだいぶ先になろう。まずは適正な運賃の収受と働き方改革によって、運送会社の人員を確保、拡充するのが先決である。
繰り返すがその原資は運賃収入しかない。そしてその原資を賄うのは荷主だけではなく、われわれ消費者、社会全体での負担であることを忘れてはならない。
以上
(C)2021 Takeshi Yamada & Sakata Warehouse, Inc.