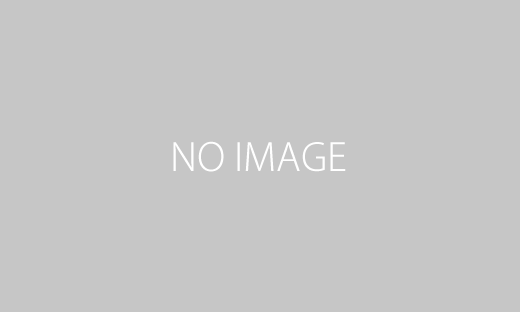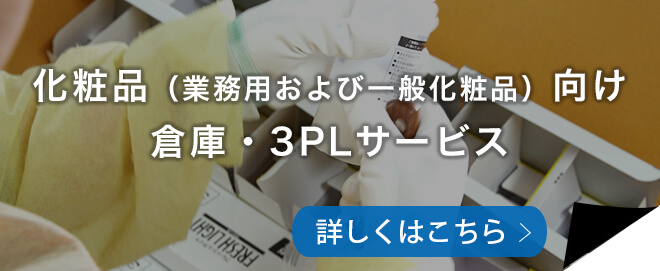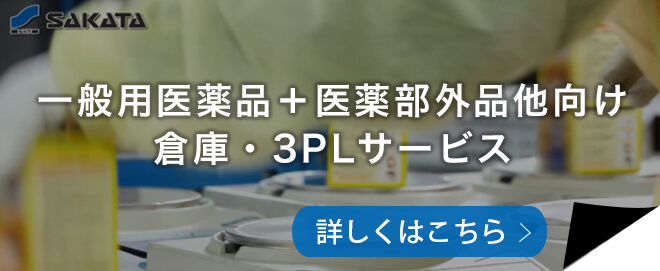第40号顧客起点小売業の条件と可能性―小売マネジメントの視点から―(2003年09月22日発行)
| 執筆者 | 三村 優美子 青山学院大学 経営学部教授 |
|---|
目次
1.日本の小売業の危機と転換
先日発表された2003年の商業統計(速報)は、小売業の構造変化の激しさを十分に示すものとなった。小売商店数は約130万店となり、この3年間で7.6%の減少、また、消費不振やデフレ現象を受けて年間販売額も6.1%減少している。日本の多くの商店街は一部の地域を除き空き店舗に蝕まれており、空洞化という深刻な状態を呈している。零細な中小小売業の閉店はもとより、経営不振に陥った大型小売業(百貨店や総合スーパー)の経営破たんも目立つ。大店法の規制緩和(2000年に廃止)が大型小売業の過剰出店競争を刺激した帰結ともいえるが、明らかに日本の小売業は規模の大小(企業や売場面積規模)を問わず深い混迷の中にある。
ただし、業態別の動きを追っていくと小売業の構造変化の方向は比較的分かりやすい。それは、小売業態は、環境変化に適合するための価値提供の仕組みだからである。小売業態は、一般的に対象市場に合わせて構築された小売マーケティング・ミックスとして理解されてきた。ただし、メーカーの新製品開発とは異なり、小売業者の創意工夫や改善・修正を経て、競争優位性を持った”標準形”(品揃え、売場面積規模、販売方法、営業時間、価格水準などの共通特性の組み合わせ)として確立されたとき業態として認識される。もちろん、標準形といっても小売業者ごとに多様な形態が展開されうるし、また環境変化に合わせて変容していくという流動的な面も大きい。また、アメリカのスーパーマーケットのように、市場変化に合わせて業態が分裂(大型化、複合化、高級化、ディスカウント化など)し、さらに、競争優位の業態に収斂していくといった分裂と収斂のダイナミックな変容過程として捉えることも可能である。
業態別の構造変化は、一般的に、成長業態、成熟業態、衰退業態の勢力交替サイクルとして捉えられてきた(*1)。 現在、成長業態と目されるのはコンビニエンスストアやドラッグストアであるが、これらにも明らかに変調が生じている。コンビニエンスストアの商店数は、商業統計(速報)によれば、3年間で5.6%の増加となっているが、既に市場は飽和化し、激しい競争の中で格差拡大と再編・統合の段階にある。酒や医薬品の販売規制緩和を受けて販売増加の可能性はあるとしても、これら市場分野における異業態との競争は熾烈である。とくに、近年成長が著しいドラッグストア市場は2010年に10兆円の規模まで拡大すると予想されており、コンビニエンスストアの最大の競争相手となっている。しかし、ドラッグストアにもオーバーストアの兆候が現れており、価格競争による収益悪化や再編・統合の動きが進行中である。
小売業態は、その革新性や差別性の高さで競争優位性を獲得し、成長と成熟過程を経て次の革新的な業態に地位を譲り消えていくと考えられてきた。既存業態のほとんどが成熟(あるいは衰退)段階に達していることから、そろそろ次の有望業態の登場が待たれるところである。20世紀におけるアメリカの小売業の発展過程を説明する”小売の輪の仮説”に従い、次の小売革新としてEコマースに期待する向きもあるが、これが小売構造を根底から変えうるか否かはまだ明らかでない(*2)。
ただし、”小売の輪の仮説”が提示するような循環論的モデルでは小売業の構造変化を説明できないという見方がある。小売革新がコストと利益構造の異なる新しい小売業態を登場させるだけでなく、むしろそれに加えてどのような小売サービス水準を実現するか(つまりどのような価値を提供するか)という点が合わせて問われるべきだからである。それは、消費社会の変化により、小売業のあり方に根本的な変化が生じているためである。消費者の抱える問題や悩み解決など小売サービスの提供が求められる時代には、低コスト・低価格が即消費者利益に結びつくわけでない。供給者コストと消費者コスト(時間コスト、身体的苦痛、商品選択の制限など)は本質的にトレード・オフ関係にあるからである。
しかし、小売革新はコスト・価格軸を中心として語られ、小売サービス水準軸で語られることはほとんどなかった。消費社会が貧しくかつダイナミックな経済発展の時代には説得力を持った”小売の輪の仮説”も、小売業の多様なあり方が求められる時代には、過度に供給発想に偏った考え方となる。小売業の変化の方向性が見えにくいのは、”低コスト・低価格の実現こそ小売革新”という通念が強すぎるためといってよい。
いま必要なことは、このような小売業の多様なあり方を捉える新しい思考枠組みである。 従来、小売業の多様性は、低コスト・低マージン型(低付加価値・低サービス水準)と高コスト・高マージン型(高付加価値・高サービス水準)を二極とする軸上の分布として捉えられてきた。そして、小売の輪の仮説は、業態成熟化に伴う前者から後者への移行過程を捉えたのである。しかし、前者と後者は、全く異質な小売マネジメントを基本としており、前者から後者への移行は容易でない。多くの場合、この移行過程が本質的に競争力弱体化の道となったのは、トレード・アップにはその経営体質の転換が求められるためである。この小売マネジメントの違いを前提にするならば、供給起点型小売業と顧客起点型小売業との違いもみえてくる。
小売業の多様なあり方とは、業態(小売形態)の多様性ではなく、それを形づくる小売マネジメントの多様性によるものである。
2.小売業のあり方を変える規定要因
小売業のあり方を大きく変えたのは次のような要因である。
第一に、1980年代以降のパワーリテイラーと呼ばれる巨大小売業の登場と小売競争行動の変化である。
なぜ、パワーリテイラーが登場し小売寡占が急激に進行したのかについては、規模や範囲そして速度の経済によるとは説明されるものの、社会経済的な背景も含めてその成立メカニズムについてまだ十分に解析されていない。しかし、ここでは、大型小売業間の激しい競争の中で、競争の次元が売場単位から特定カテゴリー(棚)単位へと細分化が進んでいることに注目しておきたい。トイレタリー商品、菓子、缶飲料、酒やビールなどで展開されている小売競争は、業態間や業態内競争というよりも各店の売り場や棚次元の競争である。さらに、同一業態内での企業間格差が開いていることも大きい。これは、業態が、標準形として共有されるというより、特定企業の戦略行動の特性を強めているためである。業態のあり方が小売業の競争行動を反映することから当然の帰結といえる。今日では、ウォルマートのスーパーセンターのように、開発企業の”一人勝ち”を生じさせた業態もある。パワーリテイラーの台頭は業態の溶解の過程とみることもできる。
第二に、情報化の進展とサプライチェーン・マネジメントの高度化に伴い、生産から消費段階まで取引連鎖を通した全体的な供給過程として統制する傾向が強まったことである。
この目的は、最終販売と物流(在庫・配送)活動を同期化させることで在庫削減と欠品による機会損失を防ぐところにあるが、それが一種の需要管理的な動きに結びつく可能性があることは否定できない。
それは、消費財のように需要の不確実性と変動性の高い分野において物流と販売活動の同期化を図る場合には、変動性の高い品目の排除など取扱い品目の制約を通した管理的な工夫により需要の透明性(数値的予測性)を高める必要があるからである。もちろん、見込み仕入れ・販売のもとで発生した需給不一致(在庫過剰)を見切り販売で解消したり、取引条件に市場危険負担を折り込む(返品条件など)ことで対応することの無駄の大きさからすれば、消費者反応を予測可能な範囲にとどめるため実販売の場をある程度管理・統制することは是認される。投機(仮需)原理から同期化(実需)原理への転換は、効率性の観点からは必然的な方向といえるからである。
ただし、これが過度に進められたとき、小売店頭が硬く同質的な場に変質する可能性があることは無視できない。それは、需要管理が本質的には消費者選択の制約であり、潜在的な可能性を秘めているが需要の不透明な商品を排除していくからである。長期的にみるならば、消費者とのゆたかな出会いを求める小売機能の弱体化に繋がる。
もちろん、このことは、サプライチェーン・マネジメントの必要性を否定しているわけではない。問題は、サプライチェーン・マネジメントの高度化が、小売業の役割は何かという本質的な問いかけを提示したということである。
1980年代以降、”効率性の高さ”が小売業の競争力を規定しその明暗を分けたこともあり、小売業の経営が効率追求に過度に偏ったことは否定できない。つまり、長期的な顧客価値実現を目指す”効果”と小売業の基礎体力の強さを目指す”効率”の均衡が崩れ、後者に優れた小売業が目立つようになったのである(*3)。 しかし、効率的で財務的価値の高い小売業が消費者にとって魅力的な小売業であるとは限らない(*4)。 むしろ、小売業の寡占や巨大化が進むことで、効率的ではあるが硬く冷たい店頭に対する消費者の不満は募り、比喩的ながら”消費者の反乱”さえ予想させている。そして、”効率の論理”(低コストと利益志向)を標榜する小売業が圧倒的な競争力を発揮しているようにみえる一方で、消費者の潜在的な不満を受けた”効果の論理”(顧客志向)に立脚する新しい小売勢力台頭の兆しがある。それは、小売業の底流変化であり、効率追求の極に振れすぎた小売業が、効果と効率の均衡を回復させようとしているといえる。
第三に、サービス化を背景として物販中心の小売業のあり方に限界が見えてきたことである。ただし、これには、モノが売れないための小売業の売上げ不振という表面的な次元を超えて、小売業の多様なあり方という視点からの検討が求められる。
効果と効率の均衡回復過程は、”消費者にやさしい小売業”へという原点回帰と捉えられるかもしれない。しかし、それは単純な原点回帰ではない。従来の商品(モノ)販売の場としての小売業とは別に、商品販売と情報そしてサービス提供を複合させた小売業が成長する可能性があるからである。小売業の変化は、振り子の水平運動ではなく、スパイラルな上昇移動といえる。
1980年代以降、日本の消費構造は顕著な変化を示してきた。それは、モノを中心とした消費の伸び悩みとサービス消費の伸張である。総務省家計調査(全国・全世帯)によれば、消費支出全体に占めるサービス支出の割合は、1980年の32.7%から2001年の41.0%まで大きく上昇している。1980年代には消費の個性化や多様化が注目され、多品種(少量)化の流れへの対応の必要性が指摘されたが、それはあくまで”モノ消費”の枠にとどまるものであった。消費のサービス化(無形化)は、物財の供給と販売を前提として構築されている小売業のあり方を大きく揺るがすことになる。なぜならば、無形要素の大きい商品(経験財や信頼財)の価値は消費者の使用過程を通して実現するものであり、使用過程を通したクオリティ管理が不可欠なためである(*5)。 つまり、売った時点で活動が終結する従来の販売機能を主とする小売業では対応できない。
ここでも、小売業とは何かという本質的な問いかけが提示される。
小売業は、生産と消費の間に存在する懸隔を架橋し、生産から消費段階に至る価値転換過程の一翼を担っている。生産にばらつきがあり商品の品質格差が大きいほど、あるいは生産と消費との異質性が高いほど、商品を消費者に適合させる小売業の役割は重要といえる。しかし、標準的商品の大量生産体制の確立は、この小売業の役割を大きく後退させた。つまり、規格化・標準化されたマスプロ商品をマス広告と販売促進を通して消費者に提供していくマーケティングの仕組みに組み込まれた小売業は、販売と物流機能(在庫保有)に特化する形で成長してきたといえる。そこで求められるのは量的な需給調整である。
たとえば、酒販店の凋落は、確かに直接的には酒販店免許緩和によるものであるが、缶ビールやアルコール飲料などマスプロ商品を中心とした品揃えを続ける限り、個別の小売業の独自性は生まれず、品揃え量や立地以外に差別化は困難である。店頭販売が自販機に容易に置きかえられる状況のもとでは、規模の力を背景とした価格競争に陥るのはやむを得ない。1990年代前半に吹き荒れた価格破壊の嵐も、ディスカウント小売勢力の台頭という面以上に、マスプロ商品の取扱いに終始する小売業の限界を示したという意味で深刻である。
マスプロ商品においては、小売業を含む流通段階では、適時・適量・適品以上の付加価値はほとんど生まれず、小売業の収益はいかに低コストを実現できるかにかかっている。
一方、顧客に合わせた修正や調整が必要で、使用過程まで含めたクオリティ管理が重要な商品においては、質的な需給調整が必要になる。つまり、小売業がそれぞれの顧客に合わせた独自能力を発揮することが求められるのであり、問題解決あるいは価値創造という言葉が現実的な重みを増す。
消費社会の高度化はサービス要素の大きい商品分野を成長させているが、ここでは、従来のモノ販売中心の小売マネジメントでは対応できず新しい小売マネジメントが必要となる。近年の小売業の不振は、モノ中心市場の成長鈍化(収縮)とサービス要素の大きい市場の成長という消費市場の構造変化に不適応を生じさせたことによるものである。
3.顧客起点小売業の条件―関係性マーケティングからの示唆
新しい商品分野に対応するにはどのような小売マネジメントが必要なのであろうか。このことを考察するときには、関係性マーケティングの枠組みとその成立過程が参考になる。
20世紀初頭、もともと標準的マスプロ商品の市場開拓と統制手段として成立したマーケティング技法は、当然のことながら、サービス要素や情報要素の大きい商品分野に必ずしもうまく適合するものではなかった。特に、1980年代において規制緩和とサービス経済化が進行し、フードサービス、金融・保険、ホテル・旅行、通信・運輸など純粋なサービス・ビジネス分野でマーケティング技法が応用されるようになったとき、比較的早い段階で、モノ(物的要素)を中心としたマーケティングの限界が見えてきたといえる。そして、そのことがマーケティングの重要な転機となったのである。
周知の通り、サービス・マーケティングでは、商品とサービスの特性の違いを出発点としている。つまり、無形性、変動性、一体性(非分離性)、消滅性という特性をもつサービスでは、在庫保有を通した需給調整が困難であり、かつ品質のばらつきが大きいという問題がある。そこで、サービス・マーケティングでは、顧客担当者と顧客との相互作用と信頼関係、顧客担当者の問題解決能力を助ける組織設計と能力開発、サービス提供プロセス管理、顧客満足を含むクオリティ評価測定、広告・販売促進を含む多次元のコミュニケーション活動など独特の工夫を持ち込むことになった。その中心概念は、顧客関係、信頼と共有、トータル・クオリティである。そして、このサービス・マーケティングに逆に刺激される形で商品中心のマーケティングの枠組みが変容したのである。関係性マーケティングの登場である。
関係性マーケティングとは、顧客との長期信頼関係と顧客とともに問題解決(あるいは価値共創)を強調するマーケティングの思考枠組みである(*6)。 なぜ、顧客関係が組織にとって重要かは、一部優良顧客が収益のかなりの部分を生み出している(7:3の原則など)という実利的理由だけでなく、顧客の情報提供や発信力が大きな影響力を発揮するためである。高関与で不安(知覚リスク)の大きい商品では、満足した顧客が発する口コミや評判が別の消費者の商品選択を左右している。さらに、これに加えて、組織の理解者・協力者としての役割の大きさは無視できない。顧客自ら価値創造の担い手であり、顧客が商品・サービスの生産と流通過程に参加することで、商品・サービスのクオリティ水準を維持し高めていくのである。
たとえば、この典型的な例は医療サービスにみることができる。
医療サービスの目的は患者の治療と健康回復である。しかし、たとえ優れた治療や投薬が行われたとしても、医療サービス提供者と患者の間に信頼関係がなければよい成果が得られるとは限らない。治療の成功は患者の自然治癒力に規定されるからである。このことは、生活習慣病など慢性疾患の場合特に顕著である。そのため、患者の症状に合わせた薬剤処方とともに、患者の病気への理解を深めさせ食事や生活指導などの情報提供や教育・支援活動が重要な意味を持つ。言葉を換えるならば、患者(顧客)の問題解決能力を高め支援する体制づくりが必要ということである。そして、患者をコアとして、病院、診療所、調剤薬局などの医療機関、あるいは医師、看護師、薬剤師、栄養師などの分業と連携が求められている。
このような顧客の問題解決あるいは顧客価値実現を目指した水平的機能連携の仕組みは、21世紀に相応しい新しいマネジメント・モデルといえる。NormannとRamirezは、これをValue Constellation(価値の星座)と呼称し、そのなかで患者支援サービスを主軸とした調剤薬局ネットワークの事例(デンマーク)などを紹介している(*7)。 顧客を囲み円環状に作られたネットワーク組織というその形態から、ここでは価値連環システムと呼ぶことにしたい。顧客起点小売業は、孤立して存在するのでなく、価値連環システムの一環として顧客接点を担う存在と考えるべきである。
医療サービスはある意味で極端な事例であるが、医療サービスを比喩として考察すると、顧客起点小売業の条件にいくつかの示唆を得ることができる。
①顧客ニーズに焦点を合わせた売場編成
顧客起点小売業の条件は、その顧客接点(真実の瞬間)が生きたものであることである。これには、”顧客ニーズ”を基軸として、商品、品揃え、販売方法、サービス、情報提供など売場のあり方が定義されていなければならない。たとえば、ウォルマートとの激しい価格競争により経営不振に落ち込み再建を進めるトイザラスの事例が参考になる。トイザラスは”玩具のスーパーマーケット(量販)”路線から、ディズニーのような子供達の夢を感じさせる売場に、さらに乳幼児を抱えた若い親達の支援と情報提供を主軸とした売場作りへという路線転換を試みている。特に、仕事を持ちかつ孤立しがちな若い母親達の悩みに焦点を合わせるならば、幼児玩具や育児用品の販売に相談や支援機能を融合させることは大きな意味を持つ。もちろん、そのためには、売場に専門知識や資格(看護師など)を持った担当者を配置しなければならない。いかに人手を減らすかという低付加価値(価格訴求)路線から専門人材を擁した高付加価値(サービス訴求)路線へは、180度の転換であるため容易ではないが、顧客ニーズを起点に売場の再定義を試みた事例として注目に値する(*8)。 ここでは、自店の顧客ニーズをどれだけ深くかつ鋭くとらえ売場を定義できるかが決め手となる。
②問題共有のための多次元コミュニケーション
顧客志向小売業の特徴はそのコミュニケーションのあり方に顕著に現れている。
供給志向型においては、コミュニケーションの内容は商品情報や販促情報が中心であり、基本的に一方向である。販売情報や顧客反応情報のフィードバックが行われるとしても、定量情報が中心であり総じて単純な内容に留まる。これは、一つには供給志向型においては顧客ニーズの多様性が前提とされておらず、集中的な情報分析処理と意思決定が行われているためである。
一方、顧客ニーズの多様性を前提としている顧客起点型においては、顧客に対して、商品情報や販促情報に加えて、成分や品質情報、生産履歴情報、使用方法や管理方法に関する情報、専門家や他の使用者の意見情報など、多次元に渡る情報提供が求められる。主役は顧客であり、顧客の商品・サービス選択と問題解決を助けることが目的となるためである。さらに”顧客とともに”を実行していくため、顧客からの質的な反応情報のフィードバックが極めて大きな意味を持つ。苦情や問い合わせなど具体的な反応情報はもとより、顧客担当者との間で交わされた何気ない会話から重要なヒントが得られることがあるからである。つまり、顧客起点型においては、コミュニケーションの内容は多様であり、双方向性を前提として多元的な流れが形成される。そして、分散的な情報分析処理と意思決定が特徴となる。なによりも顧客接点が情報発信と収集の場として重要であり、顧客担当者の能力とそれを生かす組織設計(機能や部門横断的かつフラットな組織)が決め手となる。
③機能連携と協働の論理に基く機能外部化
先に価値連環システムはネットワーク組織の特徴を有すると述べた。つまり、顧客起点小売業の依拠する流通システムは、硬い”統合の論理”ではなく、柔らかい”協働(連結)の論理”で編成されているということである。
統合の論理のもとでは、価値連鎖(バリューチェーン)全体を自らの統制下に置くため機能のほとんどが内部化される。大型小売業が中間(卸)機能を内部化しメーカーからの一貫物流体制を構築するとか、あるいはPB商品を開発し生産段階まで内部化(契約生産含む)する後方垂直統合がその究極の形である。製販直結の仕組みが最も効率的という通念が統合の論理に根底にある。世界の巨大小売業を支えているのはこの統合の論理である。
しかし、統合の論理は、本質的に需要の差異が少なく標準的商品で対応しやすい市場においては有効であるが、需要が多様で、サービス要素や情報要素が大きな比重を占める市場には、あまりに硬直的で適合できない。顧客起点を志向すると、品揃えの多様さと機動的な組換え、さらに顧客ニーズを深く追求していく専門性などが要求されるためである。いわゆる”いいかげんさ”、”曖昧さ”、”衝撃吸収”などの柔構造の流通システムが必要であり、それを構築できるのは協働の論理である。これは、価値連鎖の各機能要素を受け持つ企業間の取引連携を通して具体化していく。
ただし、これは、たとえば従来の百貨店のように無原則な納入業者依存を意味しているわけではない。そこで求められているのは、信頼と暗黙の契約(共通規範となっている商取引慣行)という日本的取引風土や慣習を生かしながら、目標と成果尺度を共通化させ、共通コストの透明化や緻密な情報交流と共有のもとで共通の問題解決を進めていくメーカー、卸、物流業者との共同取り組みである。
近年、スーパーマーケットと卸、百貨店と納入業者などいくつかの優れた共同取り組みの事例が伝えられるようになった。そこでは、現実の問題解決を目指した新しいマネジメントが浸透しつつある。それは、巨大化や寡占化など皮相な流れからは見えてこない静かな(しかし組織変革を伴う徹底的な)マネジメント革新といえる。
以上
【注釈】
- (*1) William R. Davidson, Albert D. Bates and Stephen J. Bass, “The Retail LifeCycle”, Harvard Business Review , November-December 1976.
- (*2) Clayton M.Christensen and Richard S. Tedlow , “Patterns of Disruption in Retailing”, Harvard Business Review, January-February 2000.
- (*3) 効率と効果の対比については嶋口充輝の枠組みを参考にしている。 嶋口充輝,『顧客満足型マーケティングの構図―新しい企業成長の論理を求めて』有斐閣、1994年、3-8頁
- (*4) 激しい再編成を続ける巨大小売業の背景には財務価値重視の価値観があり、顧客視点は希薄との批判が生まれている。
“When you can’t sell the goods, sell the shop”, The Economist, January 18th 2003, pp53-54. - (*5) 供給起点から顧客視点のクオリティ概念の転換がマーケティング・マネジメントの あり方を変えつつある。
近藤隆雄「サービスの”全体的質”の構造―サービス評価のフレームワーク」『季刊マーケティング・ジャーナル』No.76、2000年3月。
A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L.Berry, “SERVQUAL:A Multiple Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality”, Journal of Retailing, spring 1988. - (*6) Frederick E.Webster, ” The Changing Role of Marketing in the Corporation”, Journal of Marketing, October 1992.
- (*7) Richard Normann and Rafael Ramirez, ” From Value Chain to Value Constellation” ,Harvard Business Review, July-August 1993.
- (*8) “Toys ‘R’ Us: Can CEO John Eyler fix the chain?”, Business Week , December 4 2003, pp.48-53.
(C)2003 Yumiko Mimura & Sakata Warehouse, Inc.