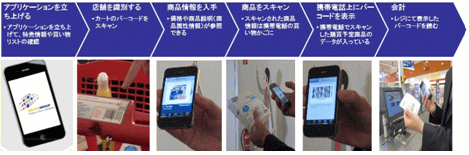第237号事例にみる欧州小売業システム化動向(2012年02月09日発行)
| 執筆者 | 西山 智章 (流通システム開発センター 流通コードサービス部 次長) |
|---|
執筆者略歴 ▼
目次
- 1.メトロ・フューチャーストア(ドイツ)
- ①電子タグの活用
- ②モバイルの活用
- ③画像認識による生鮮ラベル自動発行システム
- ④リサイクリングシステム
- 2.アルバートハイン(オランダ)
- ①賞味期限管理と自動値引き
- ②セルフスキャニングシステム
- 3.デーン(オランダ)
- ①切り花にGS1データバーを利用
昨年9月、GS1*の標準化会議(GS1 Industry Standards Event)がドイツ・ケルンで開催されたのに併せて、ドイツ、オランダのいくつかの小売業の最新システムを視察したのでその最新動向をレポートする。
*GS1=流通情報システム分野における国際標準化機関。世界約110の国と地域で構成され、
日本からは当センターがGS1-Japanとして加盟。
1.メトロ・フューチャーストア(ドイツ)
フューチャーストア(Future Store)は、ドイツ最大の小売グループであり世界小売業ランキング3位のメトロ AGが、08年からドイツ北西部のデュッセルドルフ郊外のTonisvorstで運営する実験店舗である(もともと03年から別の場所でスタート)。実験店舗といってもそのための特別な店舗という訳ではなく、同社のハイパーマーケットである「Real(レアル)」の郊外型標準フォーマット(店舗面積約8、600㎡)の店をそのまま利用している。同店では、消費財メーカー、ITベンダ、サービス企業など75の協力会社と共同で、新技術を元にした新しい店舗オペレーションやサービスが実験されており、効果が確認されたものから他への展開が図られている。以下、新しい試みのいくつかを紹介する。
①電子タグの活用
同店では、現在、商品の入荷時と精肉売場を中心に、電子タグの取り組みを行っている。
入荷時では、トラックから荷下ろしの際にパレット単位に取り付けられた電子タグを読み取り、物流の可視化と検品作業の軽減や在庫管理精度の向上などを進めている。ただし、現在は商品の多くは物流センターで店別に仕分けされてくるため、パレット単位の電子タグが読まれる比率は全体の10%程度に止まっている。(写真-1)
写真-1 トラックが直付けした入荷バースと左右に設置された電子タグリーダ

精肉売場では、店内加工した商品(個装パック)に、商品コード、賞味期限日、シリアル番号等を書き込んだ電子タグを利用している。顧客が商品を手にすると、売場陳列台の全面にセットされた電子タグリーダが感知し、在庫情報がリアルタイムで更新される。これにより、精肉商品の欠品やロス防止などに大きな効果を上げている。
(写真-2)
写真-2 精肉商品に貼られた電子タグと陳列台に設置されたリーダ

②モバイルの活用
携帯電話(モバイル)も、ショッピングシステムをはじめ、購買に関わるさまざまなシーンで活用が試みられている。
例えばセルフスキャニングシステムは、ハンディスキャナの代わりに、商品のスキャニングから精算までの全てがモバイルで行えるようになっている。
具体的には、店内を巡りながらモバイル(のカメラ)で購入したい商品のバーコードをスキャン(商品は買い物カゴへ)。支払いは、モバイルに精算用バーコードを表示させ、セルフ用精算レジでこれをスキャンするだけで完了する。この他モバイルには、スキャンした商品の詳細情報を照会するなどの機能も盛り込まれている。
将来的には、オンラインショッピングへの対応やクーポン配信、NFCを活用した携帯電子マネーなどの新サービスも計画されているとのことである。(写真-3)
写真-3 モバイルによるショッピングの流れ
*画像をClickすると拡大画像が見られます。
③画像認識による生鮮ラベル自動発行システム
欧米のスーパーでは、青果物は量り売りが行われている場合が多い。顧客は購入したい青果物を計量器に乗せ、画面などに表示されている商品一覧の中から該当するものを選択して、売価が入った精算用バーコードラベルを発行、貼付するのが一般的である。
しかしこのやり方では、顧客が商品一覧の中から間違った商品を選択したり、ラベル発行をスピーティに行えないなどの課題があった。
本システムは、計量器にカメラが付いており、商品を乗せると、カメラにより撮影された画像と登録済みの画像パターン(一商品ごとに30枚程度)がマッチング処理され、該当商品の候補が自動的に画面上に表示される。これにより、顧客はいちから商品を探さなくても、より簡単かつ正確に購入商品の選択が可能となる仕組みである。
(写真-4)
写真-4 生鮮ラベル自動発行システム
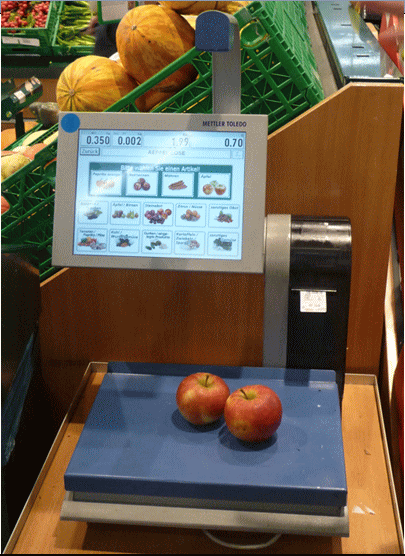
④リサイクリングシステム
写真-5 リサイクリングシステム

同店には、ペットボトル等の全自動のリサイクリングシステムが設置されている。(写真-5)
顧客が容器を店舗へ持参し、本システムへ投入するとレシートが出力される。レシートには、上3桁が980のJANシンボル(バーコード)が印刷されており、レジ精算時の金券として使用できるようになっている。なお、金額は容器の種類などによって細かく設定されている。
システム化以前は、受付にも2名のスタッフを配置していたが、現在は回収されたPET容器や瓶などをバックヤードで整理するスタッフ2名のみになっているという。
本システムは、リサイクルを社会システムとして定着させたい政府、リサイクルを集客に活用したい小売業、さらに金銭が還元されることで消費者はリサイクルに協力しやすくなるというように、3者がメリットを享受できる仕組みとなっている。
今回は、特にGS1システムの関係部分を中心にご紹介したが、同店ではこの他にもサウンドや映像で売場の雰囲気作りや商品販促を行うシステム、ワインや酒の試飲ロボット、双方向コミュニケーションによる案内ロボットなどの多くの最新システムを見たり、触れたりすることができるようになっている。今後もメトログループでは、フューチャーストアを活用して様々な試みを行っていくとのことである。
2.アルバートハイン(オランダ)
オランダ最大の小売業であるロイヤル・アホールドNVが展開する、食品スーパーのアルバートハイン(Albert Heijn)では、現在、鶏肉商品の賞味期限管理とそれによる自動値引きなどに取り組んでいる。
①賞味期限管理と自動値引き
同社では本システムを導入するにあたり、顧客に賞味期限日(原則、商品陳列から1週間以内)が分かりやすいように、一週間の各曜日を色別にした新ラベルシールを開発した。
具体的な使用方法は、商品が納品された段階で、あらかじめ賞味期限日の該当曜日以外をプリンタで黒く塗りつぶし、顧客がラベルに表示されている色を見るだけで、すぐに賞味期限の曜日が分かるようにしている。現在、本ラベルは、納品時にバックヤードで、POS用バーコードラベルと併せて印刷、貼付されている。(写真-6)
写真-6 賞味期限日(曜日)を分かりやすく示した新ラベル
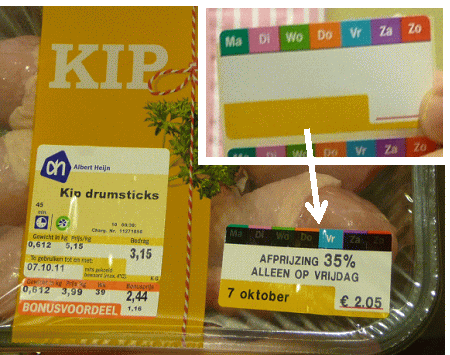
またバーコードには、GTINと賞味期限日がアプリケーション識別子(AI)により表示されている。(写真-7)
写真-7 賞味期限日が入ったバーコードラベル
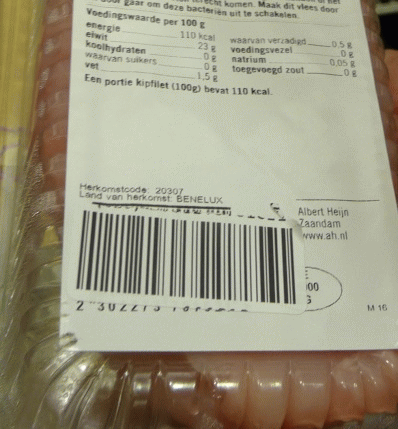
賞味期限日当日、商品がPOSで販売されると、バーコードの賞味期限日により自動的に一律35%の値引き処理が行われるようになっている。これにより、顧客に商品の鮮度を分かりやすくアピールすることができるようになり、また自動値引きによりコストを掛けずに廃棄ロス削減や売上アップなどの効果が上がっている。
なお、現在はまだセルフスキャニングシステム(後述)がGS1データバー未対応のため、バーコード表示にはGS1-128が使用されている。今後、機器の対応や対象カテゴリーの拡大を進めつつ、GS1データバーへの切り替えを進めていく予定とのことである。
②セルフスキャニングシステム
同社では、ハンディスキャナタイプのセルフスキャニングシステムにも取り組んでいる。
顧客は、最初に会員カードを読ませてハンディスキャナを取り出し、店内を回りながら自分で商品をスキャンする。(写真-8)
写真-8 セルフスキャン用のハンディスキャナ

買い物終了時、セルフスキャン用レジにスキャナを返却し、会員カードを読ませることによりレシートが出力され精算が終了する。出口(ゲート)から出る際には、レシートのバーコードを読ませることにより精算確認が行われ、ゲートが開くようになっている。
なお、不正防止への対応として、顧客に対して一定の割合で、サンプリングチェックを実施している。サンプル顧客一人あたり5品目を確認し、未スキャンのものがないかどうか確認しているという。
3.デーン(オランダ)
①切り花にGS1データバーを利用
オランダの中堅食品スーパーであるデーン(DEEN)では、切り花にGS1データバー(拡張多層型)を利用している。
現在は商品コードに加えて、切り花に加工した日付(製造日)をAIで表示し、加工管理などに利用している。将来的には自動値引きなどへの利用のほか、対象商品分野も精肉などの不定貫商品へ拡大していくことを目指している。(写真-9)
写真-9 切り花の管理に利用されるGS1データバー
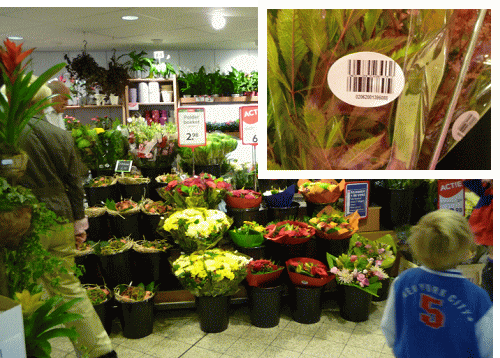
今回、GS1データバーについては、オランダの一部小売業における利用事例しか視察できなかったが、トレーサビリティに熱心な欧州では、特に精肉商品(不定貫)への取り組みが進めつつある。具体的には、GS1データバー拡張多層型などを利用して、従来の13桁のインストアコードラベルから、GTINに加えて重量や売価、ロットNoなどが入ったソースマーキングラベルへの転換を指向している。こうした状況については、また別の機会があれば改めてご紹介していきたい。
以上
(C)2012 Tomoaki Nishiyama & Sakata Warehouse, Inc.