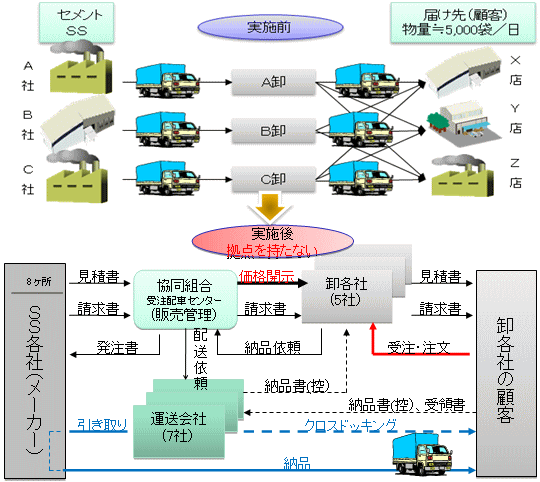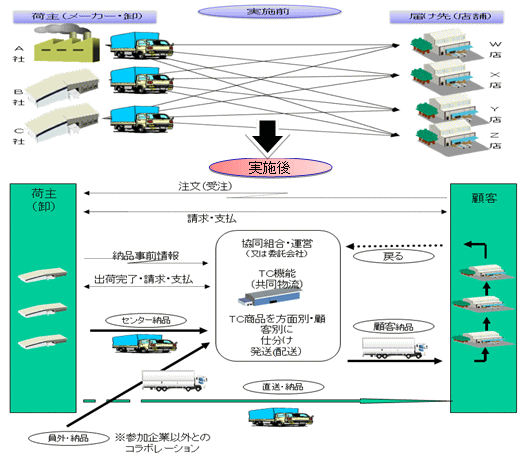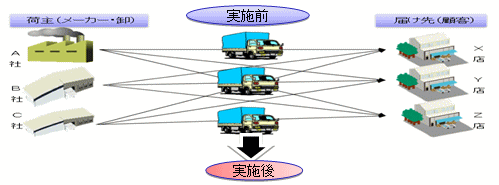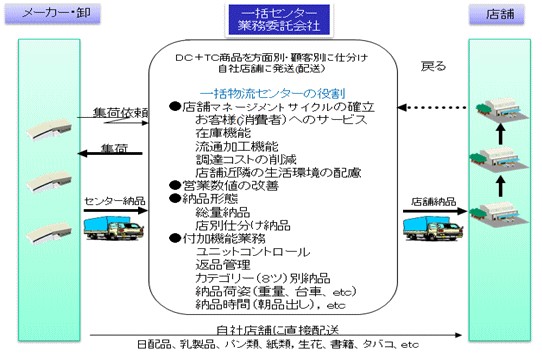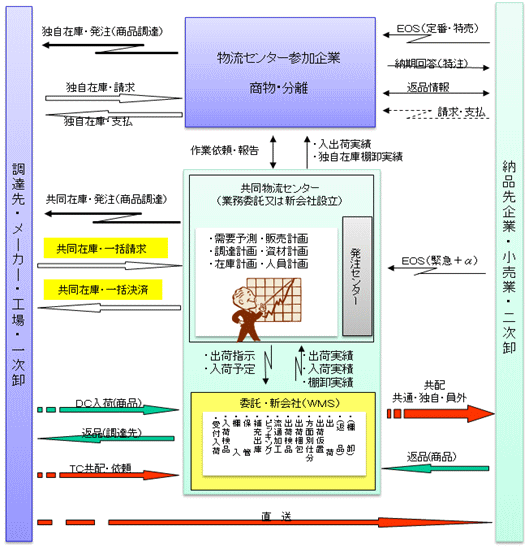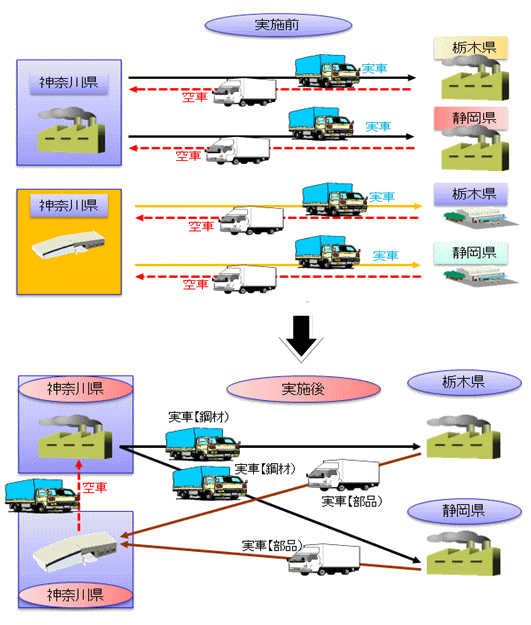第225号物流共同化(&情報システム)の進め!(後編)(2011年8月04日発行)
| 執筆者 | 髙野 潔 (有限会社KRS物流システム研究所 取締役社長) |
|---|
執筆者略歴 ▼
*前編(2011年7月21日発行 第224号)より
*今回は2回に分けて掲載いたします。
目次
6.成功する物流共同化の取り組みの考え方(&留意事項!)
1)先ず、自社の物流を知ること。
●物流は泥臭く多岐に渡る様々なものが多い、先ず、自社の物流を知り、他社の物流を知ること、鉄則!
●物流業務を核に経営資源の選択と集中を考える。
●各社の物流条件をまず把握・見直しなど調整する。
従来の取引慣行(取引口座、納品&サービス条件、在庫水準、etc)など。
2)参加意識の有る企業から始める。
●総論賛成、各論反対が物流共同化の実践にはつきもの、企業変革の意識の高 い企業、同一・共通の目的、目標を持った小数精鋭の企業に絞って取り組むのが肝要と考えます。
●多種多様の意見を持つ沢山の企業を対象に共同物流に取り組むのは難しい。
3)実現性が高く成果が得やすい共同化から取り組んでいきます。
●成果を確実に上げた段階で、次のステップの共同化に進むことが重要(成功のポイント)です。
●従って、スタートの取り組みは、「穏やかな共同化」から始めたい!
●取り組む共同化事業は、「実現の可能性が高い」「共同化のメリットが享受し易い」部分から着手し、早期に共同化事業を立ち上げ、効果を確実にした段階で、次のステップに進むことが成功のポイントと考えます。
4)強力なリーダーシップ(企業&個々人)が必要・・・旗振り役や推進組織がしっかりしていないと進まず、途中頓挫してしまいます。
●リーダー企業
共同物流に適した荷量が確保できる企業が望ましい。
●個々人のリーダーシップ
利害を乗り越え、共同事業の策定、共同化内部の組織固め、種々雑多な意 見調整、等々の「強力な牽引力の発揮」が出来る人材が望ましい。
5)物流共同化は、「公平、公正」と「犠牲・妥協」を旨とすることが必要です。
●特に投資負担、運用費(作業料率)、などに気遣いを持つことが肝要です。
投資負荷の小さい事業展開を心掛けることが信頼関係醸成の第一歩です。
●極力早めに作業コスト負担の在り方を整理すること。
例えば、共同化への参加責任負担(均等割り負担)、企業規模による負担(差等割負担)、作業費負担など。
●機密保持の範囲の明確化
6)物流情報システムの共有化・武装化
複数企業の類似ビジネスモデルを構築、開発WMSの要件を同一にし、1社 では負担の大きい開発コストを共同開発で極少化を狙います。
●質の高いWMS(物流現場管理システム)の共同開発
●参加企業とのデータの標準化、規格化、EDI普及促進(仕入先、納品先、etc)
●参加企業とのデータインターフェイス
7)物流力のある物流事業者との提携
●立地条件を加味した物流拠点の確保
●アウトソーシング(&3PL)事業者との連携
●共同化参加企業と物流事業者との物流子会社などの設立・・・運営のバックアップ事業会社の確保、etc
7.物流共同化の事例
実務・実地で経験した物流共同化の事例などを5ツほど、ご紹介します。
物流の共同化を目指している方、目指そうとしている企業のご参考になれば幸いです。
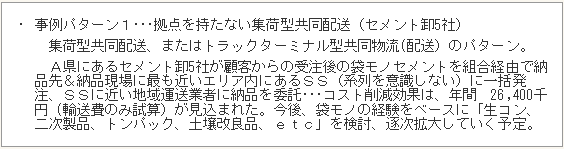
1)配送費(年間)の合理化
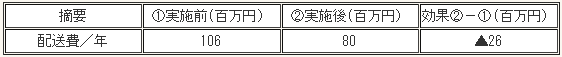
*画像をClickすると拡大画像が見られます。
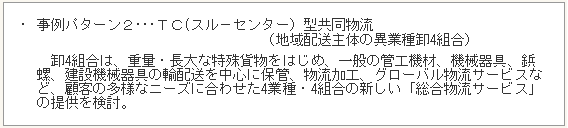
1)事業収支
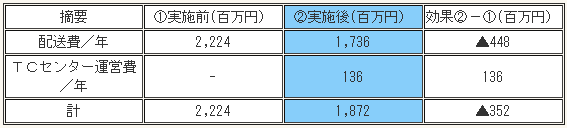
2) トラック台数・積載個口数
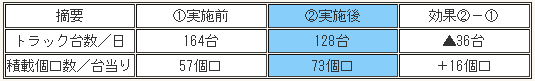
*画像をClickすると拡大画像が見られます。
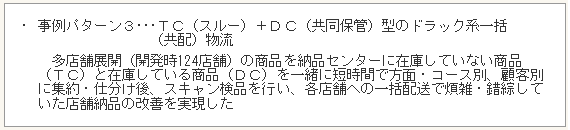
*画像をClickすると拡大画像が見られます。
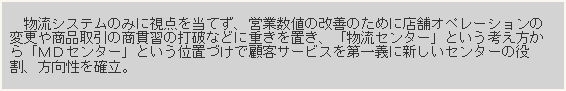
◆参考コスト内訳・・・センターフィ≒2.5%
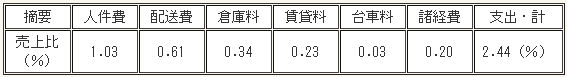
*画像をClickすると拡大画像が見られます。
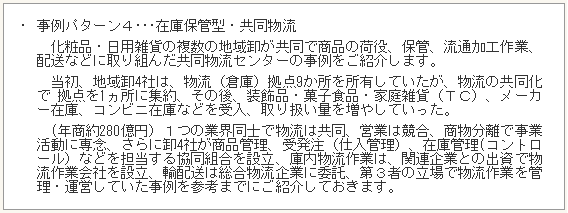
1)在庫保管型・共同物流概念図
*画像をClickすると拡大画像が見られます。
2)在庫保管型・共同物流、実施後の効果内容
①在庫金額の改善推移(実績比較)
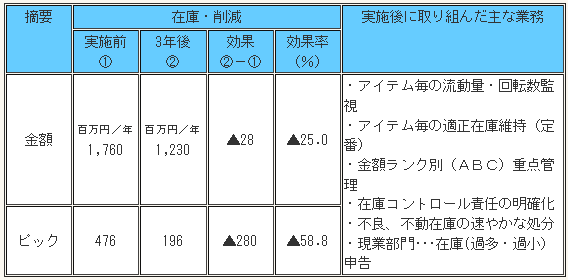
②作業人件費の改善推移(実績比較) 単位:金額(百万円/年)
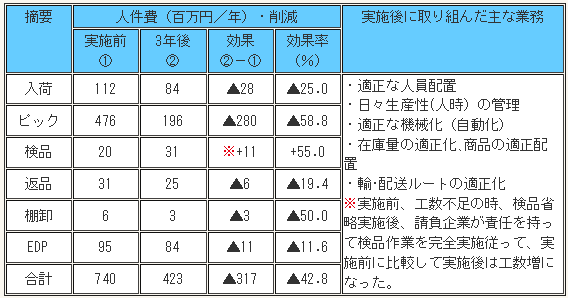
③車輌関連改善推移(実績比較)
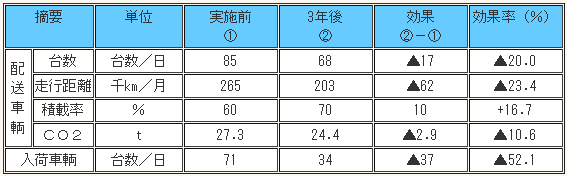
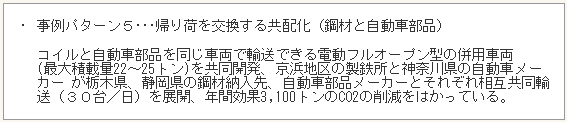
*画像をClickすると拡大画像が見られます。
8.行政(国交省・経産省)の物流共同化への取り組み、etc
1)21世紀の我が国経済社会にふさわしい新たな物流システムを形成する。
コストを含めて国際的競争力のある水準の物流市場(3PL市場)を構築する。
2)環境負荷を低減させる物流体系の構築と循環型社会への貢献
3)物流における地球温暖化対策(CO2削減目標1400万t+500万t)
●物流施設の立地等に関する非効率性の解消
●トラック走行距離削減による環境負荷の軽減
●空港・港湾・道路等の物流関連社会資本と物流施設の一体的機能的な整備を促進する仕組みを構築
4)社会資本の整備(空港・港湾・高速道路等,物流関連)物流関連社会資本を最大限活用し,民間物流施設の整備を推進
5)3PL事業や不動産証券化等、新たな手法による物流施設の出現
●物流効率化・環境負荷の軽減に資する物流施設の整備
●それに伴う輸配送の集約化・共同化などにより、物流コスト・CO2排出量を軽減
◆参考・・・行政の物流共同化に関する支援体制
1)中小企業者などによって、構成される組合、及び任意団体などが物流機能の強化 を図るため指導、調査研究、システム設計、実証実験などに関わる費用を補助
2)法律上の支援措置・・・中小企業流通業務効率化促進法(高度化融資制度)
中小企業が組合や共同出資会社を設立、経営基盤の強化に共同で取り組む事業
●中小企業者が協同で取り組む事業(共同物流センターや共同加工場など)
●貸付対象、事業協同組合、協業組合、共同出資会社、第三セクター、商工会など
●事業協同組合などの組合員が4人以上必要
9.最後に・・・。
1)物流企業の成長戦略が求められています。
企業の成長戦術・戦略の明確化(覚悟!)としてハイレベルの物 流管理、技術、機能、現場密着型の物流実務・実地に関わる変革 が求められていると思います。日本の企業の海外進出、さらに日本 国内における経済・企業の変革からも必要性は、明らかな事実です。
そこで、毛利元成の3本の矢の如く、大企業の物流部門、中堅・中 小物流企業が力を束ねられる「戦略経営型・物流の共同化」、 「情報システム共有化・共同化」を基軸に付加価値の高い物流を目 指していくのも一つの方策と考えます。
2)投資の質が物流企業の競争力を決めます。
自社の物流事業へ投資するのか、3PL事業者やアウトソーシン グで自社の物流を外部に委ねるのか、「どこに」「どれだけ」に加 え、「いつ」何をするかが厳しく問われる時代になっています。
物流共同化に参加する場合でも、リスク覚悟で先行利益を狙う先 手必勝もあれば状況を見極めてから安定利益を確保する後手有利も あります。
定石はなく、企業がそれぞれに知恵を絞るしかありませ ん。
ただ、立ち止まったままという選択肢はないと考えます。
以上
(C)2011 Kiyoshi Takano & Sakata Warehouse, Inc.








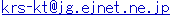 )
)