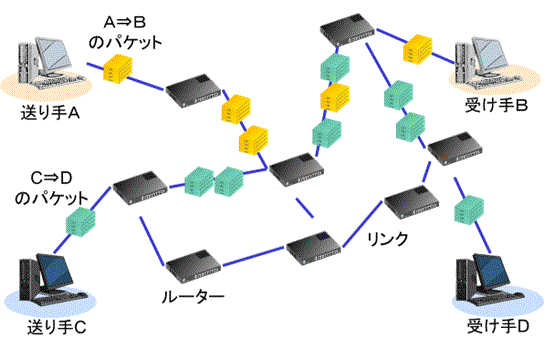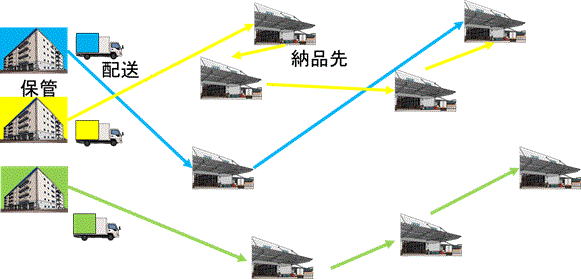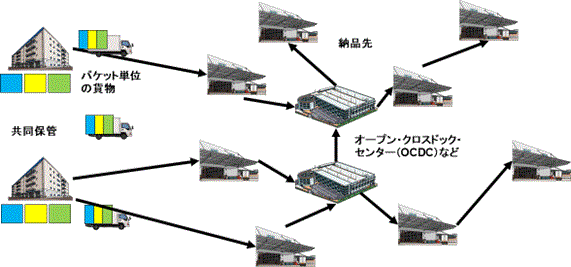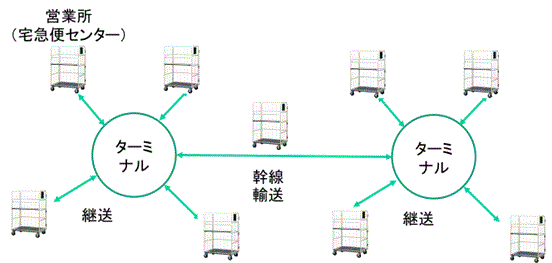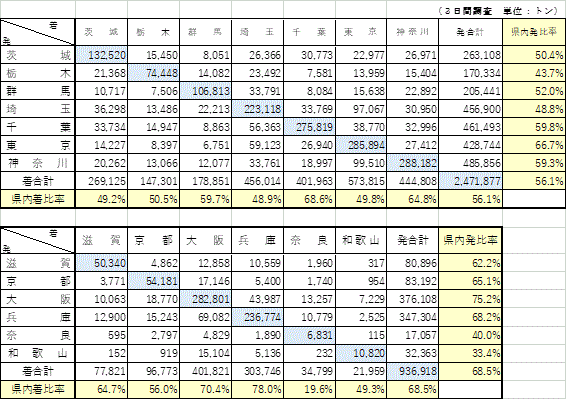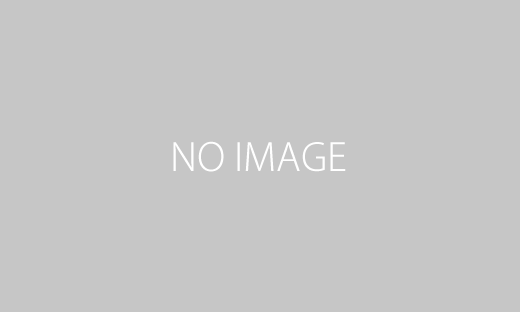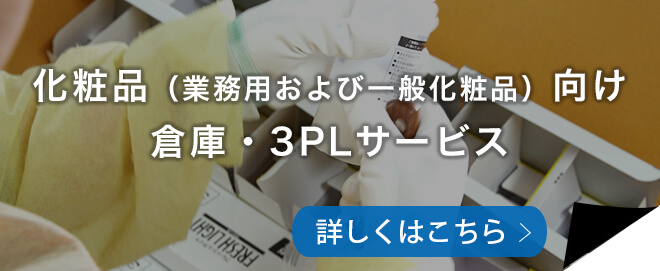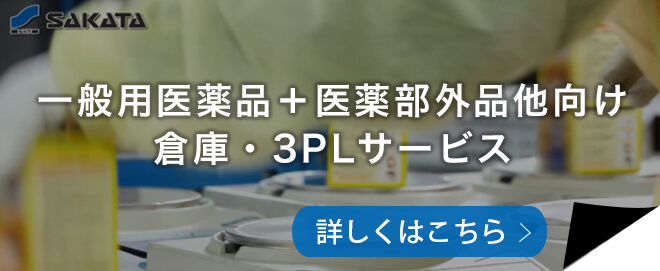第489号 フィジカル・インターネットの未来(2022年8月4日発行)
| 執筆者 | 山田 健 (中小企業診断士 流通経済大学非常勤講師) |
|---|
執筆者略歴 ▼
目次
I.注目されるフィジカル・インターネット
フィジカル・インターネットという言葉をお聞きになったことがあるだろうか。物流現場や実務の世界にはまだあまり浸透していないかもしれないが、政府や学者、コンサルタントの間で最近注目されている構想である。
直近では、2022年3月、経済産業省と国土交通省が事務局を務める「フィジカル・インターネット実現会議」で、物流のあるべき将来像「フィジカル・インターネット」を実現するため、2040年を目標としたロードマップの取りまとめが行われた。民間では、2021 年開催の国際フィジカル・インターネット会議(IPIC:International Physical Internet Conference)第8回会議で、初の日本からの発表として、ヤマトグループ総合研究所と野村総合研究所が、日本国内におけるフィジカル・インターネット関連の取組状況に関して報告した。
情報発信は増えてきたものの、あまりに壮大な構想であるため具体的なイメージがいまひとつという方も少なくないと思う。そこで連載最終回にあたって、筆者なりに物流現場での具体的な姿に落とし込み、その実現性について考えてみたい。
II.インターネット(DI)の仕組み
インターネットと称している以上、本家(?)のデジタル・インターネット(DI)をモデルにしていることは明白である。いまさらで恐縮ではあるが、話を順序だてて進める都合上、あらためてインターネットの仕組みを整理しておきたい。
インターネットは、送り手がデジタル・データという形でネットワークに情報を流し込むと、それらがパケットという小さい単位に分解され、通信リンク上のルーターを介して受け手に伝送される。データ通信には、パケットのフォーマット、ネットワークホストの識別、パケット通信のやり方などを定めた「インターネット・プロトコル」という基準が設けられている。
図表1ではデータの送り手Aからパケット単位に分解されたデータ(黄色)がルーターを経由して受け手Bに届けられている。同じように、送り手Cから送信されたパケット(緑色)もルーターを介して受け手Dに届けられる。多様なルートを通って受け手に到着したパケットは当初の順番通りに並べ替えられ元のデータとして認識される。このように、網の目のように張り巡らされたWeb上を分解されたパケットが目的地に向かうので、どこかのルート(回線)が遮断されても影響を受けずに情報伝達ができる。
III.フィジカル・インターネット(PI)
この仕組みをフィジカル、つまり物流の世界にも適用しようというのが「フィジカル・インターネット」の基本的なコンセプトである。
従来の物流を単純化すれば、発・着の事業者同士をそれぞれ直接結ぶやりとりが主流だ(図表2)。宅配便などの小口貨物や特別積合わせ便などはあるものの、一般的には図で色分けしたように、荷主単位での保管と配車により納品先に届けられる。物流の仕組みが主に発荷主中心に構築されることを前提としているためであり、業界ではいわば“常識”である。
混載貨物である宅配便も特別積み合わせ便も、原則としてバラバラに集荷した貨物をターミナルに集めて着のターミナルまで運ぶ「ハブ・アンド・スポーク方式」となっている。
いまさらいうまでもないが、ドライバーの高齢化とドライバー不足は2024年問題によってさらに深刻となることが予想されている。一方で、トラックの平均積載効率は4割程度にとどまる。ドライバーの劇的な増加や自動運転などの実用化が実現しない限り、有限で貴重なトラック資源をいかに有効活用するかが喫緊の課題であることに疑いの余地はない。
こうした問題意識の中、2011年頃より論文やジョージア工科大学、IPICなどから発信され始めたのが「フィジカル・インターネット(PI)構想」である。PIを筆者なりの解釈で示すと図表3のようになる(図の色分けは荷主を表す)。
共同保管されパレットやロールボックス等の 「規格化された容器」 に分割(パケット化)された貨物が、さまざまなトラックの空きスペースに混載され拠点やオープン・クロスドック・センター(CD)を 経由して、納品先まで運ばれる。手作業でそのような計画を立てるのはまず不可能なので、AI・アルゴリズムがコスト最小化、最適積載効率、最短ルートなどの条件を満たすパケット単位での保管とトラックなど輸送手段の最適化を行う。
PIが構想どおり機能すれば限りあるトラックの有効活用が図れる。いわば、「究極の共同物流システム」といえよう。
筆者がこの構想を知った時の印象は「そんなのできっこない」。物流実務に携わる多くの方の感想も同じようなものではないか。
基本的には現在さまざまな方面で取り組まれている共同物流と大差ないようであるし、その共同物流も実現には荷主同士の利害や条件調整に多大な労力を要しており、成功事例はまだ多くないのは周知のとおりである。まして、業界の壁を越えた取り組みとなると、混載できる商品、荷姿、商慣行など、ハードルの高さは気が遠くなりそうである。
そのような事情もあるのかは定かではないが、先の経産省、国交省の公表した「フィジカル・インターネット・ロードマップ」も抽象的な表現にとどまり、具体的な姿や実現性などは見えてこない。
IV.なぜヤマトが?
不思議なのは、これも先に紹介した通り、実事業者であるヤマトの子会社ヤマト総研が野村総研と共同研究を進めていることである。物流事業者が「拒否反応」を起こしてもおかしくない構想に、子会社とはいえ参加しているということが筆者には合点がいかなかった。
ところが、構想の理解が進むにつれ納得感が深まってきた。宅配便は基本的にほとんどの区間を通してロールボックスによって運ばれる。これはPIでいうところの「パケット」そのものである。集荷した貨物をロールボックスに積載して発ターミナルに集め、幹線便で着ターミナルへ送り込み、そこからラストワンマイルへの配送を担う営業所(宅急便センター)へ継送する。典型的な「ハブ・アンド・スポーク」方式である(図表4)。
ヤマトはこの方式をPI方式に転換することを検討しているのではないか。つまり、ロールボックスをターミナルに集めることをせず、多方面に向かうトラックの空きスペースにバラバラに混載、オープン・クロスドックセンターなどを経由して、最終的に全国4,700か所といわれる宅急便センターへ届ける。
長距離はともかくとして、この仕組みは比較的短距離では有効と思う。ハブ・アンド・スポーク方式のディメリットは、近くの届け先でもいったん集約ターミナルを経由しなくてはいけないからである。極端な話、隣の営業所へ継送するのでもターミナルまで送る必要がある。
こう考えるとパケット化された宅配便や路線便など、小口貨物ではPIの検討余地は大いにあるものといえるのではないだろうか。もちろん、以上の構想はあくまでも筆者の勝手な想像によるものであり、関係先に確認したわけではないことをお断りしておく。
V.一般貨物の可能性は
ではPIの実現性は小口貨物に限られるのであろうか。当初の話と矛盾してしまうが、一定の条件のもと一部の中ロット近距離輸送においては可能性があると考える。
以前、本コラムでの拙文「第474号数字の独り歩きに注意(2021年12月21日発行)」で紹介させていただいたことではあるが、国交省「貨物純流動調査2015年」による国内貸切トラック輸送の8割強が関東域内、関西域内といった「地域ブロック内」で動いている。地域ブロックをまたぐ長距離輸送は1~2割程度の貨物の偏りがある上に、比較的往復実車が進んでいる分野でもあるので、PIの対象から外した方がいいだろう。
そこで注目されるのが同一県内あるいは地域ブロック内での1~2トンといった中ロット貨物である。関東でいえば、神川県内あるいは神奈川⇔東京西部、埼玉といった域内配送である。中ロット貨物は特別積合わせ便には載せられないので、運送会社内でいろいろ工夫して積み合わせを行っている「中途半端」な貨物である。
また、地域ブロック内での配送習慣は「回転率重視」である。近場に配送した際は帰り荷を探すのではなく、いったん空車で営業所や発地に戻り次の配送をこなすので、計算上の積載効率は50%となる。複数の納品先を巡回して配送する「ルート配送」も、出発時では100%の積載効率が最後は0になるから平均積載効率は50%となる。「トラックの6割は空車で走っている」といわれるのはこうした事情によるところが大きい。
図表5は、関東、関西の地域ブロック内での発着トン数をまとめたものである。おおむね4割から6割が同一県内、それ以外がブロック内他県に配送されている。パレット化やロールボックス化されたこれらの中ロット貨物をPI上にうまく乗せて空きスペースを埋めることができれば、4割という積載効率を大幅に高めることは可能かもしれない。
中ロット貨物がどのくらいを占めるのかを知るには、さらに調査を深めなければならないが、フィジカル・インターネット構想を実現するための有望かつ効果の高いマーケットといえるのではないだろうか。
現在、筆者が関係する学術研究グループで、こうした域内配送の最適ルート選定プログラム開発が進められている。おおがかりなサーバー容量など必要とはせず、また従来の配車シミュレーション・ソフトのようにち密な条件設定をすることなしで簡易にエリア内のルート選定ができる仕組みである。
多くの事業者が参加するクラウド上で、こうしたプログラムを利用できる環境が整ったときにフィジカル・インターネット構想は日の目を見るのかもしれない。微力ながら、そうした取り組みの一端でも担えていければ幸いと考えている。
最後に、読者の皆様と情報発信の場を与えていただいたサカタウェアハウス様をはじめとする関係者の皆様に感謝申し上げます。
以上
(C)2022 Takeshi Yamada & Sakata Warehouse, Inc.