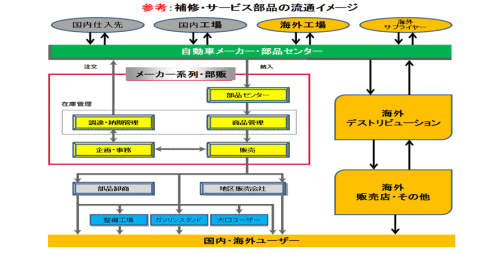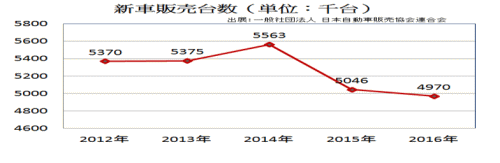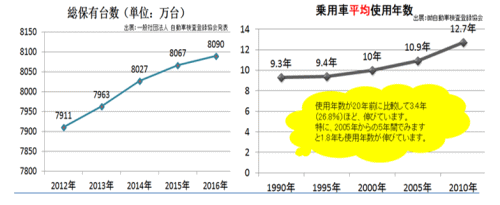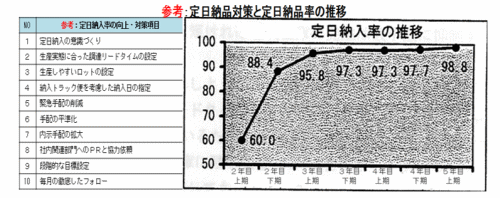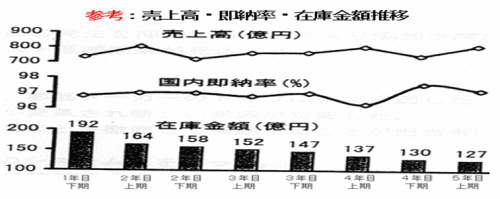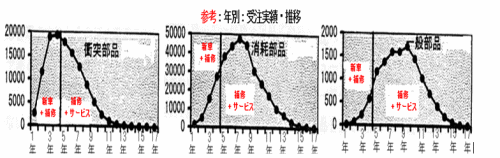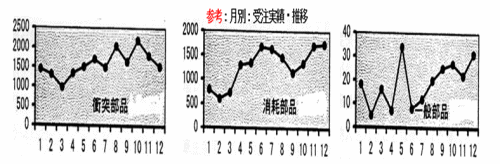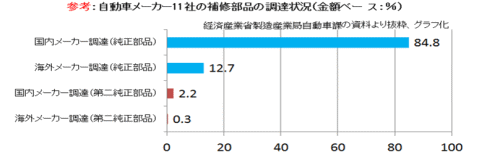第371号 自動車「補修・サービス部品」を考える。 (2017年9月7日発行)
| 執筆者 | 髙野 潔 (有限会社KRS物流システム研究所 取締役社長) |
|---|
執筆者略歴 ▼
目次
- 1.はじめに。
- 2.N社の補修・サービス部品拠点(物流センター)の概要
- 3.自動車補修・サービス部品と保証について。
- 4.自動車用補修・サービス部品の動向
- 5.補修・サービス部品の供給期間
- 6.補修・サービス部品の定日納品対策
- 7.補修・サービス部品の在庫(需要)削減・事例
- 8.これからの補修・サービス部品市場を考える。
- 9.最後に。
1.はじめに。
自動車「補修・サービス部品」とは、自動車メーカーの責任で新車の販売から、その車が廃車になるまでの期間に保守・点検修理、交換などの目的で必要とする部品のことです。自動車メーカーは、新車が発売されてから廃車されるまでの期間、部品の供給責任を持ち、旧型車、現行車のそれぞれの数世代に渡る補修・サービス部品の管理をしています。自動車メーカーにより違いがありますが約15~20年ほど、保管しています。
昨今、部品の共通化が進んだとはいえ、各社ともに管理部品点数は50万点~100万点、在庫ありアイテム点数(入出庫が無くても在庫がありで登録されている部品)もメーカー毎にマチマチですが、30万点から50万点と膨大な点数に達していると思われます。
私が自動車メーカーの部品物流部門のプロジェクトに在籍していた頃は、設計変更などで、月間3,000~5,000点(新設、修正、廃止)の動きがありました。ビックリです。廃止された部品も市場からの出荷要求のために在庫が必要になります。部品番号が異なっても互換性有りの部品があれば、新旧親子対応(紐付け)で管理をします。
日本の自動車保有期間は長期化の傾向にあり、車検や定期点検、修理時の部品交換などで安定した車の性能を保っています。現在は、素早く修理完了を目指しているため部品交換の発生機会が増加しやすい傾向にあるように感じています。国内の生産と自動車販売市場が低迷している中、車の使用年数が長くなり、一時的な補修・サービス部品の需要が見込まれるのではないかと期待(想定)されています。さらに、補修・サービス部品の将来見通しは、従来のガソリン車、新しい技術のハイブリッド車、電気自動車、プラグイン・ハイブリッド車、自動運転車などで補修・サービス部品市場の変革が訪れようとしています。
私もサラリーマン時代に生産車両は競合、補修・サービス部品は協調と自動車メーカー11社の持ち回りで物流研究会にも参加したことがあり、中国圏と関東圏の補修・サービス部品の共同配送に関係者が積極的に取り組んでいたのを思い出し、そこで、N自動車を中心にした補修・サービス部品の現状を考えて見ることにしました。
2.N社の補修・サービス部品の拠点(物流センター)概要
N自動車は、全国に散らばっていた複数の自動車の補修・サービス部品倉庫を昭和47年(1972年)頃から神奈川県相模原市南区(北里大学・北里病院前)に約13万坪(427,000㎡)の敷地面積に東洋一と言われた大規模高層自動倉庫5棟、後楽園の3倍はあると言われる平屋倉庫1棟を含めて3棟(1~2層)、大規模な輸出作業場を兼ねた倉庫棟1棟の9つの倉庫棟を配置していました。倉庫が増設される毎に大型車両を使っての各地からの移転作業、長いことかかりました。
その後、10年?前に輸出作業棟(4号棟)は、売却を行い、輸出梱包作業を各号棟で吸収するようになりました。N自動車が生産する乗用車・商用車全社種の補修・サービス部品、並びにオプショナルパーツを内製5工場と部品メーカー約250社から受け入れ、集中管理する一大補修・サービス部品の供給基地になっています。
この時、逐次建築した各号棟への移転の経験が化粧品・日用雑貨の共同物流(建築面積約6,600坪)の移転(8ヶ所から一ヶ所)をはじめ、コンサルになってからの複数回の移転にも役立ちました。
現在、全ての補修・サービス部品を国内全域に供給、さらに、N自動車が販売している世界約200前後の国々に輸出する最重要拠点として稼働しています。この大規模な拠点(9つの倉庫棟)から年間約2,500万件(ディリー約10万件)の出荷オーダーを捌いて日本全国、並びに世界各地に出荷しています。9つの各倉庫棟は、部品の機能、形状・寸法、重量・材質、月間出荷量などの要素で分類し、倉庫毎に大きなサイズの部品(フード、フェンダー、ドア、ガラス、タイヤ)、中小部品(ワイパー、ブレーキパッド、ランプ)などの品質の保持や作業性、ロケーション把握のしやすさを考慮して、それぞれの部品形状や重量にマッチしたラックで大半が管理されています。
補修・サービス部品は、形状がまちまちで大小があり、一人の手では扱えない重量物、ガラス製品・パネル製品のように破損やキズに注意を要するものもあり、それぞれ専用のラックに保管されています。さらに、重量棚の上部をパレット単位の入出荷に便利なユニットロード用の保管、下部の棚をバラ単位の出荷用保管にしたラックなども沢山使用しています。庫内搬送の主役はフォークリフトですが、入出庫に電動の無人車やコンベヤを利用している号棟もあります。
また部品の受け入れから出荷まで、現場作業での情報処理の基本を支えているのがバーコードシステムです。バーコードをスキャンして処理するハンディターミナルを全面的に導入、ミスの少ない迅速・効率的な作業を目指しています。
3.補修・サービス部品と保証について。
自動車部品は、自動車メーカーの工場において新車に組み付けられる部品と、自動車の購入後に行う車検や整備、修理、機能向上などに使用する補修・サービス部品に大別されます。自動車は多様な車種・車型の乗用車、トラックが存在し、それぞれの専用部品から成り立っています。
特に修理に緊急を要することが多く、スピーディに部品を出庫するために在庫の必要性が高く、全国に点在する部販(部品販売店)からディラーの整備部門、独立の整備事業者などに供給する必要があります。また、出荷頻度が少ない部品でも車検や整備、修理に支障をきたさないように常時在庫する要があるため適正な在庫を維持・管理する幅広い在庫戦略が重要になっています。
このように流通系小売業などで扱う食料品や雑貨などの生活商品とは異なる流通の特性を持つのが自動車用補修・サービス部品なのです。補修・サービス部品には、自動車メーカーのブランドで供給される純正部品と部品メーカーが独自のブランドで供給する優良部品があります。自動車メーカーは、販売した自動車が廃車になるまで、消耗品の交換から修理までの補修に必要な全取り扱い部品を在庫、車が市場にある限り、補修部品を供給する責任を負っていると言われています。
自動車修理の保証を受けるためには、純正部品が取り付けられていることがメーカーの保証条件の前提となっており、純正部品は部品そのものの保証もされています。また、低価格で供給する第二純正部品があります。これは、純正部品と同程度の品質が確保されていることが条件になっているとのことです。
さらに、優良部品があります。国内外の純正部品を製造する部品メーカーが製造し、自社ブランドで販売する部品です。純正部品とは異なり、車種やメーカーを越えた部品の共通化が図られたものが多く、メーカー系列以外の整備工場などで優良部品を多く採用しているようです。これは、純正部品の企画と異なり、優良部品を取り付けた自動車は、自動車メーカーの保証を受けることが出来ないことになっているとのことです。優良部品自体は、部品メーカーによる保証、時には部品卸販売会社や流通段階でも補償負担に応じているとのことでした。
4. 自動車用補修・サービス部品の動向
自動車を新車、中古車で購入した後は、適切な維持・管理が必要になります。補修・サービス部品の需要は、故障修理や事故修理だけでなく、自動車の車検や定期点検などで、保安基準に適合するよう維持・管理する役割を果たしています。自動車の平均使用年数は、自動車の品質向上や所得低迷などの理由により、長くなってきています。
今後、低迷する新車販売市場の影響で自動車保有台数は伸び悩みが顕著になると思われます。さらに、高齢化社会となり、高齢者の重大事故の増加、少子化がさらに進み、働き方改革(月60時間の残業制限)などでの所得低迷などの社会的背景から、若者の車離れで、新車販売台数の減少は避けられないものと思われます。先々の補修・サービス部品などと共に車検・点検、整備、鈑金塗装、部品・用品販売、保険などのビジネスの基盤になる総保有台数の減少が考えられ、新車販売がこれからは、右肩上がりで推移することが期待できないこと、さらに輸入車の増加を考えると、国内の補修・サービス部品業界には、先行きの厳しさが待ち受けているものと想定されます。
このような環境条件下で、軽自動車の保有比率の向上にともない、今後、整備需要や補修・サービス部品の需要の減少で業界の売り上げや需要動向に影響が出て来るものと思われます。しかし、ハイブリッド車、電気自動車の普及、自動運転車などの新たな商品、新たなサービス、例えば、電気自動車の新たな急速充電装置、自動運転の3D地図、電子回路の点検、維持管理など、新しい市場の役割が求められていくと思われます。
その一方で、車両の長期保有にともない車両故障が増えるものと予測されています。車両点検のスピードと充実、在庫部品の適正な維持管理で即納率・供給率の向上、並びに補修・サービス部品供給体制のサービス性の向上などで、各メーカー系列店は、さらなる新車販売支援が求められるようになると思われます。
市場の変化に対応した同業他社との競争力向上のために補修・サービス部品の物流のコスト低減、在庫があれば安心から適正在庫が求められ、補修部品流通においても小ロット多数回物流、系列を超えた製(部品メーカー)・配(中間流通・自動車メーカー)販(ディラー・部品商・小売)のサプライチェーンの構築が補修・サービス部品業界全体で考え、在庫削減、コスト削減が求められる時代になると思われます。
5.補修・サービス部品の供給期間
自動車は、モデルチェンジや生産中止などで生産ラインでの生産が終わった後も、点検・維持管理、修理用の部品が必要となるため、自動車部品メーカーは、補修・サービス部品としての供給義務を負います。一般的には、生産ラインでの生産が終了しても供給義務があるため、設備や型などを廃棄してしまうわけにはいきません。
どれくらいの期間、この補修・サービス部品の供給義務があるかというのは、自動車メーカー、部品の種類、納入場所によっても違いがあります。15年~20年という期間が必要との声を聞いたことがあります。一般的に自動車部品メーカーの多くは、自社の部品の寿命を自動車の寿命よりも長く維持・管理する傾向にあります。自動車の製造終了から、10年+αというのが一般的な補修・サービス部品の供給期間のようです。このあたりは、部品メーカー側では15年としているところが多いようですが、自動車メーカーとの取決めがないケースも多く、何十年ぶりに補修・サービス部品の発注が数個届いたというようなことも稀にあるようです。特に海外の発展途上国からの旧型部品の注文もあるようです。
このため、企業によっては、市場に車が走っている限り、全数廃却せず、少しずつ在庫を処分しながら供給可能な状態を保っています。この場合も廃止、即、金型を廃棄することはできず、保管しておく必要があり、悩みの種となっています。金型の保管には、スペースが必要で管理コストもかかります。そこで、一部のメーカーは、金型を保管コストの安い海外にあずけている企業もあるとのことです。また旧型の大量の金型を大型高層自動倉庫で保管・管理しているとの話しを聞いたことがあります。
自動車業界は流動する部品点数がきわめて多いため、金型の種類も多くなるという事情があります。ある部品を一つだけ欲しいというのが補修・サービス部品となりますので、ある車種の生産が終了してから何年も経ってから、いきなり一つだけ注文してくるというようなこともあります。その要請に対応するのが補修・サービス部品であり、コストがかかる要因になっています。
6.補修・サービス部品の定日納品対策
部品の需要は、新車生産用、KD用、補修・サービス用として発生します。従来、補修・サービス用部品は、「後回しでも良い」「後回しでもしょうがない」という考え方が自動車業界の生産側、補修・サービス手配者側、共に常識?になっていました。納入成績自体、仕入れ部門では即納率、供給率と区分けして納品出来れば「よし」としていいました。定日納品は最も期待されるサービス性と考え、新たに納入指示日への納入率(定日納品)による管理を導入し、その向上のために次の施策を検討、実施していました。
さて、これは、数年前の某・自動車メーカーの補修・サービス部品の定日納品率向上対策として取り組んだ概要の一端をご紹介するものです。補修・サービス部品に携わっている人達の意識を改革し、部品メーカーの窓口である営業担当者だけではなく、生産部門の人、トップ層とも直接話し合い、商売の原点である定日納品を守って貰えるよう、守れるように徹底的に議論しました。
特に、定日納品率の悪い部品メーカーとは、何回も話し合いを行い、某社に対する改善要望があれば、可能な限り手配条件におりこんでいきました。部品メーカーの生産をしやすくするために某社の手配内容(2~7項)もきっちりと改善しました。40万点にのぼる補修・サービス部品について1点、1点、部品メーカーと協議し、定日納品を守るために必要条件を手配条件におり込みました。
その結果、定日納品率が予想を大幅に上回ることができました。これは、部品メーカーのトップ層まで定日納品の意識が浸透したこと、部品メーカーと某社の担当者の地道な努力の積み上げによるものであり、定日納品が定着した現在では、部品メーカーから最初はフォローが厳しくて大変だったが、部品手配も改善され、生産がしやすくなったとの声を頂いたそうです。改善は、要求するだけでなく、相手(部品メーカー)からの要求に応えて改善したことで、部品メーカー側からやる気が起きたとの声が上がっていました。
7.補修・サービス部品の在庫(需要)削減・事例
今まで、適正だと思っていた在庫をさらに、削減させるために泥臭い在庫(需要)予測の精度を高め、対策を講じた結果、売上高が上昇傾向にあるにもかかわらず、在庫が3年半で33.9%減少しました。在庫月数では、3.2ヶ月が1.9ヶ月まで目標を上回って減少したそうです。
また、在庫が減少しても国内向け即納率は、逆に上昇傾向になりました。欠品が起きた場合の解消スピードも以前に比べて大幅に早くなりました。さらに、短期間で需要が変動する要因として
①実需≠受注:販売会社が在庫を多く持っていたため、在庫の実需が見えませんでした。そこで、販売店の売上を実需として捕まえるようにしました。
②季節的変動(雪、雨(豪雨、台風)、暑さ、寒さなどによる影響を事前にキャッチしていませんでした。そこで、季節指数設定方法の工夫で対応しました。納品は、トラック便を鉄道便・船便などに変更して対策しました。
③新車販売台数の月毎の変動:車検・点検を加味した月別車検対象台数をベースにした予測をするようになりました。
④需要の急増減:部品の販売キャンペーン、拡販キャンペーンの実施方法などの改善で対応、
⑤海外による影響:発展途上国への輸出入の大量ロット化の改善とリードタイムの長期化で輸出物量の平準化と見直しで対処、
⑥価格アップ前の駆け込み需要:早めの価格改定情報を提供、リードタイム(平準化)を意識した受発注に変換。そこで、調査した実需に近い受注実績をもとに予測と実績の誤差率の少ない計算式(指数平滑法)を使用することにしました。
衝突・消耗・一般部品のグループ別、新車使用部品・新車使用終了部品、国内・輸出別に最適な指数を選択して在庫予測を行い、大幅な在庫削減が実現しました。
先ず、17年間の受注実績を調査しました。その結果、需要パターンは、上記の参考:年別受注実績推移の通り、①衝突部品②消耗部品③一般部品をロングレンジで見れば、はっきりした需要パターンがあることが分かりました。この需要パターンから衝突部品は、新車のうちは少し傷を付けても交換しますが、古くなると交換しなくなるという顧客心理が働いているようでした。
上記の参考:月別受注実績推移(短期間の推移)をみると需要が大きく変動しています。ロングレンジの需要パターンを重視し過ぎると予想と実績が乖離してしまう恐れがあるように想定することができました。
8.これからの補修・サービス部品市場を考える。
自動車市場というと、新車に話題が集まる傾向にありますが、自動車は新車を販売すれば終わりということではなく、繰り返しになりますが、その後も車検や部品交換、故障、事故の際の修理などが必要となってきます。次の新車購入時には、中古車として下取りに出す中古車市場があります。新車であろうが、中古車であろうが購入した顧客は、購入後もその自動車の安全と機能の正常な維持のための部品交換、修理などのサービスを求めています。
私が自動車メーカーの情報システム部門から部品物流部門に移動した時は、先ず、受注後、3日以内に部品を出荷することを前提に即納率を98%以上の確保が大事、さらに、部品物流部門は、新車の販売支援のためにあることを肝に命じ、サービス優先、儲けは二の次だと先輩から教わりました。その当時の在庫は同業他社よりも多いなと感じていましたが、概略3.2ヶ月位だったと記憶しています。
今は、様変わりで補修・サービス部品関連事業者は市場の要求に応えるためにあらゆる補修・サービス部品を迅速に提供する使命と物流コストを意識して在庫数の削減を行っています。
これからの時代は、様々な自動車の普及が急速に進み、各企業の補修・サービス部品を取り扱っている部門は、それぞれの系列メーカーの強みに沿って次世代自動車向けの補修・サービス部品の取り扱いを考え、試行錯誤した経営戦略を練りはじめていく必要があると感じています。ガソリン車、ハイブリッド車、プラグイン・ハイブリッド車、クリーンディーゼル車、エンジンを持たない電気自動車などが主流になると思われます。従来の自動車と大きく異なり、取り扱う補修・サービス部品も変わりそうです。駆動装置や車両構造の変化に伴い、現行車を整備する際に必要であった整備技術や技能はもちろんのこと、新たに必要な整備技能などが発生してくると思われます。
電気自動車は、バッテリーやモーター、インバーターといった新しい駆動装置で走行する車が開発、市場に送り出され、新たな機能で走行するため、補修・サービス部品の追加が必要になるものと思われます。電気自動車の整備では、アッセンブリ交換に集約される可能性も考えられます。
また、部品のモジュール化が進むことにより、一つの部品が大物化することで部品単価が上昇しますが、整備機会や部品交換機会は減少すると見られ、補修・サービス部品の売上の低下が懸念されると思います。さらに、自動運転技術も急速に進み、次世代自動車の整備・修理点検アイテムが簡素化されていくものと思われます。さらに、自動車の電子化が進めば、コンピュータでの診断内容が高度化する一方で、工数自体は減少しそうです。
コンピュータとそのソフトは複雑な仕組みになり、従来の整備経験では対応が難しくなりそうです。専門性の知識と新しい設備投資が必要になると思われます。これからの自動車の点検・修理は、電気自動車を始めとする次世代自動車が国内市場に普及することにより、日本でも点検・整備事業が自動車メーカーや販売店(整備)の対応の仕方が変わっていくと思われます。
9.最後に。
自動車が地球環境に与える影響に対する関心の高まりや資源枯渇への懸念を背景に、ハイブリッド車、電気自動車、プラグイン・ハイブリッド車などの次世代自動車の市場導入が急速に進みつつあります。補修部品を取り扱っている関連企業や関連整備事業者は、次世代自動車の普及に備えた対応を行う必要が出て来るものと思われます。さらに、自動車に関わる産業は、従来の産業分野、コンピュータ、電気関連産業、etcの技術が集約され、益々グローバル化が必要とされて来ています。
海外の自動車の補修部品市場(アメリカなど)は、修理技術を習得した人達が高収益を求めて独立系修理店(自動車販売店、以外の部品販売・修理を行う店舗すべてを指す)の経営に乗り出しているとのこと、安価な非純正部品を揃え、修理工賃を安価にして、どこのメーカーの車でも修理してもらえること、修理店が近隣にあり、修理時間などに融通が利く点などから、自動車販売店よりも広く支持されるシステム(仕組み)や構造となっているようです。
アメリカでは、メーカー系列と独立系の売上比率は、概算でメーカー系列25~30%、独立系修理店70~75%を占めているそうです。日本の補修部品市場は、メーカー系列がほとんどだと思います。
次世代の自動車の普及が進む頃には、日本の補修部品市場も主役は、メーカー系列の自動車販売店から独立系修理店に移り変わっているかもしれません。従って、補修・サービス部品市場においてもこれからは、世界に目を向けていく時代が来ています。
日本も中長期的な視点での補修・サービス部品産業を考え、補修・サービス部品事業も10年以上経過した補修・サービス部品での新車販売の競争サービスを避け、メーカー系列を離れて国内外の補修・サービス部品を集約化、一本化し、世界で類を見ない流通ルートの変革で日本独自の安心安全を第一とした日本市場での国内外の車を問わず、補修・サービス部品の供給体制、強力なアフターフォロー体制をリードする日本市場を期待しています。
以上
(C)2017 Kiyoshi Takano & Sakata Warehouse, Inc.