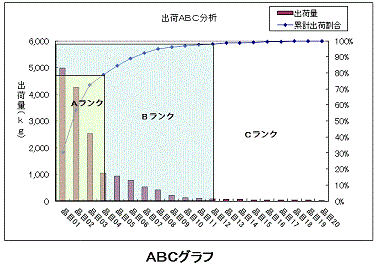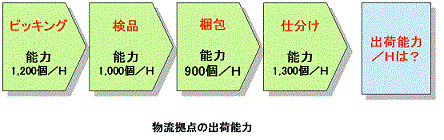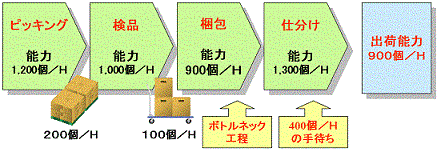第310号 物流拠点コストダウン~マクロとミクロの視点 (2015年2月17日発行)
| 執筆者 | 山田 健 (山田経営コンサルティング事務所代表 流通経済大学非常勤講師) |
|---|
執筆者略歴 ▼
目次
1.はじめに
(1)料金値下げは限界に
物流コストを下げるもっとも手っ取り早い方法は何かといえば、それは複数の物流業者を競わせるコンペを行うことである。価格競争を通じて物流の枠組みを変えることなく確実にコストは下がる。
しかし最近の深刻な人手不足の一方で、物流業者の多くが利益率の低下に苦しんでいる。このような状況で料金値下げは限界であるし、下手に値下げ交渉しようものなら、仕事を断られるのがオチである。物流コストダウンは物流の仕組みを変えて実現するしかない。
本稿では、物流の要である物流拠点に焦点を当て、マクロとミクロの2つの視点からコストダウンにプローチしていきたい。
2.物流拠点配置の原則~マクロの視点
(1)単純ではない物流拠点配置
メーカーを例にとれば、理論上では「工場から物流拠点までの輸送料」「物流拠点にかかわる費用」そして「物流拠点から納品先までの配送費」の合計が最小となるように物流拠点の最適立地を計算すればいい、ということになる。ただ、現実にはこの他にも以下のような多くの要素を検討しなければならず、それほど単純な話ではない。
(2)複雑な連立方程式
●品目数が多いか少ないか
扱う商品の品目数も重要な要素である。品目数が少なければ拠点数を増やしてもそれほど問題はない。
飲料のように比較的品目数が少ない商品では、在庫管理に手間がかからないので、短納期を要求されるコンビニチェーン向けの在庫拠点を分散させることも行われている。
一方、10万点以上にもおよぶ機械補修用のパーツなどは在庫を分散させたら管理に膨大な手間がかかるので、リードタイムの許す範囲で極力集約することが望ましい。
●出荷量が大きいか小さいか
出荷量の大小も考慮する必要がある。出荷量がそれほど大きくなければ拠点を1か所に集約することも可能だが、出荷量が大きい場合はたとえ配送リードタイムが長くても、一か所に集中させることはリスキーである。
大量の出荷が集中すると、パート・アルバイトや配送車両の確保が追いつかなくなるし、作業スペースも足りなくなるので、拠点を分散させておく方が安全である。
●輸送に何を使うか
輸送手段も影響する。鉄鋼や紙など、重くて大量輸送が必要な製品は工場から拠点まで海上輸送を利用することが多いので、港湾に近い場所に物流拠点を立地させる傾向にある。また、分散させると輸送効率が落ちるので、拠点数は極力絞られる。
●海外生産品
海外生産品を調達する場合は港や空港が物流の起点になる。一般的には、定期コンテナ船の便が多い東京、横浜、名古屋、大阪、神戸を中心に関東、関西地区に立地する傾向が強い。これは、港が国内生産の場合の工場と同じように物流の起点となるためである。
海外生産比率が9割を超えるアパレルや、同じく7~8割の家電製品は関東、関西に2大拠点を構えることが多くなっている。
●納品先の立地
消費財では大消費地である福岡、関西、関東、札幌の4か所周辺に拠点を設置するのが有利である。生産財は地方であっても納品先の工場への配送がしやすい地域に立地する。
●パート・アルバイトの集めやすい場所
軽くて小さい消費財を扱う拠点では、パート・アルバイトを大量に集める必要がある。このような拠点では他の条件よりも、まずは「人集め」のしやすい地域への立地が優先される。
住宅が少ない都心部や人の住んでいない工業地帯、高所得者の多い地域などは不向きである。比較的中程度の所得層が住んでいる郊外の団地やマンションの近く、徒歩か自転車で通勤できる距離というのが望ましいところである。
●企業の戦略
拠点立地はコストや立地条件だけで決めるのではなく、競争力の源泉と考える企業もある。これは、主に配送リードタイムを差別化の手段と位置付ける事業戦略にもとづく。
端的にいえば、配送費無料は当たり前で、注文翌日配送から当日配送へサービスレベルをアップしようとしているネット通販業界が該当する。ある大手ネット通販では、全国1か所の拠点からスタートし、販売量の増大と当日配送エリアの拡大を背景に拠点数は拡大の一途をたどっており、いまでは全国に10か所の拠点を配置するにいたっている。
●リスク・マネジメント
東日本大震災では、物流拠点が損害を受けて商品の調達や供給が止まってしまった多くの例が報告されている。そのため最近では、物流のリスク・マネジメントの観点から、関東、関西の2拠点を設置し、一方が被害を受けたらもう一方から商品を供給する、というように1か所がダメージを受けても他の拠点でカバーできるように拠点の分散化を図る例もみられる。どの程度拠点の分散化を図るかは、被害程度の想定レベルと許容できるコストとの微妙なバランスを考えた上での判断となり、なかなか簡単ではない。
このように、物流拠点の配置は複雑な連立方程式を解くようなものである。原理原則を十分踏まえつつ、諸条件に応じた柔軟な対応が求められる。
3.ミクロレベルの物流拠点内作業効率化
拠点配置の見直しは得られる削減効果も大きいが、その分仕組みを大幅に変更するための時間と労力も要する。それに対し、拠点内作業の効率化は、短期間で着実なコスト削減を実現できるテーマである。ここでは代表的な2つの手法を紹介する。
(1)拠点内動線に注目したABC分析による在庫レイアウト改善
●知っているがやらない
ABC分析による在庫レイアウト改善は、物流拠点の作業に携わる人なら、おそらく知らない人はいないと思われるほどポピュラーで初歩的な手法である。いわば拠点内作業効率化の一丁目一番地といえる。
では、それほどの基本であればさぞかし多くの現場で実行されているのだろうと考えたいところであるが、現実はかなり違う。知っているものの実行している現場は少ない。ABC分析に基づき継続的にレイアウト見直しを実施している現場はさらに少数派である。
●ABC分析による在庫レイアウト改善の考え方
物流拠点内の作業を効率化する第一のポイントは在庫の置き方にある。入出荷の際に商品の在庫場所まで移動する時間は、作業全体の半分以上を占めるといわれている。この移動時間はトヨタ生産方式でいうところの、付加価値を生まない「運搬のムダ」であり、本来ゼロにすべき時間である。この移動時間(=距離)を最小限にするために拠点内の動線に注目した手法が、ABC分析にもとづく在庫レイアウト改善である。
ABC分析の理屈はいたって単純だ。よく動く商品をAランクとして入出荷口の近くへ配置し、動きの少ない商品をB,Cランクとして、それぞれ拠点の奥や工場などにまとめて配置するというものである。これだけで、入出荷の移動時間は大幅に短縮され、作業が効率化される。
ABC分析の対象は「出荷量」あるいは「出荷頻度(出荷日数)」となる。一般的に、素材などのように荷姿が大きくて量も多く、品目数が少ない商品は「出荷量」、消費財のように小さくて少量で、品目数が多い商品は「出荷頻度(出荷日数)」が適している。
さらにレイアウトを厳密に行う場合は、この両方を使う場合もある。
●ABC分析の原理は「2:8の法則」
ABC分析は、「パレートの法則」を応用した分析である。「パレートの法則」とは、「あらゆる経済活動は全体の20%の行動により結果の80%が決まっている」という普遍的現象のことである。これは、「20-80の法則」あるいは「2:8(ニ-ハチ)の法則」などといわれている。物事は均等に分布するのではなく一部に偏在する、つまり必ず偏りがあるという現象のことである。
●ABCグラフで視覚的に把握
ABC分析は、出荷量(または出荷頻度)の多い順に品目を並べ、その累計出荷割合を計算する。累計出荷割合とは出荷総量に対する各品目の累計量の割合である。
そして、累計出荷割合がおおむね80%までをAランク、98%までをBランク、残りをCランクに分類する。
右のグラフでは、出荷20品目中上位4品目(Aランク)で全体の80%の出荷を占めている。逆にCランクである13位以下の8品目は出荷量のわずか2%程度にすぎない。これらの在庫を混在して配置、管理しておくことが非効率であることはあらためていうまでもないことであろう。(*画像をClickすると拡大画像が見られます。)
(2)拠点内作業の総生産性に注目した生産性向上
物流拠点の作業で大切なのは個別作業の生産性ではなく「総生産性」である。総生産性とは「ある目的を遂行するための生産性」をさす。
●ボトルネックが総生産性を決める
いま、「物流拠点から商品を出荷する」という目的で、次のような作業を行っている。ピッキングから検品までそれぞれの作業で1時間当たり1,200個、1,000個、900個、1,300個の処理能力がある。それでは、この物流センターの出荷能力は1時間当たり何個になるだろうか。
難しい計算など必要ない。900個である。他の作業がいくらがんばっても一番遅い作業の能力以上の生産性は上がらない。この物流拠点では、ボトルネックである梱包の処理能力が総生産性の制約になっている。ピッキングと検品では処理能力に時間当たり200個の差があるので、工程間に200個の作業待ち商品がたまっていく。同じように検品と梱包の間には100個の滞留が発生する。逆にボトルネックの梱包と仕分けでは、仕分けの処理量が400個多いため、手待ち時間が発生する。
この理屈は、ゴールドラット博士の著書「ゴール」に出てくるTOC(Theory Of Constraint:制約理論)として紹介されているので、ご存知の方も多いだろう。(*画像をClickすると拡大画像が見られます。)
●総生産性をアップするには
総生産性をアップする一つの方法は、ボトルネックに他の工程を同期化することである。先の例では、ボトルネックである梱包の時間当たり900個の処理能力に合わせて、他の作業にかかわる人員を減らすことになる。人員を減らしても総生産性には何の影響も与えない。
ただし、この方法は現在の出荷能力(総生産性)で問題がない場合に限る。処理能力900個では出荷時間が遅くなり、トラックの集荷に間に合わないケースが発生している、などの問題がある場合は総生産性を上げるための方法を考えなくてはならない。
その際のもう一つの方法は、ボトルネックの能力を上げることである。これは、ピッキングや仕分けのように生産性の高い作業から人員を梱包ラインに移動することを意味する。少々忙しくなるが、ピッキングをしていたパートが途中で梱包ラインに入り、場合によっては検品も行ってまたピッキングに戻る、という具合に一人何役もこなしてもらうわけである。
4.おわりに
本稿では、もっとも効果が期待できる2つの切り口を取り上げたが、拠点内作業効率化には他にも多くの手法がある。ただ、いずれも「無駄な動きをなくす」「手待ち時間をなくす」ことが取り組みの原点であることに変わりはない。
以上
(C)2015 Takeshi Yamada & Sakata Warehouse, Inc.