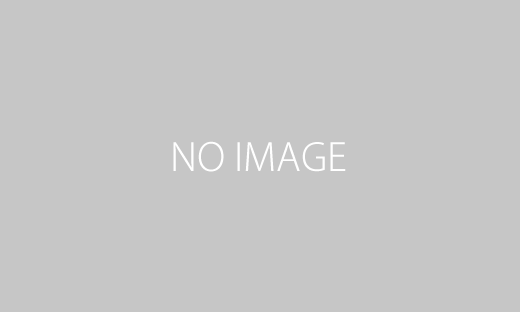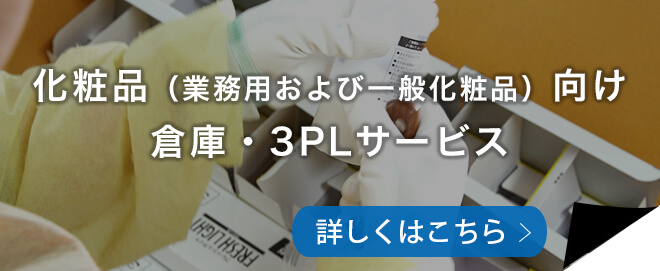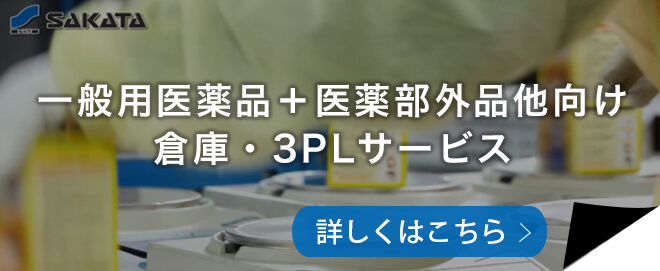第105号船社物流の史的展開とその競争力(2006年8月10日発行)
| 執筆者 | 合田 浩之 東海大学 海洋学部航海工学科国際物流専攻 講師 法学博士 |
|---|
目次
【1】船社物流とは 問題の所在
船社物流とは、(伝統的には)定期船を主力業務としていた邦船社が、フォワーダー業・倉庫業・混載業・陸上輸送関連業務を展開することと定義する。船社物流の歴史は、1980年代半ばまで遡り、既に20年近い時間が経過した。邦船社には、船社物流への参入時においては、社内に業務に関する知見が殆どなかった。その一方で、既存のフォワーダー・倉庫会社といった国内企業に伍して発展したのか、ということについては、案外、議論がなされていない。そこで、拙稿では競争力という視点から船社物流を考察したい。
【2】邦船社の物流部門への取り組み
2-1 船社物流の草創期
先進国の定航(コンテナ船運航)企業は、1980年代半ばに転機を迎えた。転機の出現は、①業の側と、②荷主の側、③会計学・経営学の進化に原因があった。邦船社に焦点をあててこの点を回顧すると、
①業の側の事情変更
一言でいえば、定航部門の行き詰まり感である。中進国海運による追い上げと、欧米系船社には今風に言えばIT技術で劣位にあった。
特に前者を敷衍すれば、単純なPort to Portのコンテナ輸送であれば、運賃競争に劣位にあり、彼我の品質の差がなくなったということである。これに対する船社の対応は、一つには、自社が提供するサービスの付加価値を高めるという方向であった。当時の言葉でいえば、総合物流ということになるが、今風に言えば、貿易物流のワンストップ=ショップの提供であり、海陸一環輸送の観点からの陸上輸送部門(鉄道・トラック(コンテナトレーラー・小口のトラック)への展開であった。後者については後述する。
二つには、低価格の中進国海運に貨物が流れる現状を受けて、他船社積前提で、自社系列のNVOCC・混載業者*1を立ち上げることであった。これら二つの戦略は自社グループの影響力が及ぶ貨物量を増大させることを暗黙のうちに企図していたともいえた。
②荷主の側の事情変更
1985年のプラザ合意後の急速な円高の進行は、日本製造業をして、生産拠点のアジアシフト・欧米現地生産拡充を促した。従来の北米・欧州航路共、往復航の貨物の源泉は日本市場(日本市場は邦船の金城湯池であった)が殆どであったが、貨物の発生地が日本からアジアへ移るということを意味した。邦船は、日系貨を死守せねばならなかった。他方、アジアには、日本製造業が満足する質のフォワーディング・陸送サービス等は、然程発達していなかった。それゆえ荷主筋は、船社に対して現地進出を促した*2。そして、欧米での現地生産は、基幹部品の内陸工場(日本⇒欧米)への滞りない輸送(今風の言葉でいえば、「JIT物流による」複合一貫*3輸送)の需要が、急速に拡大することを意味した。
③経営学・会計学の事情変更
今では当たり前のこととなった「在庫管理」の思想が、日本企業に普及しはじめたのは、実にこの時代のことなのである。「コンテナ」なる用具は、船社においては輸送手段を異にしても簡便に積み替えることができる用具*4という認識は、コンテナ草創期からあったはずであるが、「コンテナが運送用具であると同時に、移動する倉庫である」という発想は、この時期はじめて認識されたのである。欧米船社に対して劣位にあったと表現したIT技術とは、この時代では、顧客照会用の「コンテナ追跡管理技術」を意味した。当初はコンテナ単位、いずれP/O・カートン単位への貨物可視化へと進化する。
2-2 物流思想の深化と業務意識の変化
これまでの議論を整理すると、「物流部門」に期待された機能とは、定航業務を「培養・支援」する手段という発想が色濃かったことを看取できる*5。しかし、荷主の利潤拡大・費用圧縮には際限がない以上、在庫の圧縮の進行も極限まで求められ、それは、「週1便」の定曜日配船(在来船時代(月末配船が基本)から考えれば驚異的な配船である。)が当たり前であった定航部門とNVOCCとしての物流部門との社内利害の矛盾を高めた。
荷主利益に立てば、NVOCC部門は、自社系統の定期船に固執するわけにはいかないことは当然であるが、それが容認できないとなると、荷主が多頻度配船を要求する以上、定航部門も配船増を達成しなければならない。自力(単独)で配船増を模索した邦船社も、90年代前半位には、その限界を直視せざるを得ず、アライアンス=他社との共同運航という発想の転換を容認した。筆者はこの時点で、物流部門と定航部門の社内矛盾も思想的に止揚されたと考えている。つまり物流は、定航培養の手段ではなく、定航とは次元を全く異にする商品であり、逆に、理論的には「物流」の一手段(パーツ)として定航機能が存在し、従属・奉仕すべきものであることを、社内の誰もが疑わなくなったのである。
この時期になると、特定荷主の特定案件毎に、結果的に全世界に総花的に群生していった物流海外現地法人群の「ブランド統一」や「ネットワーク効果の追及」が叫ばれるようになる*6。要するに、それまでそれぞれ単独行動をとっていたA国・B国・C国…の現地法人が、有機的に連携するということである。
もっとも、起源を異にする同一機能を有するグループ企業の整理・統合は、今後残された課題である。例えば、コンテナ船船積み支援を意図した混載会社・NVOCC会社・エアーフォワーダー*7の重複である。また船社傘下の港湾運送企業もフォワーダー業を独自に展開している。荷主に対するワンストップサービス提供という哲学が是であるのであれば、いずれ斯様な企業内再編成が、大規模に生じるであろう。
【3】競争力の鍵
船社物流は、日本の荷主に追随する海外展開を見せた。そのエッセンスは、「日本人による日本語での日本式のサービスを外国で提供する」ということであり、特定荷主の特定案件を橋頭堡として、当該案件を中核に成長するという業態である。
しかし、船社物流の黎明期には、少なくとも、フォワーディング・倉庫業の「本質」の部分で勝負する能力・知見を企業内に保持していなかったこと、日本には既存のフォワーダー・倉庫業者が、顕在であったにもかかわらず、何故に船社が海外で飛躍し彼我の形勢が逆転したのか?ということを考える必要がある。筆者は、その鍵は、「英語力」ある社員の大量蓄積という社内資源と、ネットワークという(世界各国の優良「港運会社」「倉庫会社」「フォワーダー」を臨港代理店として長年起用してきたという)伝統的遺産にあるとみる。
【4】現状と展望
日本社会において国際「物流」業は20年の歴史を経過し、伝統的な日本のフォワーダーにおいても国際畑の人材は、邦船社にさすがにキャッチアップしたといえる。その意味で邦船社の優位性の一つは色あせたといえるだろう。
船社物流の黎明期に、船社内部には、フォワーダー・倉庫業の本質の部分で勝負する能力を企業内に保持していなかったと先に述べたが、それは、日本国内では、伝統的なフォワーダー・港運等が群雄割拠するに船社は手を拱いているということである。
即ち、日本の船社物流は、日本国内での直営の「現場」の欠如・不足という事情がある。メーカーでは、現地工場で工場管理を行った人材が、日本では生産管理部門やマザーファクトリーに勤務することにより、その技能・知識を維持、あるいは高度化することが一般的に見られるが、船社物流の人材が東京に復帰したときは、マザーファクトリーが用意されているとはいいがたい。船社物流の物流マンとは、日本においては、持ち株会社的な本社の、外国子会社経営管理スタッフであり、外地では、現業の管理者であり、対顧客窓口に過ぎないのである。そして日本国内に(必ずしも)腰が据えられていないという現状は、消費財・汎用的な部材の輸入物流の増勢が続く中、船社物流ビジネスを拡大する上で、ネックの一つに国内体制(特に小口配送体制)があるということを意味する。船社各社は、どのように対応をするのであろうか。既存の企業グループ内に「解」が見出せなければ、外部優良企業との連携が模索されてしかるべきである。
ところで、外国語力という点では、商社運輸というコンペティターが存在する。物流は、商品売買の派生需要であり、売買には代金決裁・信用供与は重要である。商社は、金融を物流サービスとワンセットで用意できる物流市場のプレーヤーであることが案外等閑に付されている。この点も、今後の各社の対応に興味が湧くところである。
以上
| *1 | コンテナ船草創期にも邦船社は、自社系列の混載会社を立ち上げているが、これは自社あるいは同盟船社へ限定した船積み支援的な意味を持つという点で、次元を異にする。 |
| *2 | 既存の国内の倉庫業・フォワーダー業者も日本の荷主に追随して海外展開をはじめるが、それにも関わらず、素人のはずであった船社が物流業を成長させたことが、注視すべき重要な事実である。 |
| *3 | 通し船荷証券を発行する船舶と鉄道の複合輸送そのものは、戦前から提供されているが、この在来船時代の一貫輸送と別次元で捉える船社関係者が普通である。米国での貨物列車の発車時刻を厳守すべくコンテナ船はスケジュールを維持するようになって、複合輸送が、JIT物流の一環であるという意識が含まれるようになったからである。 |
| *4 | RORO船やコンテナ船の荷役を「革新荷役」と表現した事がある。今では、一部の港湾運送事業者以外用いない言葉である。日本におけるコンテナ船の普及は、1960年代後半の高度成長の時代であった。当時、在来船荷役が限界に達して、日本各港で大規模な滞船が生じた時期であった関係で、コンテナの出現を「荷役の革新」という側面のみに強い印象をもった船社や港湾関係者には多かったように筆者は思う。 |
| *5 | 当時、物流を担うセクションは港湾物流部あるいは港湾流通部と称され、コンテナ船運航のインフラである港湾部門と同一セクションであったことも、物流はコンテナ船周辺部門=支援部門という意味があったことの現れである。後述するように1990年代中葉に船社の思想に変貌が生じた時に、港湾部門と物流部門は分離して別のものとして扱われる。 |
| *6 | 製造業各社が、海外に総花的に展開した生産拠点を再編成する動きに呼応している。 |
| *7 | 定航船社のエアフォワーダー業界への進出は1960年代である。定期船営業の蒐貨力を前提に、定期船貨物が航空機に流出することへの対策として進出がなされた。 |
(C)2006 Hiroyuki Goda & Sakata Warehouse, Inc.