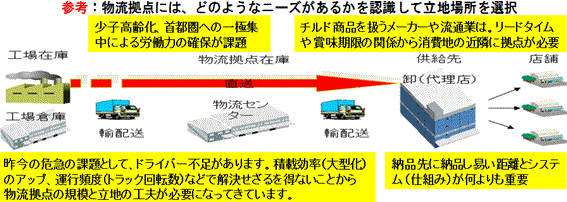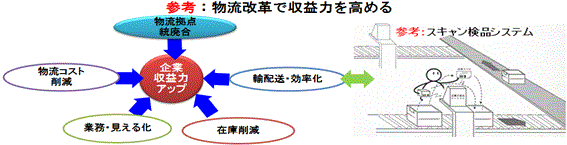第404号 リアルからネットへの変革の中での物流実務(仕組み)を考える。(前編)(2019年1月22日発行)
| 執筆者 | 髙野 潔 (有限会社KRS物流システム研究所 取締役社長) |
|---|
執筆者略歴 ▼
目次
1.はじめに。
物流業界に於いて、製配販の効率的なサプライチェーンを構築する上での物流拠点システム(仕組み)が注目され、さらに、インターネット取引が急成長、BtoCの当日配送、時間指定納品などのジャストインタイムでの過酷なサービス合戦、BtoBにおいても納期順守(期日・時間指定など)による厳しい物流・配送競争が求められています。
昨今、インターネット取引の普及で少量・多頻度、時間指定などによる輸送業務がトラックドライバー不足、燃料価格の高騰などの要因で物流拠点内システム(仕組み)における納品条件の緩和、生産性向上などの変革・改革が求められ、物流全般の見直しが始まっているようです。
その変革の風は物流拠点の立地する場所や在庫する商品の量、アイテム数などと共に配送リードタイム、保管料、荷役料、人材確保などの物流サービスレベルまで影響してきています。さらに、拠点の立地によって入荷する商品の調達物流コスト、販売物流コストにも影響を与え、さらに、マルチテナント型物流拠点の需要の広がりで、コスト、品質・精度、納期などのサービスレベルの見直しまで左右されるようになってきました。
リアルからネットへの変革の中で、物流実務(仕組み)について考えて見たく思います。
2.物流拠点は物流活動の基本です。
平成30年の2月に福井県内の国道8号線の各地で約1,500台の車が立ち往生、ドライバーの救援、荷物の遅延に四苦八苦していました。物流拠点は、立地場所、在庫量、保管アイテム数、入出荷量などを勘案して納期を基点に保管スペース・荷捌きスペース、保管料や荷役料、配送リードタイムなどの物流サービスレベルが決まってきます。拠点の立地によって入荷する商品の調達物流コストと顧客への販売物流コストも決まってきます。つまり、コストとサービスレベルという物流の主要な要素が物流拠点の立地によって左右されてしまうのです。
拠点(場所)の変革は、物流の変革と言い換えることができると思っています。物流活動は、「必要な時に、必要な量を、必要な場所」にローコストで正確にお届けする使命を持っていると言われています。その物流拠点の場所と共に拠点内システム(仕組み)は業種業態、並びに企業内外の環境条件によってその位置付けや要件が異なるため個々の用途や天災、人災などを含めた最適なシステム(仕組み)を創り出されなければなりません。物流拠点には、どのようなニーズがあるかを認識して極力、ニーズに適応した立地場所を選択するのが肝要です。
流通業の最終納品先となる物流拠点の立地の最も大きなファクターは顧客・店舗に商品を納品し易い距離とシステム(仕組み)が何よりも重要と考えます。さらに、チルド商品を扱う製造業や流通業は、リードタイムや賞味期限の短さなどから消費地の近くに拠点を配置することが肝要です。
昨今の喫緊の課題としてドライバー不足があり、積載効率(大型化)のアップ、運行頻度(トラック納品回転数)で解決せざるを得ないことから物流拠点の規模と立地の工夫が必要です。さらに、少子高齢化、首都圏への一極集中による労働力の確保などの課題が山積しています。
3.物流拠点が所有から賃借にシフトしています。
物流拠点における最も顕著な変化は「所有から賃借」への流れです。
かつて物流事業者は倉庫や物流センターなどを自前で建設し所有するのが当たり前でした。それこそが競争力の源泉と考えられてきました。倉庫を賃借するのは、あくまでも短期的、臨時的な対応であり、安定的に需要が見込める案件については、自社所有が基本でした。
ところがここ10年位で状況が一変しました。今まで、地味で投資とは無縁な存在でした物流拠点が有利な投資物件として注目を浴びはじめたからです。外資系、及び日本の大手不動産企業・部門は、豊富な資金力を背景に業界の常識では考えられなかった巨大なスペースと機能的で快適な物流拠点を次々に開発・建設しています。昨今の物流業界の拠点集約、大型化の傾向もこの動きが後押ししていると思われます。このような物流不動産ファンドの登場により、賃借という比較的「気軽」な方法で物流拠点を確保することが容易になりました。いままでは、荷主や物流事業者が資金やリスクの面で取り組めなかった大型物流拠点(物流センター)の確保が柔軟に実現できるようになったことで物流拠点・拠点内システム(仕組み)の変革に大きく貢献し始めました。
このような物流拠点の進化の背景には、ネット通販の急拡大に伴う物流機能の強化の必要性と近年の物流業界における取り扱い物量の増加が著しくなったことです。さらに、翌日配送から即日配送へと配送時間の短縮が急激に進んできました。これらに対応するために物流機能の整備・強化はネット通販会社や物流企業にとって大きな課題となり、その物流機能の整備・強化の核となるのが物流拠点・拠点システム(仕組み)です。以前は「倉庫」と呼ばれ、企業活動のコア部分をサポートする業務というのが一般的な印象でした。従来の「倉庫」では、即日・翌日配送などの最先端サービスに対応しにくいため最新鋭の大型物流拠点・拠点システム(仕組み)を開発するようになってきました。この開発を外資系、及び日本の大手不動産部門が担い、物流企業への賃貸が増え、拠点配置の自由度が高まり、物流の変革が急速に進み始めました。
4.これからの物流拠点(物流センター)の運用力の変革
物流拠点の機能は、センター全体の運営管理の精度向上が取引条件として必要になってきました。複雑化する顧客ニーズへの対応、物流の効率化、環境対策、マネジメントの強化など、物流の変革で物流センター(倉庫)独自の実践的な物流改革・改善が求められています。
例えば、配送の効率化、在庫削減などの目的に応じて最適な物流拠点の配置、物流センターの構築などの統廃合が全国的に実施されてきています。
さらに、生産性の向上のための作業導線の短縮、サービス、品質・精度の向上などの目的で拠点内レイアウトの改善、物流コスト(輸送費・人件費)などの削減要素を精査し、改善プランと削減目標を策定、具体的な施策の実行が始まっています。在庫の削減は、定量的な在庫分析により、適正な在庫量の決定方策の導入(商品別・得意先別の在庫分析、商品別在庫回転率、不良在庫の把握、適正な生産量・仕入量の策定)などが実施され、輸配送の効率化、運賃削減、環境対策(CO2算出量の自動計算)、現状の輸配送コストの可視化と削減要素の精査、配車計画や輸配送エリア・ルートの見直し、標準化など、物流業務に関わる自動化、省力化、運用全般の変革が進んでいます。
さらに、商物分離、アウトソーシング、日々の作業管理(商品改廃・在庫・ロケーション、日付管理、etc)の充実、物流現場のデータ収集・分析、物量に応じた要員確保(人員計画)と適正人員の配置、品質・精度、サービス性を落とさない運用の実現が必要です。大手小売りチェーンは、納入業者毎に自社のレイアウトにあったカテゴリー別納品、什器・ゴンドラ別納品、通路別納品などを求めています。 そして、店舗の販管費の削減を優先するためにノー検品化、品出しの省力化、納品業者の集約、週別納品回数の削減、時間帯、機能集約などで高い納品精度、納期の遵守、納品業者別、カテゴリー別などの損益管理、庫内現場作業コストの削減、納価への反映、情報と現品在庫の一致、過剰在庫の適正化のための市場出荷動向(マーケットイン)に合わせた在庫量の適正維持、そして、継続的な改善活動を支えるマネジメント力を伴った物流人材の育成、特に物流現場の最高責任者である現場に精通したセンター長の育成が求められています。
(C)2019 Kiyoshi Takano & Sakata Warehouse, Inc.