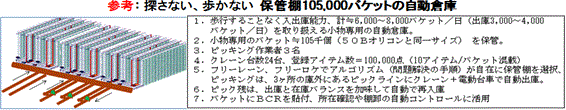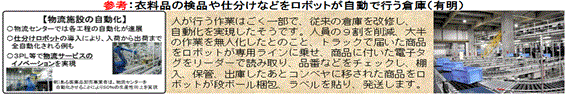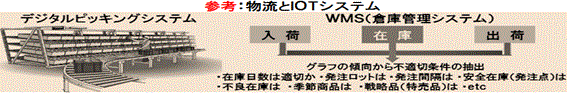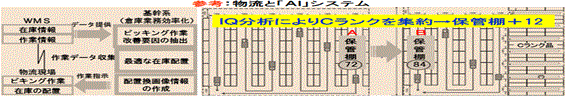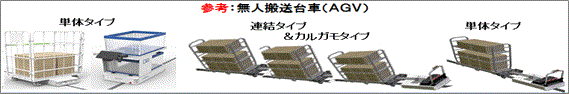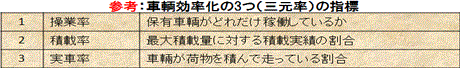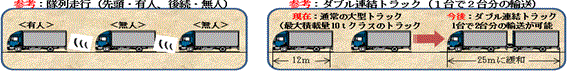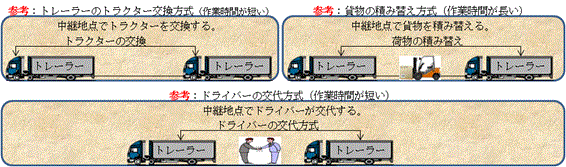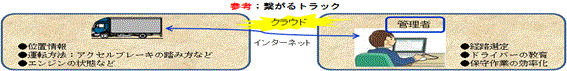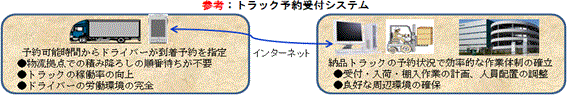第428号 次世代物流(100年に一度の変革)を探る(考える)(後編)(2020年1月21日発行)
| 執筆者 | 髙野 潔 (有限会社KRS物流システム研究所 取締役社長) |
|---|
執筆者略歴 ▼
目次
6.次世代物流で進化する拠点内(物流センター)物流
IOT(モノのインターネット)は、世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ、インターネットに接続、相互に通信することで自動認識や自動制御、遠隔監視などを行うことができるようになります。
既に普及しているDPS(デジタルピッキングシステム)、WMS(倉庫管理システム)、スマートグラス(コンピュータ搭載の眼鏡)が充実していくものと思われます。
AI(人工知能)は技術開発の段階にあり物流シーンの活用はこれからだと思われます。
今後、AI音声認識物流システム、AI画像認識物流システムなどを中心に拡大していくとみられます。
例えば・・・WMS(倉庫管理システム)は、システムに蓄積されているデータを基幹系に提供、基幹系では、保管率向上とピッキング作業の効率化のための在庫配置の最適化、ピッキング作業の実績などを分析、さらに施策の評価・改善で在庫配置の継続的な最適化を実施することと、その最適化でピッキング効率の向上に繋がる棚配置などが考えられます。
2025年までに経産省の後押しで「コンビニ電子タグ1,000億枚宣言」がスタート、RFIDは電波を用いてタグデータを非接触(無線)で読み書きするシステム、複数タグの一括読み取りができるといった利点から、様々な物流シーンで活用されると思われます。
ケースやパレット、台車にRFID(電子タグ)を取り付け、ゲートやRFIDセンサーで情報(データ)を読み取ることができます。
狭い通路でも自由自在、様々な物を自動搬送、ネット通販市場の拡大で小型の搬送物が増加、これからは、労働力不足、自動化促進を背景に自律走行型の無軌道タイプやアーム付AGVの導入が進みそうです。
7.次世代物流で進化するトラック輸送
いま、トラック輸送(大型)は、大きな変革期を迎え、これまでの成功モデルを受け継ぐだけでは成長できないと言われ、技術革新で着々と進化するトラック輸送があります。
検討されているものとして隊列走行、ダブル連結トラック、トラクター(ヘッド)交換方式、ドライバー交代方式、繋がるトラック、トラック受付予約システムなどがあります。
その背景としてこれからの労働力不足、現在の輸配送コストが物流費の半分以上を占め、輸配送コストの改善が益々重要視される時代がくると思われるからです。
コストの低減を運送業者と交渉しても「これ以上の値下げは限界」と言われ、また、輸配送コストの管理は委託業者に任せきりで内容がよく分からずコストダウンができない、物量の波動が激しく、常に車輌を多めに手配しなければならないなどの背景があります。
輸配送は、対顧客物流・サービス維持を前提とした効率化が必須で車輌効率化には、大きく3つ(三元率)の指標があり、これらを定量的に捉え、輸配送の特性と車輌効率化視点の組み合わせをもとに実際の効率化施策に繋げていきたいものです。
これからは、コストウェートの高い輸配送をいかに効率化して様々な物品をローコストで顧客に届けられるか、働き方改革と自動車運送事業、取引関係の適正化などの改革が最重要課題となると思われます。
さらに、ドライバーの高齢化や未経験者の雇用で安全・安心教育の強化、作業の効率化、生産性向上、ドライバーの負担軽減などを柱に多様な人材の確保・育成が検討され、IT(情報技術)を活用した最先端技術やシステムの開発・導入が進んでいくと思われます。
ドライバーの労働時間の短縮に向けて高速道路のSA、PAを中継地点として長距離運行を複数のドライバーが分担、日帰り勤務を可能にしようとしています。
輸送の効率化、ドライバーの安全教育では、車載通信機とインターネットで位置情報や運転情報などを管理する「繋がるトラック(コネクテッドカ―)を2020年には、国内で50万台規模の普及が見込まれています。
さらに、運送事業者と荷主が走行車両の運行情報を共有することで輸送効率、安全、車両保守などの向上を図る保有車両の全てに車両動態管理システムを導入し、空車回送率の改善、取引先や消費者への情報開示を進める予定だそうです。
ドライバーが物流拠点への到着時刻を事前に予約できる「トラック予約受付システム」で荷物の積み降ろしの待ち時間を減らし、トラック稼働率向上が期待されています。
8.最後に・・・。
次世代の物流拠点の動向は、物流現場の人手不足の深刻化など、社会の大動脈である物流の課題解決のための自動化・ロボット化、IoT、AI技術とWMSなどのネットワーク(無線通信網)を活用し、人間依存から省人化、効率化を実現するための各種の手法を取り入れた次世代物流への取り組みが始まっています。
さらに、深刻な人手不足が自動化の加速と物流業界でも技術革新競争が始まっています。
これは「EC(電子商取引)市場の拡大」と「AIやロボットなどの技術革新」などの背景に加えて人材不足という難しい課題が引き金となり、自動化ニーズが加速しています。
物流の自動化の軸は「自動倉庫システム」と「搬送ロボット」だと考えます。
昨今、アマゾンやユニクロ、ニトリなどの物流拠点の「自動化」が話題になっています。
物流業界においても、工場と同じく「自動化」のニーズが強くなってきています。
次世代の物流拠点の完全自動化を目指す研究は、活発ですが巨額の投資を必要とし、物流の多岐多彩である動作を確実に実行するには、まだ課題が多いと言われています。
最後に次世代の物流システムを導入する際には、イニシャルコスト(初期費用)、ランニングコスト(保守・維持管理費)を含めた物流コストの収支試算(投資対効果)での判断が重要と考えます。
次世代物流の一端を知り、これからの物流に携わる人達の活躍の一助になれば幸いです。
以上
(C)2020 Kiyoshi Takano & Sakata Warehouse, Inc.