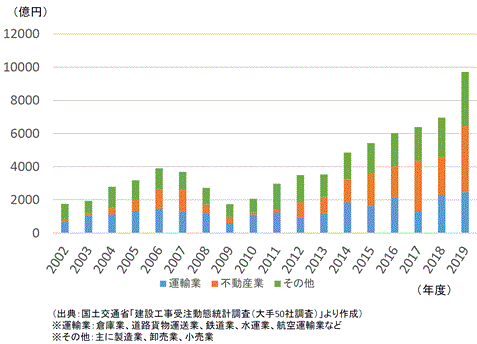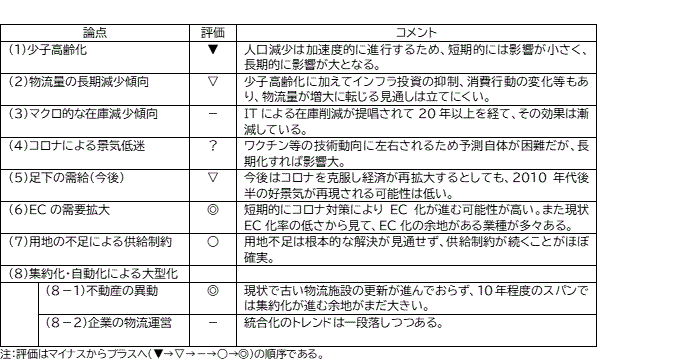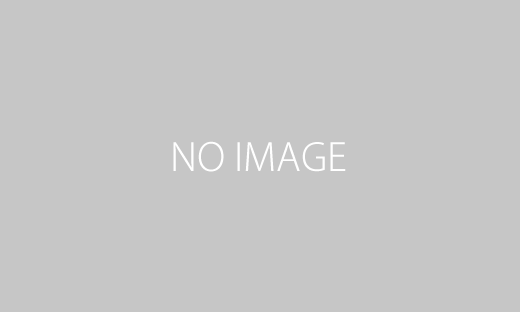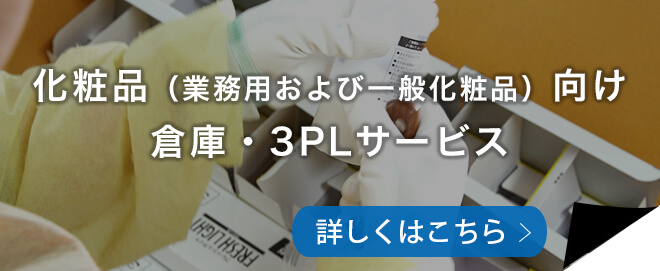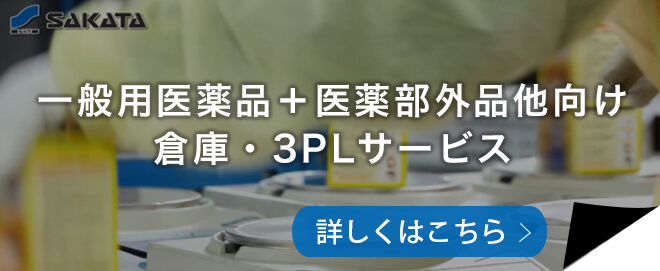第458号 物流施設は建てすぎなのか?(2021年4月20日発行)
| 執筆者 | 久保田 精一 (合同会社サプライチェーン・ロジスティクス研究所 代表社員 城西大学経営学部 非常勤講師、運行管理者(貨物)) |
|---|
執筆者略歴 ▼
目次
1.はじめに
近年、物流施設の建設が高水準で進んでいる。2019年度は近年最高水準であり、2020年度はコロナ禍により失速するかと思われたが、実際には引き続き高水準を維持している(本稿執筆時点、年度前半までの実績)。
ただし、マクロ的に見ると、以下のような論拠から「物流施設は建てすぎなのではないか?」との見方がある。
(1)少子高齢化で人口は確実に減少する。今後は毎年中核市が一つずつ消えていくほどのスピードで減少するのだから、施設需要も減るはずだ。
(2)そもそも物流量は長期的に減少している。貨物輸送量(トンベース)は最盛期である平成初期の7割程度しかない(なお、物流量の減少は人口減の影響もあるが、平成年間の主たる減少要因は、建設ストックへの投資縮小と長寿命化である)。
(3)マクロ的な在庫量は、企業の在庫削減努力やITの進展によって減少している。
(4)上記の要因に加えて、コロナ禍によりグローバル化にブレーキが掛かり、当面は世界的に景気が調整局面入りする可能性が高いのではないか。
ただし、この論点は、各所でさんざん議論されてきた問題であり(※)、すでに議論の余地がないとも言える。
(※例えば月刊ロジビズ・2020年10月号「物流不動産」特集、流通ネットワーキング・2020年9-10月号特集「物流センターの開発と運営」などを参照。)
一方で、議論のベースとなっているレポートの多くは、物流施設の開発者側が、開発のポテンシャルを確認するために作成しているものが多い。だから中立性に問題があるのだ、と言いたいわけではないが、ある時点での開発ニーズとマクロ的な総需要とでは、傾向が必ずしも一致しない(例えば、住宅分野で、空き家が社会的に問題化するのと同時に、新築マンションの供給が高水準であったとしても、矛盾はしないことと同様である)。
このような点を踏まえて、本稿ではマクロ的な需給状況の視点にたち、主要な論点を整理しておきたい。
2.「需要は堅調である」サイドの論拠
上述の「建てすぎ」論に対しては、様々な観点から反論が挙がっている。主要な論拠は以下のとおりである。なお余談ながら、この分野の有識者の中では(いまのところ)、これら論拠をもとに「需要は堅調だ」との立場が主流である。
(1)足下の需給(現に新しい倉庫は埋まっている)
次々に大型倉庫が新規供給されているが、結果的に埋まっている。よって需要はある、という立論。
(2)ECの需要が拡大する
人口減でも施設需要が減らないのは、EC(特にネット通販)の需要拡大が続くからである。
(3)土地がないから供給過多にはならない
需要が過多なら供給が増えることでバランスするのが通例だが、現状でそうなっていないのは「土地不足」による。
(4)集約化・自動化で大型化する
これは施設需要の総量が増えるという主張ではないが、物流拠点は集約化・統合化される傾向にあるため、小規模な既存拠点ではなく、新たな大型拠点のニーズが増える。
3.前項の論拠の検証
これらの主張の論拠について、一点ずつ検証していこう。
(1)足下の需給について
「実際に埋まっている」というのは現時点では明らかであり、従って需要がある、という点についても異論を差し挟む余地はなさそうだ。
この論拠の問題を挙げるとすると、「過去に供給された倉庫が埋まること」は、「将来供給される分に相当する需要が生まれること」の説明要因とはならないということだろう。言うまでも無く、「前者の説明要因(説明変数)が、後者でも引き続き有効である」ことの証明が必要だ。
この説明要因は(2)で触れるEC拡大などだが、以下で触れていないなかで重要なものは、景気動向である。周知のとおり2010年代中盤から2018年末まで続いた景気拡大局面は、バブル期以降で最長の好況期であった。荷主は売上や物流量が拡大する場合は、相応のコストをかけて保管スペースを確保するため、当然、物流施設の需給にプラスに働いてきた。これがコロナ禍を受けて今後、どのように変化するか(しないか)がポイントとなる。
(2)EC需要拡大について
ECの需要は世界的に急速に拡大しているうえ、コロナ禍でさらに加速している。ECが拡大しているということは、逆にリアル店舗の売り上げが減っているということになり、施設需要を相殺する側面もある。しかし一般にEC対応の物流センターは小ロット、多頻度出荷となり、必要な坪数は広くなるため、施設需要にはプラスに寄与すると考えるのが妥当だ。また、アマゾンのように、物流施設の増設につぐ増設をしている企業があることも実需面で説得力がある。
さて、今後の需給を占ううえでのポイントは、「ECがどこまで拡大するか」である。「総取引額に占めるEC取引額の割合」を「EC化率」と言うが、世界各国のEC化率を見ると、日本は諸外国よりも低い傾向がある。コンビニが象徴的だが、日本は欧米と比べても小売り店舗網が稠密で、リアル店舗の利便性が高い。そのためEC化率が低いのが現状だが、逆に言えば、今後の拡大余地が大きいとも言える。
一方、日本でECが本格的に普及し始めてからすでに20年以上を経過しており、ECへの親和性が高い商材の多くは相当部分がECに移行済みであるのはマイナスだ。家電、事務用品、書籍などすでにEC化が3~4割を超えている商材については、それほど伸び代はない。また、今後ECが伸びる過程で、ウーバーイーツのようなリアル店舗からの配送が拡大するなど、従来のEC物流の流れとは異なる展開をたどる可能性もある。当面はECの拡大によって物流施設の需要も拡大するといって良いが、それ以降は不透明とも言える。
(3)用地不足による供給制約について
需給がタイト化する要因の半分は供給の制約だ。特に需要が旺盛な首都圏ではまとまった用地が確保できず、物流施設需要に応えることが出来ていないという見方が強い。主要な用地の供給源であった工業団地や工場跡地などの物流適地は概ね開発済みである。90年代は工場の海外移転で遊休地が続々と供給されたが、オフショア化の動きも逆流しつつある。あとは、(物効法などを利用して)農地・市街化調整区域等を転用するといった手法をとることでしか、大規模な供給は見込めない。供給制約が引き続き厳しい場合には、新規供給にはシーリングが課される状況になり、需給面はプラスに作用するが、この点の見通しはどうだろうか。
土地利用計画の今後は、国・地方の都市計画行政次第だが、今のところ、物流を考慮して都市計画の仕組みを見直すような動きはない。中長期の施策を示す国の総合物流施策大綱などにも、関連する記述は見られない。この点には深入りはしないが、今後も根本的な変化は見通しづらい。
なお、市街化調整区域の転用を進める点では、物効法(物流総合効率化法)への期待は大きく、埼玉県など特定の地域を中心に活用が進んでいるが、件数や面積で見る限り広域的・マクロ的な需給を左右するほどの規模ではない。
(4)集約化・自動化による大型化について
近年、物流拠点は大型化する傾向が見られ、統計上からも確認できる。これは不動産としての物流施設の異動という側面から言えば、中小の物流施設が閉鎖し、大型の施設が新規に供給されているということになる。これを物流施設のユーザーである企業の物流運営の側面から見ると、企業の物流網を構成する物流センターが、かつては中小規模のものが多数あったが、近年は大型のセンターに統合されているということになる。
この両者は、一つの現象の表裏の関係でもあるが、その背景にある事情は必ずしも同じではないので、それぞれ分けて論じる。
(1)不動産の異動としての側面
一般に物流施設(特に営業倉庫)は建築物としての寿命が長い。そのため今でも高度成長期に建設されたような老朽化した拠点が多数現存している。これらの古い拠点は一般に小規模であり、レイアウト上も利用効率が悪い。
そのため立て替えが必要だが、小規模な敷地では立て替えても逆に建設坪単価が高くなってしまい、大規模施設と比肩できるような競争力を発揮しにくい。
これに加えて旧来からある倉庫街は交通インフラとのアクセスが良好な場合が多く、従来の物流用途で施設更新するよりも、他用途に転換するほうがメリットがある場合が少なくない。このような事情から、例えば東京湾岸部等では、マンションやオフィスへの転用が非常に多い。物流関連で施設更新する場合であっても、高付加価値な領域、例えばトランクルーム、美術品や書類・データ保管センターなどの用途で衣替えするケースも目立つ。
このような異動は、統計からも確認できる。
図表2、3はいずれも法人土地・建物調査のデータ(東京都)を引用したものである。
図表2を見ていただくと、過去10年間で、都内の「倉庫」の面積はわずか5%しか増えていないことが分かる。一方、同じ期間に1建物あたりの延べ床面積は、55%も増大している。この統計は新築だけでなくすべての建物(法人所有等の限定はあるが)を対象とした調査であることを踏まえると、驚異的な伸びだと言える。
図表3は同じデータを、延べ床面積の階層別に見たものである。小規模な倉庫(特に2千平米未満)が減少している一方で、2万平米以上の倉庫が急増していることが分かる。
このデータからも、都市部から小規模な施設が言わば「追い出されて」、大規模な拠点に集約化されるという現象が、物流施設の大規模化のトレンドを後押ししているであろうことはかなり明白である。
この現象は「施設の場所がシフトしただけ」とも言え、物流施設への実需と言えるかどうかは疑問の余地がある。しかしながら、依然として都市部に中小規模の倉庫が多数存在すること、その継続運営には(上述のとおり)経済合理性がないことを踏まえると、今後も大規模化を促す要因となりうるだろう。
(2)企業の物流運営の側面
企業の物流運営の側面から見ても拠点の統廃合が進んできた。統廃合の進展を促してきた要因は実は多様だが、主なものとしては以下の3点を挙げることができる。
1つは、「拠点の広域化」だ。ナショナルブランドの日用品、食品メーカーは、かつては都道府県ごとに在庫拠点を持っていた。これが、圏域ごとに一つに集約され、東日本、西日本の2拠点に集約され、というふうに集約されてきた。この背景にあるのは、道路網の整備、情報システムの高度化(在庫情報の一元化等)である。
2つめの要因は、「企業の統合化」である。日用品、食品などの卸売業で特に顕著だが、従来存在した地域単位の中小の卸は、M&Aで統合化が進んだ。その結果、主流の企業はいずれも、売上高が数千億~数兆円規模へと大規模化が進んだ。この過程では、品種のフルライン化も進展した。例えばかつて食品卸はさらに細かい品種ごとに棲み分けがあったが、その多くは統合化され総合卸へと変貌した。なお、実物流を担う物流事業者の統合による効果もこれと同様である。
3つめは、「サプライチェーンの縦方向の統合化・直送化」だ。かつては製造→産地卸→消費地卸→小売といったように多段階での物流が一般的だった。流通の多段階性を表す指標として、W/R比率(卸/小売比率)というものがあるが、90年代頃にはこの数値が日本の流通の非効率の象徴として挙げられていた。このような多段階性は、過去20年ほどの間、徐々に適正化が進んだ。特に物流の実態面ではメーカーから小売への直送化等が進んだ。言うまでも無く、このような縦方向の統合化の帰結として、物流拠点の大規模化が進展してきた。
以上の3つの要因が挙げられるわけだが、その今後の見通しはどうだろうか。1,2の要因は明らかに収束傾向にある。特に1番目の要因は、むしろ拠点統合化によるコストやリスク(災害被災リスク、感染症リスク)が懸念されている状況であり、分散化に舵を切っている企業もある。
一方、3番目の要因については、まだ流通の多段階性には合理化余地がある。例えば卸が巨大化する過程で、小売業の専用センターとの業務の重複が生じており、その統合化が課題だ。また、SPA(製造小売業)のような業態がサプライチェーン全体の構図を塗り替える動きがアパレル、家具などで進行しているが、この動きはこれから他業種に波及するとみて良い。
このように状況は様々であり一言ではくくれないが、全体としては「統合化」と「分散化」がバランスするフェーズへと進行しているとみるのが妥当ではないか。
4.まとめ
以上では様々な論点を見てきたが、全体を概観するために図表4のとおり整理した。性質の異なる論点が混在しており、同一の尺度で評価できるようなものでないことは当然だが、暫定的な結論を出すため、筆者の主観で影響の大きさを評価して見た。
物流施設需要の拡大を説明する際、(6)のECの影響で語られる場合が多いが、上述し、図表でも示したように、それ以外の要因によるプラス側への寄与も大きい。一方、マイナス側の要因は「少子高齢化」など、確実性が高いものばかりだが、その多くは予測可能で、すでに織り込み済みである。問題は(4)のコロナによる影響だが、これはワクチン等の開発次第であり、予測が困難と言わざるを得ない。
以上を踏まえて個人的な意見を述べると、2020年代前半程度の中期的スパンで見る限りは、プラスの要因がマイナスを凌ぐ蓋然性が高いように思われる。ただし、プラスの要因はいずれも数十年単位で長期的に継続する性質のものではない。従って長期的には、より継続性・確実性が高いマイナスの要因が勝る可能性が高いと思われる。
物流施設についてはベースとなるデータが少なく、定量的な議論が難しいのが難点だが、逆に言えばデータさえあれば精度の高い予測も可能である。なかなか個人で取り組むのは難しいテーマではあるものの、本件は企業物流の今後を占ううえで重要テーマであり、今後も検証を進めていきたい。
以上
(C)2021 Seiichi Kubota & Sakata Warehouse, Inc.